セカンドキャリアとは?企業による支援策と人材採用のポイント
 更新日:2025.06.18
更新日:2025.06.18
 公開日:2024.08.23
公開日:2024.08.23
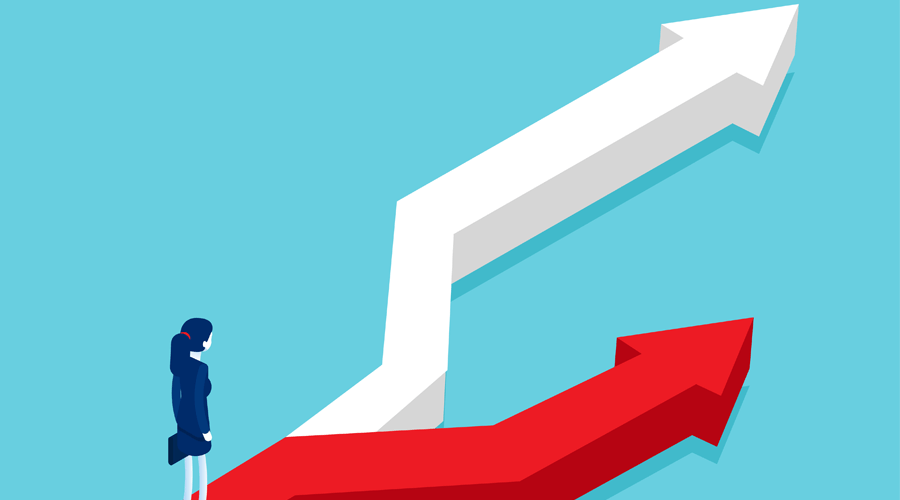
人生100年時代を迎え、退職後のキャリア形成、転職や再就職を伴うキャリアプランの変更など、セカンドキャリアへの関心が高まっています。
本コラムでは、セカンドキャリアの意味や重要性、年代別の特徴、企業による社員のキャリア支援策について紹介します。さらに、セカンドキャリア人材を採用するメリット、注意点なども併せて解説します。
セカンドキャリアとは
セカンドキャリアの概念は、社会の変化や個人の価値観の多様化に伴い、その意味合いが少しずつ変化してきました。
まずは、概念の変遷と、現代におけるセカンドキャリアの意味について見ていきましょう。
従来のセカンドキャリア
日本では終身雇用が広く根づき、以前は「1つの会社で定年まで勤め上げる」という働き方が主流でした。そのため、セカンドキャリアという言葉は長年勤めた職場を離れた後の選択肢と捉えられており、主に、ビジネスパーソンの定年退職後やプロスポーツ選手の引退後に就く「第二の人生における職業」を指していました。
現代のセカンドキャリア
近年は、キャリアの選択肢が多様化し、セカンドキャリアの概念は「長期的なビジョンに基づいたキャリアチェンジ」へと変わっています。
例えば、かつてはネガティブに考えられることもあった20代・30代の転職も、現在は新たなキャリアの構築として前向きに捉えられています。
さらに、副業解禁の流れを受け、副業やフリーランスとして新たな領域に挑戦する動きも活発化してきました。これも将来的なキャリアの選択肢を広げる「セカンドキャリアの準備段階」といえるでしょう。
こうした中、セカンドキャリアは「定年後の選択肢」にとどまらず、ライフステージに応じて柔軟にキャリアを構築することを指すようになりました。
セカンドキャリアが注目される背景
セカンドキャリアへの関心が高まっている背景には、長寿社会における人生設計の変化、女性の社会進出、働き方の多様化など、様々な要因があります。
では、こうした要因は、セカンドキャリアを考える個人の意識にどのような影響を与えているのでしょうか?
長寿社会における人生設計の変化
日本は世界トップクラスの長寿国であり、平均寿命は年々延びています。厚生労働省の平均余命の調査によると、2023年の男性の平均余命は81.09歳、女性の平均余命は87.14歳でした。50年前の1973年と比べて、男女ともに10歳以上延びています。
<平均余命の推移>
| 調査年次 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1973年 | 70.70歳 | 76.02歳 |
| 1993年 | 76.25歳 | 82.51歳 |
| 2023年 | 81.09歳 | 87.14歳 |
このように、定年退職後の人生が20~30年に及ぶことが一般的になり、「定年後どう生きるか」「どのように収入を得るか」といったキャリア設計の重要性が高まっています。
長寿社会においては、定年退職後の再就職や独立など、様々な選択肢があります。そのため、定年前の段階から、セカンドキャリアに向けた準備を進めることが大切です。具体的には、新たな分野への挑戦やスキルの習得、必要に応じて資格の取得なども有効といえます。
こうした取り組みが、その後の人生における選択肢を広げ、生涯現役で活躍するための鍵となります。
女性の社会進出
出産や育児を機に離職する女性は依然として多いものの、近年、出産後も就業を継続する女性の割合が増えています。
厚生労働省の調査によると、2000年~2004年に第1子を出産した女性のうち、就業を継続した人は27.5%でした。これに対し、2015年~2019年に出産した女性のうち就業を継続した人は53.8%に増加。約15年で、育児後に仕事を続ける女性の割合が2倍近くになりました。
この背景に、社会全体で女性の職場復帰や再就職を支援する機運が高まっていることが挙げられます。
育児休業制度やリモートワークの普及が進み、ワークライフバランスを重視した働き方が広がっているのです。また、離職期間中に得た経験を活かして、新たな分野へ挑戦する女性も増えています。企業側も多様な働き方を受け入れるようになり、女性のセカンドキャリアを支援する動きが活発化しています。
出典:「第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況」(厚生労働省)
働き方の多様化とライフスタイルの変化
近年、終身雇用や年功序列といった従来の雇用システムが見直され、フリーランスや起業など、自分らしい働き方を求める人が増えてきました。育児や介護といったライフイベントと並行して、ワークライフバランスを重視しながら、キャリアアップを目指す傾向が強まっています。
企業側も、人材不足の解消や離職防止策として、リモートワークやフレックスタイム制の導入、副業・兼業の自由化など、多様な働き方を受け入れ始めています。
こうした社会全体の変化が、自分らしいキャリアの追求につながり、セカンドキャリアに対する関心の高まりを後押ししているのです。
セカンドキャリアは何歳から?年代別の特徴
セカンドキャリアを考え始める時期は、人によって異なります。ここでは、30代、40代、50代のセカンドキャリアの特徴について解説します。
30代:キャリアの模索とスキルアップ
30代は社会人経験を積み重ね、自身のキャリアパスについて見つめ直す時期です。入社時に描いていたキャリアビジョンと、現在の仕事内容やスキルのギャップに悩む人も少なくないでしょう。
また、結婚や出産、育児といったライフイベントを迎える時期でもあるため、ワークライフバランスを意識したキャリア選択が求められます。体力やバイタリティーも十分あり、新たなスキルの習得やキャリアチェンジに挑戦する人が多く見られます。
40代:専門性の向上と長期的なキャリア形成
40代は、管理職や専門職としてのキャリアを積み重ねながら、今後のキャリアパスやライフプランについて真剣に考え始める時期です。
仕事面では、これまでの経験を活かしつつ専門性をさらに高めることが求められるでしょう。他方、プライベートでは子育てが本格化し、ワークライフバランスの重要性を実感する人も多い時期です。子育てがない場合でも、ファーストキャリアの目標を達成し、次のステップを考える人もいます。
このように、40代からのセカンドキャリアには、仕事とプライベートの両立を目指し、長期的な視点でキャリアを形成する傾向があります。
50代:定年後を見据えた準備と新たな挑戦
50代は、定年退職後のシニア世代の生活や働き方について具体的に考え始める時期です。
仕事面では、これまで培ってきた経験やスキルを活かして、後進の指導や育成に力を注ぐ人もいれば、独立や起業、社会貢献活動など新たな挑戦をスタートさせる人もいます。
一方で、老後の生活設計や親の介護問題など、新たな課題に直面するケースも少なくありません。
こうした事情から、ファーストキャリアが一段落したあとの安定した生活に向けて、収入源を確保しつつ無理のない働き方で目標が達成できる仕事を模索する傾向があります。
企業や行政によるセカンドキャリア支援
近年、企業だけでなく行政もセカンドキャリア支援に力を入れています。適切な支援があれば、従業員の選択肢が広がり、企業にとっても人材の定着や組織の活性化につながります。ここでは、企業と行政が行うセカンドキャリア支援とそのメリットについて解説します。
セカンドキャリア支援とは
セカンドキャリア支援とは、従業員が現在の職業を離れ、新たなキャリアに挑戦する際に企業や支援機関が提供するサポートのことです。具体的には、スキル向上のための研修、転職や起業の支援、働き方の柔軟化などが含まれます。これらの支援により、スムーズなキャリア移行が可能になります。
企業が導入できるセカンドキャリア支援策
企業によるセカンドキャリア支援には、様々な取り組みがあります。以下の表に、各支援策の概要をまとめました。
| 支援の種類 | 概要 |
|---|---|
| キャリア研修の実施 | 長期的なキャリア形成を支援する研修。30代・40代の社員を対象とした早期のキャリア研修を含む。 |
| リカレント教育の推進 | 語学、IT、介護・福祉など、社員の業績アップやスキル向上につながる学び直しの促進。教育機関や職業訓練校への入学、セミナー、自社研修の実施。 |
| キャリア相談窓口の設置 | キャリアコンサルタント資格を持つ人員の配置。メンタリングやコーチングの提供。 |
| 経済的支援 | 経済的負担を軽減するための支援。給与補償や福利厚生、教育訓練費の補助、キャリアチェンジ支援、ファイナンシャル・プランニング支援など。 |
| 時間的支援 | キャリアチェンジに向き合う時間を確保するための支援。フレックスタイム制度、リモートワーク、転職・開業に向けての準備休暇制度、短時間勤務制度の導入など。 |
| 情報的支援 | セカンドキャリア構築に役立つ情報の提供。キャリア情報、プログラムおよび研修情報、キャリア評価、異業種交流会の機会など。 |
| 社外副業・兼業の許可 | 副業・兼業の自由化による多様な経験の蓄積、スキルアップの推進。 |
| 再雇用制度 | 定年後の再雇用制度、短時間勤務、嘱託制度の活用により、経験豊富な社員の活躍を支援。 |
行政や支援機関によるセカンドキャリア支援の具体例
企業だけでなく、行政もセカンドキャリア支援のための制度や助成金を提供しています。これらを活用することで、従業員のキャリア移行が円滑に進むだけでなく、企業側も研修や再就職支援を効率的に進められます。以下に、主要な支援制度をご紹介します。
-
キャリア形成サポートセンター
厚生労働省が推進するジョブ・カード制度(個人のキャリアプランの作成や職業能力の証明のためのツール)を活用した、企業の人材育成・採用選考などの支援
-
人材開発支援助成金
企業が社員に職業訓練を行う際に、経費の一部や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度
-
教育訓練給付制度
雇用保険の被保険者が厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講する際に、教育訓練経費の一定割合をハローワークから支給する制度
セカンドキャリア支援で得られる企業のメリット
社員のセカンドキャリアを支援することは、離職者の増加につながるという懸念があるかもしれません。しかし、適切なセカンドキャリア支援を行えば、企業にとって様々なメリットが生まれます。以下に主な利点をまとめました。
| 主なメリット | 内容 |
|---|---|
| 社員の意欲向上 | セカンドキャリア支援を通じて、社員が自身のキャリアビジョンを明確化することで、目標達成に向けた意欲や、仕事や学びへのモチベーションが向上する |
| 企業イメージの向上 | 社員のキャリア形成を支援することで、社会的責任(CSR)を果たしていると評価され、ステークホルダーからの信頼を獲得しやすくなる |
| 他社との信頼関係の強化 | セカンドキャリアを見据えた社員に対し、転職先や再就職先を自社でサポートすることで、他社との信頼関係の強化につながる |
セカンドキャリア人材の活用が企業にもたらす価値
近年、企業が抱える課題を解決する手段として、セカンドキャリア人材の採用が注目されています。
自社でセカンドキャリア支援を行った人材や、他社からの転職や再就職を希望する人材を受け入れることで、豊富な経験とスキルを持つ人材の活用が可能になります。ここでは、セカンドキャリア人材を活用することで、企業が得られる価値について紹介します。
(1)即戦力としての貢献
セカンドキャリア人材の多くは、これまでの経験で培った知識やスキルを有しています。特定分野の専門知識や業務経験を持つ人も少なくありません。採用後は即戦力として活躍する可能性が高いでしょう。
特に高度な専門性が求められる職種や人材不足が深刻な業界では、セカンドキャリア人材の採用が、事業の成長を加速させる重要な戦略となります。
新卒採用や若手社員の育成には多大なコストと時間がかかりますが、セカンドキャリア人材であれば、多くの場合基礎的な社会人研修や初期の教育は不要です。セカンドキャリア人材の採用は、人材育成のコストを抑え、効率的な人材投資を可能にさせます。
(2)イノベーションと組織活性化
異なる業界や職種での経験を持つセカンドキャリア人材は、新しい視点や異なる価値観を組織にもたらします。これにより、社内のイノベーションを促し、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。
セカンドキャリア人材には管理職やリーダーの経験者も多く、メンターとして若手社員の育成にも貢献できるでしょう。多様な経験を持つ人材が加わることにより、チームの活性化につながり、組織全体の成長が促進されます。
(3)企業ブランディングの強化
セカンドキャリア人材の採用を積極的に行うことで、多様な人材を受け入れる姿勢があることを示せます。これは、企業の社会的責任(CSR)の観点からも評価される要素となり、企業のブランドイメージ向上につながります。
企業のブランディング強化は、採用や取引先との信頼関係の構築にも好影響を与えるでしょう。
セカンドキャリア人材採用の注意点
セカンドキャリア人材の採用は、企業に多くのメリットをもたらしますが、注意すべき点もあります。採用後のミスマッチを防ぐために、以下の3点について十分な検討を行いましょう。
- (1)採用基準と評価制度の見直し
- (2)柔軟な働き方の導入
- (3)ミスマッチを防ぐためのコミュニケーション
1つずつ解説します。
(1)採用基準と評価制度の見直し
これまでの採用基準や評価制度は、新卒や若手社員を前提としたものが一般的でした。しかし、セカンドキャリア人材は、経験やスキル、価値観が多様なため、従来の基準では適切に評価できない可能性があります。
そこで、セカンドキャリア人材に特化した採用基準や評価制度を見直し、以下のような要素を考慮することが重要です。
- 経験やスキルを活かせるポジションを明確にする
- 実績や成果だけでなく、ポテンシャルやリーダーシップも評価に組み込む
このように、基準を明確にすることで、採用後のミスマッチを減らし、企業の戦力として力を発揮する場を整えられるでしょう。
(2)柔軟な働き方の導入
セカンドキャリア人材の中には、家庭の事情や健康上の理由などから、フルタイムでの勤務が難しい人もいます。そのため、リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入することで、多様な人材が能力を発揮できる環境を整えられます。
年齢や体力に合わせた業務内容の調整、休憩時間の確保など、個々の状況に十分配慮しましょう。
(3)ミスマッチを防ぐためのコミュニケーション
採用後のミスマッチを防ぐためには、企業と応募者双方の期待値、価値観の擦り合わせが重要となります。選考段階から以下の取り組みを徹底しましょう。
- 企業側は、求めるスキルやキャリアパスを明確に伝える
- 応募者には、自身の経験やキャリアビジョン、現在のスキルを率直に伝えてもらう
- 入社後も定期的な面談やフィードバックを行い、状況を確認する
このような取り組みにより、採用後のギャップを最小限に抑え、業務と人材のミスマッチを防止できます。
セカンドキャリアを見据えた社員の成長を支援しよう
セカンドキャリアとは、これまでの経験を活かしながら新たなキャリアに挑戦することを指します。人生100年時代となり働き方の多様化が進む中で、企業にとっても社員の主体的なキャリア形成を支援することが求められています。
ALL DIFFERENTでは、社員がセカンドキャリアを視野に入れながらキャリアを考えるための研修を提供しています。社員のキャリア形成を支援し、組織の成長を促進したい企業のご担当者は、ぜひご活用ください。

