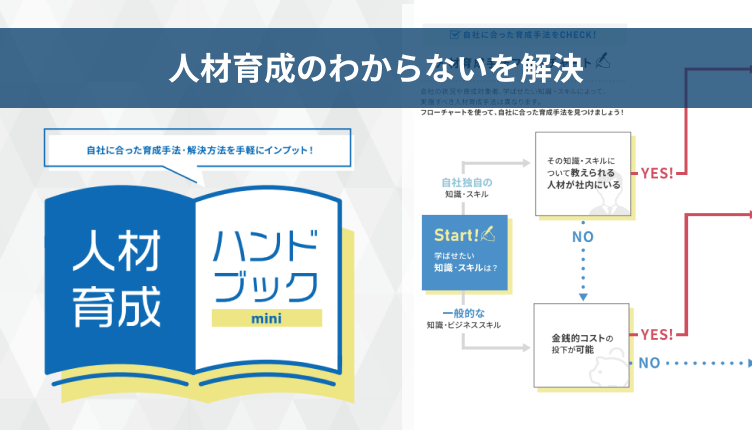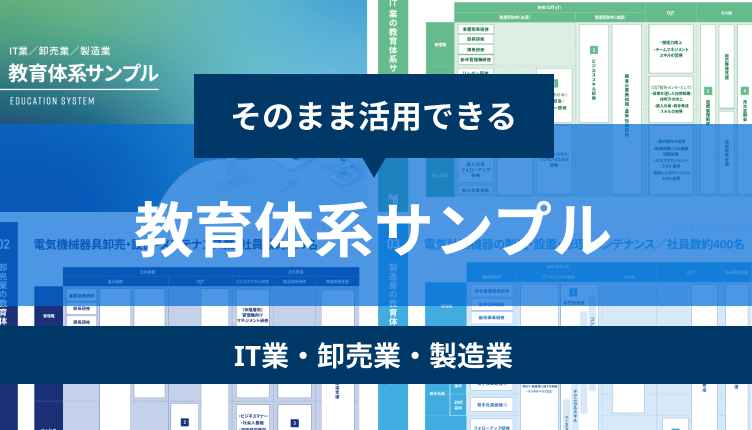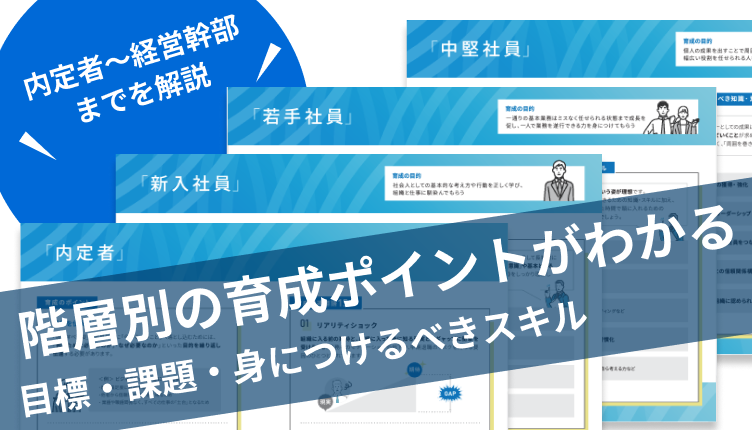キャリアとは?キャリア形成の考え方と会社側にできるキャリア支援
 更新日:2025.03.27
更新日:2025.03.27
 公開日:2022.06.10
公開日:2022.06.10

キャリアとは、仕事を中心とする「経歴」を意味する言葉です。現代のビジネスパーソンには、主体的なキャリアデザインによるキャリア形成が求められています。では、キャリアデザインやキャリア形成とは、何をすることなのでしょうか。
本コラムでは、キャリアデザイン・キャリア形成の考え方と具体的な取り組み方法、便利なフレームワーク、企業が社員のキャリア形成に向けて行える支援などを解説します。
キャリアとは?「キャリア形成」は何をすること?
まずは「キャリア」という言葉の意味を確認し、「キャリア形成とは何をすることなのか」を見ていきましょう。加えて、現代の子どもたちが学校で受けているキャリア教育についても、簡単にご紹介します。
仕事における「キャリア」の意味
キャリアの意味は「経歴」です。英語でも「career」と表記し、日本語の場合とほぼ同じように使うことができます。
広辞苑(第7版)に記載された意味では「(職業・生涯の)経歴」です。*1
そのため、必ずしも仕事の経歴だけを指すものではありません。厚生労働省は、「キャリア」の定義を「過去から将来の長期にわたる職務経験やこれに伴う計画的な能力開発の連鎖」としており、その人の職歴だけでなく成長も含めた概念となっていることがわかります。*2
簡単に言えば、「過去から未来に向けて、どのような仕事をしたのか(したいのか)、そのためにどのような能力を身につけてきたか(身につけたいか)」という経歴全体を意味する言葉であると言えるでしょう。
*1 出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
*2 出典:「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」(厚生労働省)
キャリア形成とは
キャリア形成とは、自分がどのようにビジネスキャリアを歩んでいくかを計画し、その通りに知識・スキルの獲得や経験の蓄積を進めていくことを意味します。
それには、自身がどのような人生を送りたいのかを主体的にイメージ・設計する必要があり、これを「キャリアデザイン」と呼びます。キャリアデザインのポイントは、仕事だけでなく、今後の人生全体を考えること。大切なのは、「働くことや生きることに価値を感じ、自分自身で道を切り開いていく」という姿勢です。
キャリアデザインにおいては、自らのキャリアアンカーも明確にしなくてはなりません。キャリアアンカーとは、自身のキャリア形成で最も重要な価値観のことです。キャリアデザインにおいて「ビジネスでの成功」を掲げる場合でも、あるいは「家庭生活との両立」を掲げる場合でも、より深く「なぜそれを達成したいのか」を問う必要があります。
キャリアアンカーやキャリアデザインの明確化は簡単ではありません。しかし、「こうしたい」というはっきりとした軸を持てれば、その後のキャリア形成でブレが生じにくくなります。「キャリア形成の第一歩はキャリアデザイン」と言ってもよいでしょう。
学校教育での「キャリア教育」
なお、今の新人や若手社員は、学校で「キャリア教育」を受けていることが多いでしょう。文部科学省における「キャリア」の定義は、「人が生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分との関係を見いだしていく連なりや積み重ね」。*1
キャリア教育とは、それぞれの人が社会的・職業的自立に向けて、必要な能力や姿勢を育て、キャリア発達を促す教育です。
キャリア教育は小学校から始まり、中学校・高等学校では職業も意識されます。キャリア教育の中で使われる「キャリア・パスポート」には、
- 1年間の目標
- 目標達成に向けてやるべきこと
- 1年間で頑張ったこと(学習面・生活面・家庭面)
- 教師が記入する“その学年で身につけてほしい能力・姿勢”
- “その学年で身につけてほしい能力・姿勢”に関する自己評価
などが記入され、学年が上がるほど職業や社会生活を意識した内容へと発展します。*2
今の若手社員はこうしたキャリア教育を受けて育ってきました。新人や若手社員のキャリア形成を促す際は、特に高等学校でのキャリア教育の内容も施策のヒントになるでしょう。
キャリアプランとキャリアパスの違い
キャリア形成について考える際によく見かける言葉に「キャリアプラン」と「キャリアパス」があります。
両者は、理想とする働き方やポジションに向けた計画・プロセスを意味する点では共通しています。しかし、そのプロセスの範囲に違いがあるため、使い分けが必要です。
キャリアプランとは
キャリアプランとは、「今後どのような働き方をしたいか」という観点で作成する長期的計画のことです。計画の対象期間は5年以上であることが多く、その人の人生全体にも関わるプランです。
近年は、あらかじめ応募者にキャリアプランを尋ねる面接、いわゆる「キャリアプラン面接」が行われるようになりました。
企業側が「いずれマネジメント職や幹部として活躍してもらいたい」と思って採用活動を行っている場合、応募者のキャリアプランが「プレイヤーとして第一線で活躍するスペシャリストになる」というものでは、会社からの期待とミスマッチを起こす可能性が高くなります。これを避けることが、キャリアプラン面接の目的です。
あるいは、「キャリアプランシート」を応募者や既存社員に作成させる企業もあるでしょう。キャリアプランシートとは、キャリアプランを記入して共有するツール。これも採用時のミスマッチや、既存社員の異動におけるミスマッチを防ぐためのものです。
キャリアパスとは
他方、キャリアパスとは、“社内における”キャリア形成の道筋を意味する言葉です。キャリアプランは特定の組織に限定されるものではありません。ここに違いがあります。
例えば「将来、営業部長になりたい」という新人の場合、
- 一般社員として自社の営業部に配属される
- 営業の実務で経験を積む
- 営業関連の研修で知識・スキル向上を図る
- 営業の実績や能力を評価されて社内で係長、課長へと昇進する
などの流れが想定されるでしょう。こうした社内でのプロセスを具体的に描いたものが、キャリアパスです。
キャリアパスは、社員が自ら計画することもあれば、会社側が社員に提示することもあります。「この会社の中では、どのようなキャリア形成が可能なのか」というキャリアパスの情報は、社員のキャリアプランに大きな影響を与えるでしょう。
社員のキャリアプランと社内のキャリアパスで重なる部分が大きいほど、その社員には自社で長く活躍してもらえます。
キャリア形成を企業が支援すべき理由
キャリア形成は、社員にとって働き続ける重要なモチベーションとなります。目指すキャリアを実現できるか否かは、本人の人生の価値や幸福度を左右するものだからです。そして、現在の日本は従来の人事制度が崩壊しつつあり、人材の流動化も進んでいます。
今、企業が社員のために進めるべき施策は社員のキャリア形成支援であると言っても過言ではありません。これを理解するため、主な3つの理由を解説します。
終身雇用型の人事制度が“当たり前”ではなくなった
かつては、有力企業に入社すれば定年まで安定した雇用とキャリアが約束されていました。こうした終身雇用制・年功序列制を採用する企業も多く、求職者側の大きな目標は「安定した企業に入社すること」。そのためには、「具体的な職種やキャリアプランを重視する必要はない」と考えた求職者もいたでしょう。
しかし、今は経済状況が変化し、労働力人口の減少やグローバル化といった多数の要因から、終身雇用・年功序列の人事制度は崩壊しつつあります。
2010年の段階で 既に内閣府経済社会総合研究所から終身雇用の継続困難を指摘されていましたが、2018年の「平成30年度 年次経済財政報告」でも、改めて「終身雇用制度や管理職のあり方の改革、マッチング機能の強化等が 必要」と指摘されました。*
「特定の企業への所属・肩書きだけで、生涯の安定した生活が保証される時代は終わった」と言ってもよいでしょう。
だからこそ、
- どのような仕事にやりがいを感じるのか
- どのように自身のスキルアップを図るのか
といったキャリアデザインやキャリア形成が、大変重要になっているのです。
*出典:「第2章 第3節 2 多様な働き方に向けた制度面の課題」『平成30年度 年次経済財政報告』(内閣府)
転職がキャリアアップの選択肢になった
終身雇用制度の崩壊とともに、
「より自分に合う業種や職場で働きたい」
「より高い収入を得られる会社・ポジションで働きたい」
として転職を目指す人が増えています。企業側でも、総合職での人材育成よりもスキル特化型の採用・育成に注目する傾向が高まってきました。
こうした要因から、個人に求められるスキルがより具体化・多様化し、そのスキルが仕事に直結しやすい環境へ変化しています。一人ひとりが自身の強みを自覚し、それを活かしたキャリアを積むことが重視されているということです。
実際、転職に当たって無視できない「キャリア採用」という採用方式では、応募資格や要件に特定のスキルを明記するケースが多く見られます。転職エージェントの利用や求人への応募時に「キャリアシート」の提出が必要なケースも少なくありません。
キャリアシートとは、作成者がこれまで積んできたキャリアを記載した経歴書です。作成するには“キャリアの棚卸し”が不可欠であり、そのキャリアに一貫性がなければ「行き当たりばったりで転職している」などのマイナス評価につながる恐れもあります。
しかし、もし一貫性をもってキャリアを積み重ねていることがわかるキャリアシートであれば、その人材は多くの企業にとって魅力的な人材となるでしょう。
企業が社員のキャリア形成を支援することは、労働市場におけるその社員の価値を高めることを意味します。「あの会社の社員は、本当に力のある人が多い」と評価されることで、会社全体のイメージ向上にもつながります。
働き方が多様化している
終身雇用制度の崩壊と転職希望者の増加に加えて、労働力人口の減少や少子高齢化の問題から、従来の「1日8時間、週5日間のフルタイム勤務」も“当たり前”ではなくなりました。安定した人材確保を行うには、フルタイム勤務ができない人材も採用対象とする必要があるのです。
企業が導入を進めている代表的な施策には、
- 1日6時間などの短時間勤務制度
- 時間単位の有給休暇制度
- 就業時間を固定しないフレックスタイム制度
- 遠隔地の人材も採用・勤務できるリモートワーク体制
- 副業解禁
などがあります。
ほかにも、より自由なキャリア開拓・形成を実現する「パラレルキャリア」や異分野への挑戦を視野に入れた「セカンドキャリア」も注目されるようになりました。
パラレルキャリアとは、「複業」とも呼ばれる働き方で、キャリア開拓のために複数の仕事に従事する働き方。副業とは異なり、どちらの仕事も本人にとってメインとなるキャリアになるものです。一方、セカンドキャリアとは「第二の人生」としての職業であり、定年後の職業生活や、異分野への転職を意味します。
働き方の多様化が進む現在、企業側の人事制度を見るだけでは、自身のキャリアの見通しを立てることが困難になりました。社員に求められているのは、自ら自律的にキャリアプランを立て、その実現を目指して取り組む姿勢です。
企業としては、社員が様々な選択肢の中から自身に合うキャリアを選択・実現できるようなサポートを行うべきでしょう。厚生労働省もそうした取り組みを重視し、一定の要件を満たせば研修費用を助成する仕組みを設けています。
社員のキャリア開発と企業の成長については、以下の関連コラムでも解説しています。
キャリアデザインの考え方と具体例
とはいえ、キャリアデザインの考え方は決して一様ではありません。その人の仕事の状況や取り巻く環境、仕事に対する価値観などによって異なるものだからです。
ただ、全く何の方向性もないまま一から考え出すのは大変なもの。まずは大きな枠組みである「川下り型キャリア」「山登り型キャリア」から考えてみてはいかがでしょうか。
川下り型キャリア
川下り型キャリアは、仕事を始めたばかりの頃によく見られる考え方です。まだ仕事に慣れていないために全体像が見えず、会社や周囲から大きな影響を受ける点に特徴があります。“急流にもまれながら進む”というイメージです。
川下り型キャリアでは、ゴールを掲げて進むよりも「目の前のことを1つ1つ乗り越え、経験を積み上げていく」という意識が重要になります。全体像が見えていない段階では、事前に緻密な計画を立てるよりも、経験後の振り返りに注力し、挑戦し続ける姿勢をもつことがキャリア形成につながるからです。
会社としては、上司や育成担当者による定期的なフィードバック面談を通じて内省支援を行い、スキルアップへの意欲を後押しするとよいでしょう。
山登り型キャリア
山登り型キャリアは、「次のステップに挑戦する」という段階の考え方です。明確な目標とプランを立てて一歩ずつ着実に進むイメージから、山登り型と呼ばれます。
山登り型キャリアで大切なことは、自分の意思でプロを目指す領域を決めること。本人の意思決定によるキャリア形成が不可欠であり、自身の価値観や仕事の動機といった根幹を自覚し、覚悟をもってキャリア形成を進める姿勢が求められます。
山登り型キャリアの段階で企業ができることは、例えば社内で活躍する人材の特徴(コンピテンシー)やスキルマップ、キャリアパスを提示し、本人のキャリア形成の意向を確認することです。主体的な意思決定ができるよう、目指すキャリアの実現をサポートしましょう。
キャリア形成に向けた4つの取り組み方法
キャリア形成の具体的な取り組み内容を考えるには、「Will-Can-Must」のフレームワークが便利です。「今後のキャリアのイメージがわかない」という場合は、ロールモデルを見つけたり、「やりたくないこと」をリストアップしたりして、キャリアビジョンの形成につなげる方法もあります。
(1) Will-Can-Mustを考える
キャリア形成を考えるうえで重要なフレームワークの1つが「Will-Can-Must」です。このフレームワークにおいて、それぞれの単語は下表のような意味をもちます。
【Will-Can-Mustの意味】
| Will |
今後のキャリアでやりたいこと (例)キャリア形成における目標など |
|---|---|
| Can |
今の自分にできること (例)持っている知識・スキル・経験・得意分野など |
| Must |
目標達成のためにやるべきこと (例)達成すべき売上目標、習得すべき知識・スキル、不可欠な経験など |
Will-Can-Mustの各項目について書き出していくというシンプルなやり方で、キャリアビジョンやキャリアプランの作成につなげる方法です。
もう少し具体的に見てみましょう。
例えば、「3年後までに部長に昇進する」というプランを考えるとしましょう。このとき、「3年後までに部長に昇進する」という目標自体がWillになります。より深く検討するのであれば、「部長になって何をしたいか」「どのように会社に貢献したいか」も考えると、CanやMustを明確化できるでしょう。
まだはっきりしたキャリアビジョンやプランがない場合は、Will-Can-Mustの各項目で以下のような分析・検討を進めてみてください。
【Will-Can-Mustの例】
| Will |
(例)やりたい業務、会社や顧客との関係など |
|---|---|
| Can |
(例)これまでの業績や得意分野、保有資格、対人関係における強みなど |
| Must |
(例)業績などの達成すべき目標、知識・スキルの習得、資格取得など |
このように分析・検討を進めることで、キャリア形成に必要な取り組みの具体的な内容と優先順位が明確になります。
(2)ロールモデルを見つける
また、「キャリアデザインと言われても、何も思いつかない」という人におすすめなのが、「どのような人になりたいか」を考えることです。「こうなりたい」という人が見つかれば、その人にとってのロールモデルとなるでしょう。
ロールモデルは、職場の身近な人や上司、家族、有名人など、誰でも構いません。ポイントは、憧れの気持ちや「かっこいい」という印象をもてる人物であることです。
ロールモデルを見つけられたら、その人のキャリアを調べましょう。着目すべき点は、以下の4点です。
- どのような仕事をしてきたのか
- どのような失敗や危機があったのか。それをどう乗り越えたのか
- どのような知識・スキルがあるのか
- どのような価値観をもっているのか
次に、ロールモデルのキャリアと自身のキャリアを比較しながら、Will-Can-Mustを書き出します。目標とする人物のキャリアと自身の過去・現在を比較することで、これから取り組むべき内容のイメージをより明確化できるでしょう。
(3)「やりたくないこと」をリストアップする
ロールモデル探しがうまくいかない場合や、ロールモデルのキャリアで「自分には難しいかもしれない」と感じる場合は、発想を逆転させるのも1つの手。つまり、「やりたくないこと」のリストアップです。
人によっては、「やりたいこと」よりも「やりたくないこと」のほうが思いつきやすいでしょう。これを利用して、消去法で「これならやってもいいかな」という働き方を探すのです。
「これでもいいかな」という働き方が見えたら、それを実現できるようにCanやMustを分析してみてください。
(4) キャリアアドバイザー/キャリアコンサルタントに相談する
また、「自分だけではうまく考えられない」と感じるなら、キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタントへの相談もおすすめです。
キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタントは、キャリア相談の専門家として、幅広い選択肢から相談者に合う方向性を一緒に検討してくれます。相談する中で、キャリアデザインの様々な理論やフレームワークを活用した分析も進むでしょう。これまでのキャリアの棚卸しと、そのキャリアを活かした納得感のあるキャリアプランを作成できるはずです。
相談する際は、できれば事前に自身のキャリアアンカーや「やりたくないこと」を考えてみてください。これらがあれば、相談を通じて作成するキャリアビジョン・キャリアプランに軸ができます。思いつく範囲で構いませんので、いくつか書き出しておきましょう。
キャリア形成に必要な能力
キャリア形成には、キャリアビジョンやキャリアプランを現実につなげる行動力が必要です。ここで重要なスキルの代表例は、次の4つです。
- 人間関係や社会関係を築く力
- 自分を把握し、成長する力
- 課題を発見し、解決する力
- 計画を立てて実行する力
どのようなスキルなのか、1つずつ見ていきましょう。
(1)人間関係や社会関係を築く力
1つ目は、人間関係や社会関係を築く力です。
人間関係とは、個人同士の関係性のこと。社会関係とは、組織を構成する個人が協働して活動できるように、一定の行動様式を身につけることを意味します。
人間関係や社会関係に大きな課題がある場合、組織の中で働くことは困難になります。多くの同僚と険悪な関係であれば、仕事をスムーズに進められません。組織の一員として活動する際に必要なルールを守れなければ、業務で混乱が生じたり、会社の対外的な信用を落としたりすることにつながるでしょう。
ビジネスパーソンにとって、1人だけで仕事を進められる状況は滅多にありません。それどころか、仲間と連携して進めることで、1人で行う場合の何倍もの成果を出す必要があります。
思い描くキャリアを実現するには、周囲と連携し、顧客と良好な関係を築くスキルが必須なのです。
(2)自分を把握し、成長する力
2つ目は、自身の現在地を把握し、成長する力です。
キャリアプランの実現には、自身を成長させなければなりません。成長するには、自身の現在地と目標とのギャップを正しく認識し、そのギャップを埋めるための具体的な計画を立てる必要があります。
「自分はできる」という思い込みだけでは、そうしたギャップの認識はうまく進まず、成長への道のりが遠回りになってしまうでしょう。自身が抱える課題や苦手な部分を直視することは、苦痛を伴うものです。それでも、「自分には何ができて、何ができないのか」をじっくり見つめることが成長の鍵になります。
「やりがいを感じることは何か」
「得意なことは何か」
「失敗経験に共通する点は何か」
こうした様々な視点から自身の現状を把握し、今後の成長につなげましょう。
(3)課題を発見し、解決する力
ビジネスで活躍するには、そのビジネスや組織、あるいはもっと広く社会全体に潜む課題に気づき、有効な解決策を講じる力が欠かせません。これが、3つ目の能力です。
企業は、社会課題に注目し、その課題の解決・軽減につながる商品・サービスを打ち出すことで利益を生み出しています。そのため、より上位の役職を目指すのであれば、それに応じた広い視野が求められます。自ら社会に目を向けて課題を発見し、解決策になり得るアイデアを出すのです。
課題発見力と解決力を身につけるには、日常の小さな違和感に気づき、改善のための行動を起こすトレーニングを重ねましょう。
「もっと効率よくできないだろうか」
「もっと使いやすくならないだろうか」
こうした小さな課題を見逃さないようにすることが、発見のアンテナと解決力を鍛えるコツです。
(4)計画を立てて実行する力
そして4つ目の能力が、計画を立てて実行する力です。
キャリア形成の際に気をつけたい落とし穴は、“やみくもに転職を繰り返す”などの場当たり的なキャリア選択です。本来のキャリアデザイン・キャリア形成には、計画と実行が不可欠。それまでのキャリアに一貫性を感じられない場合、社内での人事評価や転職したい企業での採用面接などで「キャリアを積んできた」と評価されることは難しいでしょう。
計画的なキャリア形成には、理想とする姿を目標に置き、その実現を目指す具体的な行動計画と実行力が求められます。例えば、最終目標から逆算して段階的な目標を立てる計画力、その計画に沿って行動する力です。
計画力と実行力を鍛えるには、頭の中だけで計画を完結させるのではなく、目に見える形(紙やパソコン画面で表示できる形)で言語化することから始めましょう。目標達成に向けて取り組むべきタスクを細分化し、優先順位をつけて期限を決めることで、具体的なアクションプランを作成できます。
タスクを1つずつ実行すれば、目標達成に着実に近づきます。これが次のタスクを実行するモチベーションにもなるでしょう。
キャリア自律支援で企業ができること
キャリア形成に向けた計画と実行は、社員が主体的に進められることが理想です。ただ、これまでキャリアビジョンを描いたことがないケースや、ビジネスパーソンとしての経験が浅いケースでは、なかなかキャリアプランの作成が進まないこともあります。
会社として社員のキャリア形成を支援するには、自律的にキャリアプランを描き、実行できる環境を整備しましょう。具体例として、今回は4つの施策をご紹介します。
キャリア面談の実施や相談窓口の設置を行う
まず行うべきことは、キャリア面談の実施や相談窓口の設置です。
キャリア面談とは、社員のキャリア形成を実現するために主体的な取り組みを支援する面談のこと。本人がどのようなキャリアを積みたいのかの聞き取り、キャリアパスの提示や現在地の確認などを通じて、キャリアビジョンとキャリアプランを引き出すことが目的です。実現に向けた具体的な取り組みと活用できるリソースの提案もできると、より充実した面談になるでしょう。
ただし、キャリア面談では気をつけるべきポイントがあります。それは、本人の価値観を尊重し、本人の意思でキャリアビジョンやキャリアプランを決定することです。決して上司や育成担当者が一方的に押しつける形で作成してはいけません。
具体的なキャリアデザインがまだ難しい段階にある社員には、先述したように本人にとって「譲れないこと」「やりたくないこと」の洗い出しを行い、今後の方向づけをサポートしましょう。
定期的な面談が難しい場合は、キャリア相談窓口の設置が効果的。面談以外のキャリア相談の機会を確保し、社員のキャリア自律を促す仕組みです。
社員が主体的にスキルアップ・リスキリングできる仕組みを整備する
人材育成施策の一環として、キャリア形成に役立つ能力開発を推進することもできます。
施策例としては、以下のものが考えられるでしょう。
【キャリア形成に役立つ能力開発施策の例】
- 勤続年数や職位に応じた「よくある課題」を理解・解決するための研修の実施
- ITスキルなど新しい技術を習得・向上させるためのオンライン教材の活用
- 出産・育児休業期間でも利用できる学習リソースの提供
- 管理職や役員への登用で必須とされるスキルを示したスキルマップの公表
また、厚生労働省が公表している「グッドキャリア企業アワード」の好事例集には、次のような施策も見られました。*
- 事業内容に応じた技術系資格の取得支援
- 管理職候補者向けの積極的な研修実施
- コンピテンシーの明示と各従業員のコンピテンシー習得状況を踏まえた人材配置
- 自己啓発費用の援助
社員のキャリア形成に際してどのような環境があれば主体的に取り組めるのか、会社として真摯に向き合うことが、成功のポイントです。
コンピテンシーの洗い出しと共有については、以下の関連コラムもぜひご確認ください。
コラム「コンピテンシーとは?意味と評価・面接に使える項目一覧」はこちら
*出典:「グッドキャリア企業アワード 2024 好事例集」(厚生労働省)
キャリアコンサルタントなどの資格所有者を増やす
他者のキャリア相談に応じる職種を「キャリアアドバイザー」や「キャリアカウンセラー」と呼びます。このような相談に対応する専門家の中心は、国家資格であるキャリアコンサルタントに合格した人々です。
社員のためにキャリア相談窓口を設けたり効果的なキャリア相談を実施したりするには、キャリアコンサルタントなどの資格取得を推奨するとよいでしょう。
キャリアコンサルタントの試験は学科試験と実技試験(論述+面接)で構成され、両方に合格すると「キャリアコンサルタント名簿」に登録されます。*1
国家資格保有者として「キャリアコンサルタント」を名乗るには、業務において守秘義務や信用失墜行為の禁止義務が課されているため、社員も安心して相談できるでしょう。
民間資格では、「ビジネス・キャリア検定試験」などがあります。ビジネス・キャリア検定試験は、職種ごとに求められる知識・実務能力を評価する検定試験。2025年1月現在、8分野41試験が実施されています。*2
各試験は就活生・内定者・新入社員向けのBASIC級から部長などのディレクター職向けの1級まで、原則として4等級に分けられている点が特徴です。部下のキャリア相談を受ける管理職として受検する場合、自身のキャリア形成とともに部下のキャリア支援にも役立つ知識を得られるでしょう。
*1 出典:「キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント」(厚生労働省)
*2 出典:中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験とは」
キャリアアップ助成金などを活用する
社員のキャリア形成を支援したくても、人件費や福利厚生のコストが気になるという企業もあるでしょう。そうした費用面の課題では、国による「キャリアアップ助成金」などの活用が選択肢に入ります。
キャリアアップ助成金では、例えばアルバイトや契約社員を正社員に登用することで助成金を受け取れる「正社員化コース」があります。支給要件は、正社員への転換規定を就業規則などに追加し、そのルールに基づいて非正規人材を正社員に登用して実際に6カ月分の賃金を支払うことです。
令和6年度の場合、有期雇用の従業員を正社員に登用すると中小企業で80万円、大企業で60万円が支給されます。さらに、派遣労働者の場合や母子家庭・父子家庭の親である場合、あるいは多様な正社員制度を新たに導入した場合には、支給額の加算もあります。*1
ほかにも、「人材開発支援助成金」の各コースでは、社員に業務上必要となる専門的な知識・スキルを習得させる訓練を計画的に実施した場合に、費用が助成されます。近年はIT分野での人材育成も支給対象に加わりました。*2
うまく活用することで、キャリア形成に必要なトレーニング費用や研修費用を抑えることができるでしょう。
キャリアデザインとキャリア自律支援に研修活用を
働き方が多様化する現代のビジネスパーソンには、「どのような働き方をしたいか」というキャリアビジョンをもって、計画的にキャリアを積むことが大切です。現在の知識・スキルの向上を図るにせよ、リスキリングによるキャリア形成を図るにせよ、キャリアプランの作成と目標達成に向けた行動力は欠かせません。
会社側ができる“第一歩”の支援は、そうしたキャリアプランを描き、キャリア形成を進めるために必要なキャリアデザインの研修です。
多くの企業で人材育成に伴走してきたALL DIFFERENT株式会社では、キャリアデザインの定義や考え方を習得できるキャリアデザイン研修をご提供しています。他の受講者とのグループワークを通じて、本人だけでは気づきにくい思考のクセや偏りを認識したり、他者から見た強みを発見したりする機会にもご活用いただけます。
一人ひとりが自ら進むべき道を明確にし、やりがいをもって働ける組織風土の醸成に、ぜひキャリアデザイン研修をご活用ください。具体的なキャリアプラン作成に必要な知識・スキルの現在地のチェックには、ビジネススキル診断テスト「Biz SCORE」シリーズもおすすめです。