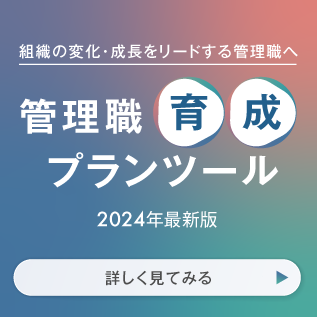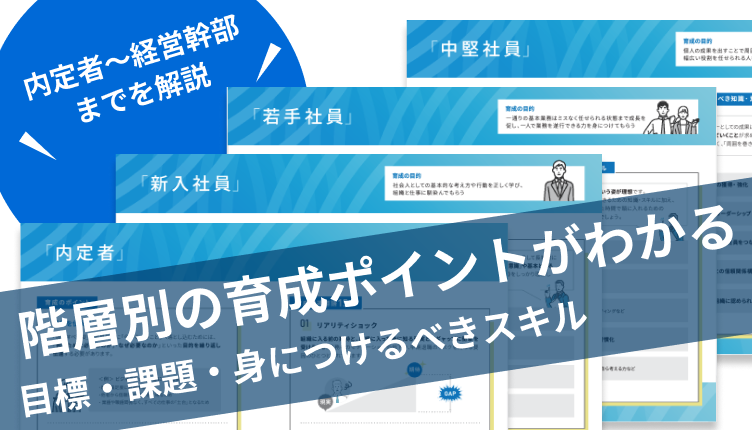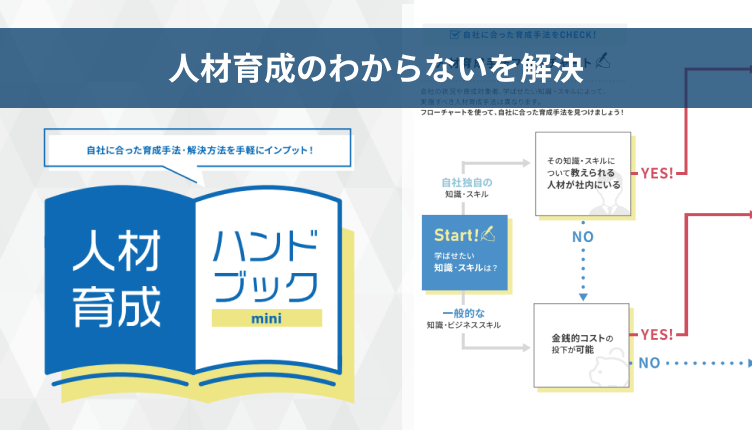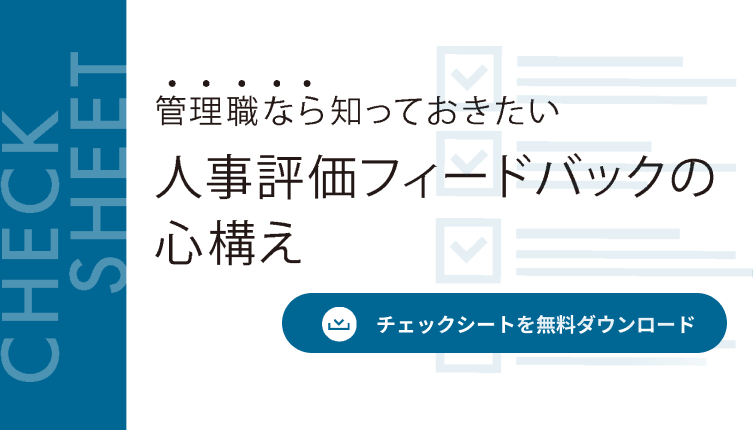管理職とは?一般社員との違い・仕事内容・6つの役割、残業手当など
 更新日:2025.02.06
更新日:2025.02.06
 公開日:2017.12.20
公開日:2017.12.20

管理職とは、企業において大きな権限と責任を持ち、組織目標達成のためにメンバーを指導・管理する職位のことです。給与が上がるなどのメリットがある一方、「やりたくない」「負担が大きい」と感じる人もいるでしょう。
本コラムでは、管理職の定義・種類や平均年収といった基本事項から、管理職の6つの役割、向いている人・向いていない人、時間外労働や休日労働の扱いまで、わかりやすく解説します。
管理職とはどんな仕事?定義と種類
管理職とは、企業の中で一定の権限と責任を持ってマネジメントを行う立場にある社員のことです。労働法などの法令において明確な定義はありません。そのため、管理職の具体的な定義や役割は企業によって異なります。チームや部門を統括し、組織運営に深く関わる職位であるという点がポイントです。
一般的にいわれる管理職の主な種類は、次の7つです。
【管理職の種類】
| 役職名 | 責任を負う範囲 | 概要 |
|---|---|---|
|
本部長 事業部長 |
事業部門 |
|
|
部長 ゼネラルマネジャー |
部署 |
|
| 次長 | 部署 |
|
|
課長 マネジャー |
課 |
|
| 係長 | 係 |
|
| 主任 | 自分が関わる現場・職務 |
|
| 店長 | 店舗 |
|
なお、例えば「係長」という役職名が同じでも、A社では管理職として扱われ、B社では管理職ではなくリーダー職として扱われるケースがあります。詳しくは自社の規定をご確認ください。
管理職と役職者・役員・一般社員の違い
管理職と比較されるものに「役職者」や「役員」があります。また、「一般社員とどう違うのか?」という疑問を持つ人もいるかもしれません。
管理職のイメージをより明確にするため、これら3つと管理職の違いを確認しておきましょう。
管理職と役職者の違い
役職者とは、役割やポジション、業務内容などを明確に示すための役職がついた社員のことです。主任・係長・店長・マネージャー・チームリーダーなどに加えて、代表取締役も含まれます。また、部長や課長などの管理職も役職者です。
管理職と役職者の違いは、主に権限の範囲にあります。管理職は、チームや部門全体の意思決定に関わる権限を持ちます。一方で、役職者は必ずしもそうではありません。
例えば、代表取締役の役割は、会社の最高責任者として社内の人事や決済の決定に責任をもつことです。会社全体を代表する立場ですので、特定のチームや部門のみに責任をもつわけではありません。他方、CTO(最高技術責任者)のように、特定分野について部門横断的に責任をもつ役職者もいます。
管理職と役員の違い
管理職と役員の違いは、契約の種類と責任を負う範囲にあります。その範囲に応じて、役割や具体的な仕事内容も変わります。
まず、役員とは、いわゆる「経営層」のことです。会社法の第329条が定義する株式会社の役員は、「取締役」「会計参与」「監査役」であり、「三役」とも呼ばれます。この他、企業によっては「CxO」(CEO、CFO、CTOなど)のような「執行役」や「理事」「幹事」も含まれます。
役員の特徴は、第一に「会社との雇用関係がない」ことです。役員と会社の間の契約は委任契約であり、雇用契約ではありません。そのため、役員は雇用保険や労災保険の適用外となっています。
これに対し、管理職は会社との雇用関係がありますので、雇用保険も労災保険も適用されます。
第二に、部署横断的に会社全体の方針・運営に関わる点です。それぞれの役員には担当分野がありますが、それでも「営業部だけ」「管理部だけ」を見ていればいいというわけではありません。会社全体を俯瞰的に見ながら、全体方針の決定・運営を進めていきます。
一方、管理職は基本的に自身がマネジメントを行うべき組織が定められています。例えば営業部長であれば、権限と責任を持つのは営業部の範囲のみ。管理部についての権限や責任はありません。
管理職と一般社員の違い
管理職と一般社員の違いは、権限・責任の範囲と人事評価における評価基準です。
一般社員とは、管理職の指示を受けて業務を行う社員のこと。管理職から見ると、部下に当たります。契約形態は管理職と同じように雇用契約ですが、管理職ほどの権限はありません。人事評価では主に自分自身の業績によって評価されます。
他方、管理職は部下をマネジメントする立場です。メンバーそれぞれのパフォーマンスを引き出し、組織としての成果を最大化することで評価されます。
また、時間外労働についても一般社員と管理職では異なる扱いがなされることがあります。詳しくは、「管理職と労働基準法の関係」に関する項目で解説します。
管理職の平均給与・平均年収・男女比率
管理職の年収は、役職や企業規模によって異なるものの、上位の役職ほど高くなる傾向があります。厚生労働省による令和5年度の調査結果から、平均給与・平均年収・男女比率を見ていきましょう。
管理職の平均給与
管理職の平均給与については、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」で見ることができます。同調査によれば、管理職の各職位における男女計平均給与、男女別平均給与は次の通りです。
【管理職の平均給与】
| 職位 | 男女計平均 | 男性平均 | 女性平均 |
|---|---|---|---|
| 部長級 | 59万6,000円 | 60万4,100円 | 52万1,000円 |
| 課長級 | 49万800円 | 50万700円 | 43万800円 |
| 係長級 | 37万800円 | 38万2,300円 | 33万5,900円 |
全国平均では、係長と課長で約12万円、課長と部長で約10万円の差があることがわかります。
なお、役職に就いていない労働者(非役職者)の賃金は、
- 男女計平均:29万1,100円
- 男性平均:31万1,900円
- 女性平均:26万300円
となっています。男女計平均で比較すると、課長級は約1.7倍、部長級は約2倍と、大きな差が見られました。
*参考:厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況「役職別にみた賃金」
管理職の平均年収
管理職の給与を12カ月分に換算すると、部長級の年収は715万2,000円、課長級は588万9,600円となります。管理職に賞与がある会社の場合、さらに高い年収となるでしょう。
また、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、全国の平均年収は460万。課長級の年収はこれを上回り、部長級はさらに高い水準であることがわかります。
管理職における男女の割合
管理職における男性と女性の割合は、厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」の企業調査でわかります。同調査で管理職の職位別に見た女性管理職の割合は、下表のようになっています。
【管理職における女性の割合】
| 職位 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 部長相当職 | 8.0% | 7.9% |
| 課長相当職 | 11.6% | 12.0% |
| 係長相当職 | 18.7% | 19.5% |
令和5年度の正社員における男女比率は男性72.7%、女性27.3%でした。これに比べると、まだまだ女性管理職の割合は少ないようです。
管理職と労働基準法の関係は?残業手当・休日出勤手当・労働組合加入
ここで、管理職の労働条件としてよく話題になる時間外労働(残業)や休日労働の割増賃金の有無と、労働組合加入の可否を確認しましょう。理解のポイントは、「労働基準法」と「管理監督者」という2つのキーワードです。
労働基準法における管理監督者と“適用除外”
労働基準法は、昭和22年に制定された法律で、労働条件に関する最低基準を定めたものです。時代の変化にあわせて繰り返し法改正が行われ、近年では時間外労働の上限規制や割増賃金の規定、フレックスタイム制などの柔軟な労働時間制度などが話題となりました。
この労働基準法には、「管理監督者」を時間外労働や休日労働の割増賃金の対象から外すという「適用除外」が定められています(労基法第41条2号)。すなわち、残業をしても休日出勤をしても、手当がつかないということです。
管理監督者が割増賃金の適用除外となる理由は、経営者に準じる権限を持ち、経営者と一体的に企業の活動や方針決定に関わる立場だからです。こうした立場の社員は、たとえ雇用契約を結んでいても、労働基準法上の「労働者」の定義には含まれません。
ただし、全ての管理職が管理監督者となるわけではない点に注意が必要です。厚生労働省の説明では、部長や工場長など、労働条件の決定・労務管理について、「経営者と一体的な立場にある者」が管理監督者であるとされています。
そのため、たとえ「課長」という役職が与えられていても、その権限が狭く、会社の経営方針にあまり関わっていないのであれば管理監督者には該当しません。残業や休日労働の割増賃金が支払われるべきであるということです。
なお、同規定に深夜労働に関する適用除外規定はありませんので、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金は支払われます。
管理職の労働組合加入
管理職が労働組合に加入できるか否かも、経営層との関わり方の実態で判断されます。
労働組合に関しては、労働組合法による規定が判断の基準となります。具体的には「使用者の利益を代表する者」でないことが条件です。労働組合がそもそも労働者の代表として使用者(経営層)と対等な協議を行うことを目的に組織されるものであるという事情があるからです。具体的には、役員、人事権を持つ上級管理者、労務や人事を担当する部署の管理者などが該当します。
ただし、誰が組合員になれるかは労働組合によって多少異なります。役職名が一般に管理職と考えられる場合であっても、労働組合によって使用者の利益を代表する者とされなかったり、労働者側の立場で誠実に活動できる者であったりすれば、加入を認められるかもしれません。
管理職にとって現実的な選択肢となるのは、社内の「管理職組合」や所属企業を問わず参加できる合同労組への加入です。いずれも労働組合法で保護されるものではありませんが、団体として労働者の権利保障や賃上げを経営層に要求するなどの活動を行っています。
管理職に求められる6つの役割
管理職には責任と決裁権が伴い、経営視点での行動が求められます。管理職の役割・仕事内容は、大きく分けて次の6つです。
- (1)戦略策定と目標設定
- (2)戦略の浸透と人材育成
- (3)チームビルディング
- (4)予算管理と労務管理
- (5)進捗管理と業務改善
- (6)コンプライアンスの徹底
順番に解説します。
(1)戦略策定と目標設定
管理職の役割の1つ目は、経営戦略などの上位計画をもとに自組織の戦略を策定し、具体的な目標を設定することです。目標設定には、売上・利益率・市場シェアなどの指標がよく用いられますが、何を重視するかは企業や部署によって異なります。
目標設定のポイントは、
- 行動につなげやすい具体的な目標を設定する
- 必要なリソースを確認し、適切に配分する
- 目標達成につながる適切なモニタリング指標(KPI/KGI)を設定する
- プロセスや進捗の見える化を行う
などです。
目標が定まったら、達成に向けた業務フローを構築し、必要な人材やリソースを確保しなければなりません。同時に、他部署との連携も重要です。自部門の施策が、他部署に悪影響を与えないよう、全体を見渡す視点を常に意識しましょう。
(2)戦略の浸透と人材育成・評価
2つ目は、自組織におけるビジョン・戦略の浸透、人材育成です。
会社全体で大きな成果を出すには、共通の目的・理念が必要。どれほど優秀な人材が集まっても、全員が同じ方向を向かなければ、十分な成果は得られません。メンバーには、自身が責任を負う組織に期待されていることを具体的に伝えましょう。
このとき、内容だけでなく「なぜそのビジョン、ルールがあるのか」を説明し、部下の理解が深まるようにすると、より実務に結びつけやすくなります。
仕事の割り振りでは、遂行すべき業務内容だけでなく、以下の点も説明すると効果がさらに高まるでしょう。
- なぜその仕事を、そのメンバーにアサインしたのか
- 個人目標や組織目標と割り当てた業務がどのように関わっているのか
- 予想される困難、つまずきやすいポイントはどこか
定期的な評価を通じてメンバーの能力を把握し、成長をサポートすることが、成果を出すチームには欠かせません。
なお、人事評価や定期的な1on1でのフィードバックでは、以下の4点を意識すると観点を明確化できます。
【人事評価における主な観点】
| 評価の観点 | 概要 |
|---|---|
| 情意評価 |
働く姿勢や意欲、仕事に対するマインドの評価 勤怠状況や勤務態度も含まれる |
| 能力評価 |
業務遂行に必要な能力の評価 コミュニケーション能力、文書作成能力など |
| 行動評価 |
仕事の成果を出すための行動の評価 周囲との連携や目標達成に向けた行動など |
| 成績評価 |
パフォーマンス評価 目標の達成状況や与えられた役割への対応状況など |
評価においては、個人的な印象ではなく記録やデータをもとに判断することも大変重要です。
(3)チームビルディング
3つ目は、チームビルディングです。チームビルディングとは、共通の目標に向かってメンバーが協力し、それぞれの能力を活かす組織づくりを意味します。
チームビルディングを進める際は、以下の4つのステップを意識すると効果的です。
【チームビルディング 4つのステップ】
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 形成期 |
|
| 2. 混乱期 |
|
| 3. 統一期 |
|
| 4. 機能期 |
|
チームビルディングは多くの部下に関わる大変な仕事です。耳を貸してもらえず、管理職自身が孤独感を味わうこともあるかもしれません。組織が1つのチームとして機能していない場合は、何よりもまずお互いに話を聞き、相互理解を深めることが重要です。
(4)予算管理と労務管理
4つ目は、組織の目標達成において実務と直結する予算管理と労務管理です。5つ目の進捗管理・業務改善と同様に、管理職の日々の仕事として大きな割合を占めます。
予算管理では、資金計画の立案から予算の配分、執行などを行います。主な予算の種類は、次の4つです。
【予算の種類】
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 売上予算 | 売上目標を金額で表したもの |
| 原価予算 | 材料費などの原価の合計を表したもの |
| 経費予算 | 広告宣伝費などの経費の合計を表したもの |
| 利益予算 | 売上予算から原価予算や経費予算を差し引いたもの |
労務管理においては、労働時間の管理や業務分担の決定などを行い、メンバーが働きやすい職場環境を整備します。
部下のワークライフバランス、メンタルヘルスに留意するとともに、ハラスメント対策も行わなければなりません。いずれも法令による規制があり、企業に具体的な取り組みが求められています。
【労務管理で近年重視されている取り組み】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 働き方改革 |
|
| メンタルヘルス対策 |
|
| ハラスメント対策 |
|
これらの課題に取り組む社内チームが既に存在している場合は、管理職も当該チームと連携して施策実行に取り組みましょう。
(5)進捗管理と業務改善
そして、業務の進捗管理では、業務が計画通り進んでいるかを定期的に確認し、遅れやズレなどがあれば計画の修正や割り当ての調整などを行います。極端な遅れが出ている場合は、業務フロー自体に問題があるかもしれません。どのような進め方が品質を落とさず効率の向上につながるかを検討し、改善を進めていきましょう。
業務改善を効果的に進めるためには、PDCAサイクル(Plan計画・Do実行・Check評価・Act改善)を回すことが大切です。問題の早期発見と改善がスムーズに行えるよう、PDCAサイクルが自律的に回る仕組みをつくりましょう。
また、近年は外部環境の変化が激しくなり、より迅速な意思決定が必要な場面も増えています。そのため、現場で業務改善を進めやすいOODAループ(Observe観察・Orient状況判断・Decide意思決定・Act行動)が注目されています。計画通りに遂行することだけに固執せず、柔軟に対応する際に有効です。
(6)コンプライアンスの徹底
6つ目の仕事の内容・役割として、コンプライアンスの徹底も、常に頭に入れておかなければなりません。
コンプライアンスには様々な法令が関わってきます。まずは、企業倫理を自部門のメンバーに浸透させ、社会の一員として適切な行動を促しましょう。自らも模範となる行動を心がける必要があります。
また、現代は情報セキュリティの視点も欠かせません。機密情報や個人情報を適切に取り扱い、決して漏洩が起こらないように防止策を仕組みとして導入することが求められます。個人情報の社外持ち出しを禁止したり、機密情報へのアクセス権を制限したりすることが一般によく実施されている施策です。
ALL DIFFERENTでは、現代のビジネス環境において避けて通れないコンプライアンスの問題について、ケーススタディを用いたわかりやすい研修をご提供しています。身近なコンプライアンス例として、横領や守秘義務・不正競争防止法・ハラスメントなどを解説。効果的なマネジメントに、ぜひお役立てください。
管理職に求められる資質・スキル(カッツモデル)
管理職としての仕事をこなすには、一般社員(プレイヤー)とは異なる資質・スキルが要求されます。管理職に必要な能力を3つに分類して提唱したのが、経営学者のロバート・カッツです。
カッツ・モデルにしたがって、管理職に求められる資質・スキルを見ていきましょう。
テクニカルスキル(業務遂行能力)
1つ目の能力は、「テクニカルスキル(業務遂行能力)」です。現場で業務を進める際に求められる能力であり、例えば文書作成能力、電話や来客への対応力などを指します。
カッツは、管理職に
- トップマネジメント層:本部長など
- ミドルマネジメント層:部長・課長など
- ロワーマネジメント層:係長など
の3階層を定義しており、この階層が低いほど、テクニカルスキルが重要であるとしています。
【テクニカルスキルとは 】
| 特に求められる管理職 | スキルの具体例 |
|---|---|
| ロワーマネジメント層 |
|
職位が低い管理職は部下に直接業務を教える立場にあり、実際にその業務を自身が高いレベルで遂行できる必要があるということです。
ヒューマンスキル(良好な人間関係の構築能力)
2つ目の能力は、「ヒューマンスキル(良好な人間関係の構築能力)」です。主にコミュニケーションスキルを意味しますが、管理職としてのリーダーシップやビジネスマナーも含まれます。
【ヒューマンスキルとは】
| 特に求められる管理職 | スキルの具体例 |
|---|---|
| 全ての層の管理職 |
|
ヒューマンスキルは、組織を最大限に機能させる核となる能力です。そのため、管理職のいずれの階層でも重視されています。
コンセプチュアルスキル(概念化能力)
3つ目は、「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」です。具体的な事象から抽象的な特徴や傾向を分析し、論理的思考や批判的思考、ときにアナロジー思考などを駆使しながら戦略を練るために必要とされます。
【コンセプチュアルスキルとは】
| 特に求められる管理職 | スキルの具体例 |
|---|---|
| トップマネジメント層 |
|
戦略立案や改善で鍵になる能力であるため、そうした業務を担当する機会が多いトップマネジメント層にとって特に重要です。
管理職に向いている人・向いていない人の特徴
管理職の役割や仕事内容、求められるスキルを見ていると、「自分に管理職は向いていないのでは……」と不安になるかもしれません。そこで、あくまで参考程度ではありますが、管理職に向いている人と向いていない人の特徴をご紹介します。
管理職に向いている人の特徴
管理職に向いている人の特徴を一言で言えば、メンバーが一体となって目標達成に取り組むための組織づくりができることです。
より具体的には、以下の6つがあげられるでしょう。
【管理職に向いている人の特徴】
- ①経営者視点で考えられる
- ②メンバーとのコミュニケーションに苦痛を感じない
- ③セルフケアとともに、ラインケアができる
- ④フィジカル面でも自信がある
- ⑤情報の収集と分析が得意である
- ⑥国籍・性別・障害の有無などに偏見がない
管理職には、経営者視点で物事を見る視点が欠かせません。上層部と現場の間をつなぐ調整力、様々な部下の得意・不得意を把握して目標達成に導く力があるなら、管理職としてすぐに活躍できるでしょう。
ただ、こうした複雑な業務を的確に遂行するには、日頃から多方面の情報を収集し、分析して戦略を練る力が欠かせません。組織内については、どの作業がどのように行われ、何がボトルネックになっているかといった情報を集めて分析。市場についても、自社の製品やサービスに関するマーケット情報を集め、より効果的に販売するための施策を考える必要があります。
さらに、人材不足が叫ばれる昨今、働き方の多様化の促進とともに、人材の多様化も進んできました。従来の価値観では差別やハラスメントといったトラブルを招くこともあります。こうした価値観のアップデートに対応し、差別や偏見を避けたマネジメントを行わなければなりません。
管理職は、重い責任の中で難しい決断を迫られるもの。そのプレッシャーは大きく、一般社員と比べて、背負うリスクも大きいでしょう。メンタル・フィジカルともに強さを求められるということです。そのため、セルフケアと日々の体力づくりが習慣となっている人にも、管理職が担う責務の重圧に耐えられる素地があるといえます。
管理職に向いていない人の特徴
反対に、管理職に向いていない人の特徴は、自分のことにしか興味がなかったり、他人と関わることが苦手だったりすることです。
【管理職に向いていない人の特徴】
- ①そもそも仕事に対するやる気がない
- ②数字や調整業務にやりがいを感じない
- ③他人とのコミュニケーションが苦手である
- ④情報の収集・分析がうまくできず、印象や思い込みで判断する
- ⑤ハラスメント行為が多い
仕事にやりがいを感じていなかったり、自分以外のことに関心がなかったりする傾向は、メンバーを上手にまとめることを妨げてしまいます。他人とのコミュニケーションに苦痛を感じてメンタルヘルスに不調をきたすような状況では、管理職としての業務遂行は困難でしょう。
また、管理職が行う組織運営と数字は切っても切り離せません。売上管理・経費・生産効率・進捗管理などあらゆることが数値で判断されますし、コストやリソースの最適化といった複雑な調整も求められます。これらの業務にやりがいを感じない場合は、マネジメント業務自体が苦痛になってしまうでしょう。
個人的な印象や思い込みといった主観のみでメンバーを評価するケースについては、各メンバーの能力や困りごとを見誤る可能性を高めてしまいます。それが出身地や性別、障害の有無、あるいは育児・介護などに関わるものであれば、差別やハラスメント行為として問題になり、メンバーが働きにくい環境につながります。
とはいえ、はじめから完璧に管理職の資質・スキルを備えている人はほとんどいません。「向いていない」と思われる場合でも、管理職に向いている人の特徴を獲得できるように知識・スキルや行動習慣を身につけることが大切です。
ALL DIFFERENTでは、成果をあげる管理職を育成する「管理職研修」をご提供しています。管理職としての役割を自覚し、組織の成果を持続的に出し続ける力を養う研修プログラムです。個別的な課題への対応も可能ですので、管理職としての成長や管理職育成をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。