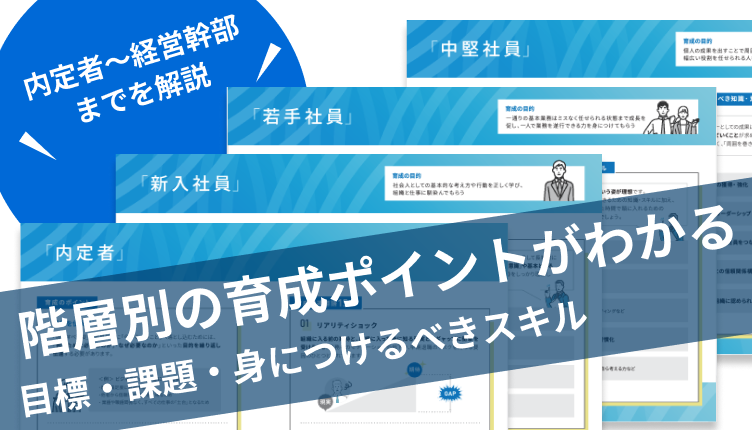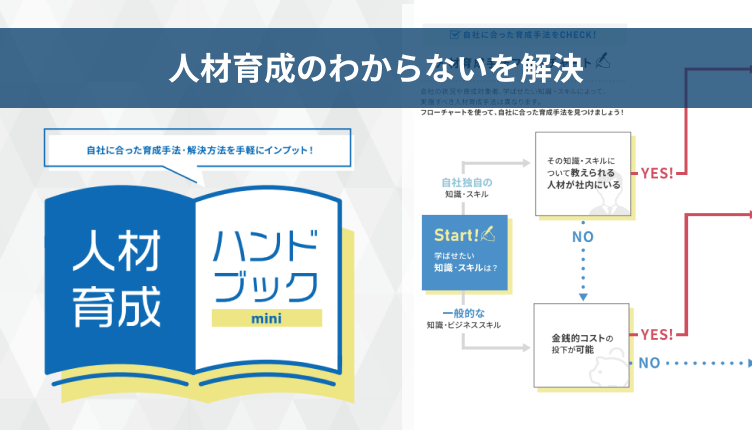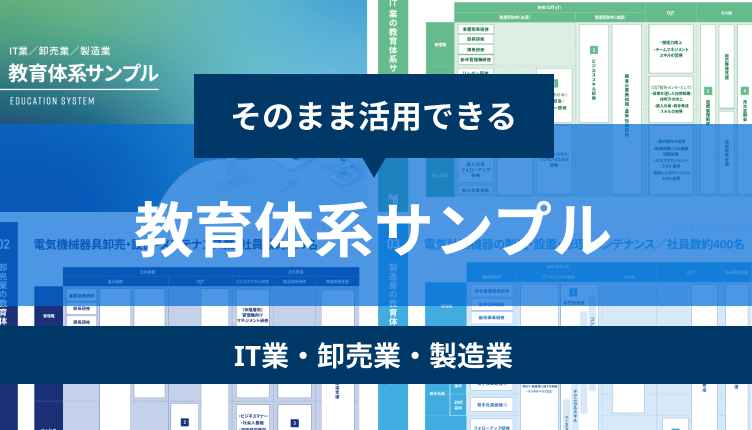転勤とは?人事異動との違いや目的、メリット・デメリットを解説
 公開日:2024.06.14
公開日:2024.06.14

転勤とは、勤務地が変わる異動を指します。企業にとって転勤は重要な人事戦略ですが、社員にとっては働き方や生活に大きな影響を与えるものです。本コラムでは、転勤の目的や対象となる人材、メリット・デメリット、社員への配慮など、転勤に関する基礎知識を解説します。
転勤とは
転勤とは、勤務地が変更になる人事異動のことです。必ずしも転居を伴うわけではありませんが、距離によっては引っ越しが必要になることもあります。
例えば、「本社から支店への転勤」や「ある支店から別の支店への転勤」というケースが考えられます。
転勤と異動の違い
異動は、勤務地や業務内容、役職が変わることで、「人事異動」とも呼ばれます。「課長から部長への昇進」といった職位の変更や、「営業部から総務部へ異動」のような部署の変更、「事務職から技術職へ異動」のような職種の変更など、人事に関わる配置転換全般を指します。転勤も異動の1つです。
転勤と赴任の違い
赴任は、勤務地に赴(おもむ)くことを表します。「海外赴任」「次の赴任地は大阪です」「〇月〇日付で赴任します」などのように使います。
自宅から通えない場所に転勤する場合に、家族と離れ、単身で暮らすことを「単身赴任」といいます。転勤の際の赴任形態の1つが単身赴任です。
転勤と出向の違い
出向は、別の会社で一定期間勤務することで、在籍出向と転籍(移籍)出向の2種類があります。
在籍出向は、元の会社に籍を残したまま他の会社で勤務することです。一方、転籍(移籍)出向は、元の会社との雇用契約を解消し、出向先の会社と新たに雇用契約を結ぶことを指します。
出向は転勤と同様に、転居を伴う場合があります。
企業が転勤を行う5つの主な目的
企業は様々な目的のために、転勤を命じます。ここでは代表的な転勤の目的を5つご紹介します。
(1)生産性向上のため
企業が転勤を実施する主な目的の1つは、生産性の向上です。生産性を高めるためには、適材適所の人材配置により、社員の能力を最大限に活用する必要があります。
特に、新規事業や海外進出など、重要なプロジェクトをスタートする際には、戦略的な転勤が求められます。確実な成果を得るために、その分野に精通した人材を配置しましょう。転勤は単なる人員配置の変更ではなく、重要な施策の一環と位置づけられます。
(2)人材育成・ジョブローテーションのため
ジョブローテーションとは、人材育成を目的とした戦略的な人事異動の一種です。日本ならではの終身雇用を前提とした長期的な人材育成の手法で、ゼネラリストの育成に役立てられることが多くあります。
2017年に実施された「企業における転勤の実態に関する調査」によると、約半数の企業がジョブローテーションを実施。社員1,000人以上の企業では、7割以上がジョブローテーションを取り入れています。
ジョブローテーションを通じ、様々な業務や部門を経験することで、適性や強みを見極められます。組織全体の仕組みや課題も多面的に把握できるため、管理職や幹部候補育成には欠かせない要素です。
*参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における転勤の実態に関する調査」
(3)マンネリ防止・組織の活性化のため
同じ業務に長い期間従事していると、マンネリ化してしまう恐れがあります。慣れた環境で同じメンバーと働き続けることで、徐々に向上心が低下し、新しいアイデアが生まれにくくなってしまうのです。
このような状況を防ぐために、転勤は有効な手段といえます。新しい職場では、これまでとは異なる経験や発想を持つ人材が出会うことで、活発なコミュニケーションが生まれます。新たな気づきを得られることが多く、モチベーションも高まり、組織全体の活性化につながるでしょう。
(4)欠員補充のため
企業にとって、人材は最も重要な資源の1つです。各部署や支店が効果的に機能するためには、適切な人員配置が必要です。しかし、退職や休職、業務量の増加などにより、人手不足が発生することがあります。
このような課題は転勤により解決可能です。欠員補充を行う際、新規採用という選択肢もありますが、転勤による人材は即戦力となります。一時的な人員不足の解消だけでなく、中長期的に見た効果的な人材配置にも役立つでしょう。
(5)不正防止のため
同じ社員が長期にわたり同じ業務を担当している場合、不正のリスクが高まります。取引先との癒着が生じることや、過度な関係性により適切なチェック機能が働かなくなる可能性があります。
このような不正リスクを防止するために、転勤は効果的です。転勤により担当者が変わることで、新しい目線でチェックができ、不正の早期発見や抑止につながります。
転勤の対象となる人材
では、企業が転勤を命じる際、どのような人材を選べばよいでしょう。転勤の対象となる社員について解説します。
異動を希望している人
転勤の対象として、まず注目したいのは、自ら異動を希望している人です。新しい環境でキャリアを積みたいと考える社員は、意欲的でモチベーションが高いと考えられます。転勤先での活躍も期待でき、会社にとっても有益です。
また、社員の希望に応えることで、会社に対する信頼や愛着も深まり、長く働くことにもつながるでしょう。
ただし、希望者全員を転勤させられるわけではありません。会社の方針や人員の配置バランスを考えて、適材適所の判断が必要です。会社は、社員が異動や転勤の希望を伝えやすいよう、面談や調査の機会を設けるとよいでしょう。
同じ部署に長期間勤務している人
同じ部署に長く在籍している社員も、転勤の対象となることがあります。長期間同じ環境で働くことで、業務へのマンネリ化や視野の狭まりが生じるリスクがあるためです。
新しい部署や職務に就くことで、社員のモチベーションを刺激し、スキルアップにつなげられます。また、組織の新陳代謝を促進し、部署の活性化を図ることもできるでしょう。
管理職・幹部候補となる人
将来の管理職や幹部候補として期待される人材も、転勤の対象となります。転勤先での経験により、幅広い業務知識や人脈が得られます。これらは、次世代のリーダーとなる管理職や幹部候補にとって非常に重要な要素です。様々な部署や職務を経験することで、リーダーシップや組織マネジメントに必要な能力を育成できるでしょう。
現在の職務で十分な成果を出せていない人
現在の職務で十分な成果を出せていない社員に対し、新しい環境で力を発揮してもらうために転勤させるケースもあります。その人の強みが生きる職務に再配置することで、適性や能力を見極められます。社員のモチベーション回復や新たな能力開発など、良い成果につながる可能性があります。
転勤のメリット・デメリット
転勤には様々な目的があり、会社と社員の双方にとってメリットがあります。しかし、一方でデメリットも存在します。ここでは、会社と社員それぞれの立場に立って、転勤のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
会社側のメリット
会社のメリットとしては、適材適所の人材配置が挙げられます。社員の能力や適性に合った部署に配置することで、個人の力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。
また、様々な部署や職務を経験することで、社員は多様なスキルや知識を身につけ、将来の管理職や専門職としての活躍が期待できます。新しい人材を迎えることで、部署内の雰囲気が変わり、新鮮な視点からのアイデアが生まれやすくなるでしょう。
社員側のメリット
転勤による社員のメリットとしては、新たなスキルや知識の習得が挙げられます。転勤を通じて、新しい職務を経験することは、キャリアパスを描くうえで非常に重要です。多様な経験を積むことで、将来の選択肢が広がるでしょう。
また、新しい環境で働くことで、新たな同僚や取引先との出会いがあり、社内外の人脈も広がります。将来のキャリアに役立つ、人脈形成が期待できます。
会社側のデメリット
会社のデメリットとしては、社員の退職リスクがあります。家庭の事情などで転居が難しい社員にとっては、転勤が退職の引き金となることがあります。優秀な人材の退職は会社にとって大きな損失です。
また、転居や社宅の費用、諸手当など、転勤コストが問題となる場合もあります。2017年の調査では、国内転勤の年間1人当たりの転勤コストは、数十万円から200万円程度かかると報告されています。最も多かった回答は「100~150万円未満」で、企業規模が大きくなるほど、転勤コストも大きい傾向がありました。
*参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における転勤の実態に関する調査」
社員側のデメリット
転勤による社員のデメリットとしては、生活や仕事の急激な変化があります。生活環境や仕事の内容が大きく変化するため、慣れるまでストレスとなることがあるでしょう。
また、家族への負担、将来設計のしにくさなども課題となります。配偶者の仕事や子供の学校など、家族にも大きな影響を与えます。共働き世帯では、配偶者の転職か単身赴任か、難しい選択をしなければならないケースもあるでしょう。
さらに、転勤の頻度が多い場合は、住宅購入や子供の教育計画など、長期的な将来設計が立てにくい点もデメリットといえます。
転勤の時期・期間・年齢層
転勤は企業の人事戦略において重要な役割を果たしていますが、その実施時期や期間、対象となる年齢層には一定の傾向があります。1つ1つ見ていきましょう。
転勤の時期
転勤を含む人事異動は、一般的に4月や10月に実施される傾向があります。これは、日本の企業では年度の始まりが4月であることや、多くの企業で上期・下期の区切りが9月と3月であることが関係しています。ただし、これ以外の時期で実施される場合もあります。
転勤の期間
転勤の期間は会社によって様々ですが、一般的には3~5年程度が多いようです。2017年の調査によると、転勤による赴任期間は、国内・海外ともに「3年程度」が最も多く、次いで「5年程度」でした。また、人事異動については、半数以上の企業が3~5年の頻度で行っています。
*参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における転勤の実態に関する調査」
転勤する人の年齢層
2017年に行われた調査によると、国内転勤の対象となる年齢層は20代から40代までと幅広く、7割以上の企業が「年齢による偏りはない」としています。
一方で、海外転勤は30代から40代の社員を中心に実施されることが多く、年齢によって偏りがあります。
また、50代は他の年代と比べて、国内転勤・海外転勤ともに少ない傾向がありました。
転勤の通知方法
転勤の通知は、一般的には、まず上司から口頭で知らされ、その後正式な書面で伝えられます。口頭による通知は「打診」や「内示」と呼ばれ、正式な辞令が出る前に内々に伝えるものです。
打診の時期は会社によって異なりますが、国内転勤では2週間~1カ月前が多く、海外転勤の場合は1~3カ月前、場合によっては3カ月以上前から行います。
正式な転勤の通知は、転勤通知書や異動通知書などの書面で行われます。これらの通知書には、転勤する日付や新しい部署、業務内容などが記載されます。
転勤の拒否と社員への配慮
就業規則に転勤に関する規定がある場合、転勤を命じられた社員は、正当な理由なく拒否することはできません。しかし、勤務地や職務が限定されている場合や、介護・育児などの家庭の事情がある場合は、転勤を拒否できる可能性があります。
2017年の調査において、転勤について配慮を求める要望が増加していることがわかりました。また、企業の8割以上は、社員の家族的事情を考慮した転勤配慮制度を設けています。転勤を理由とした転職を防ぐため、企業には柔軟な対応が求められます。社員のワークライフバランスを尊重しつつ、業務上の必要性とのバランスを取ることが重要です。