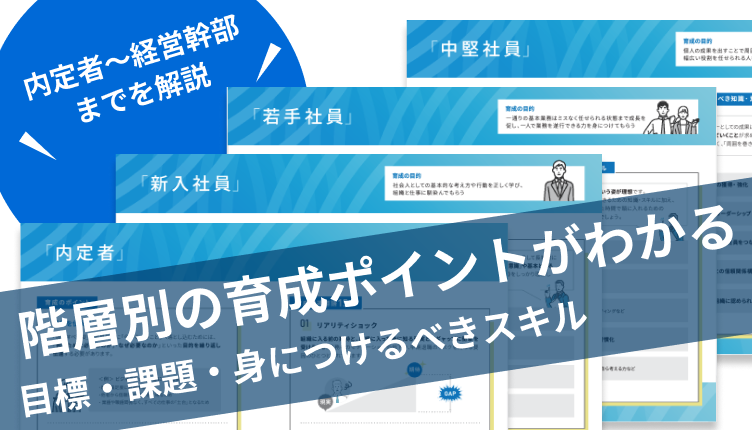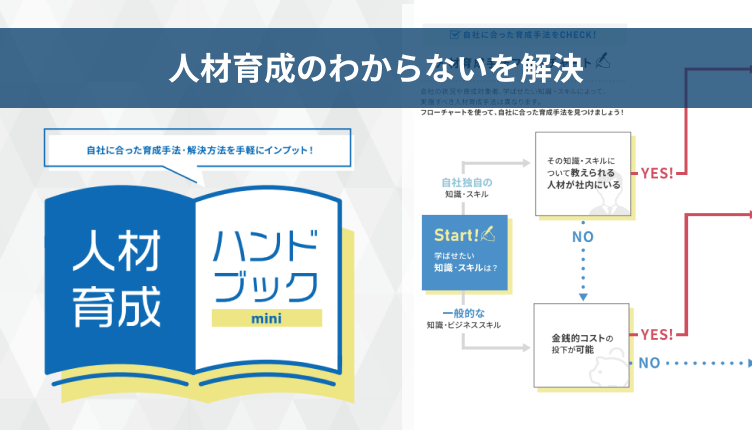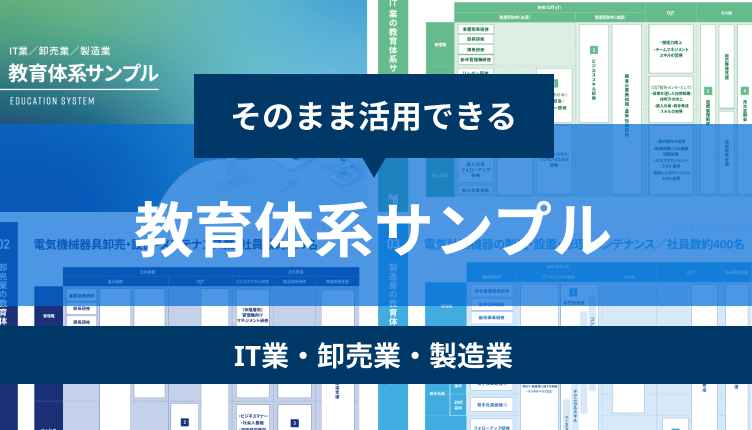主体性とは?自主性との違いや妨害要因、発揮につながるポイント
 更新日:2025.03.27
更新日:2025.03.27
 公開日:2021.03.24
公開日:2021.03.24

主体性とは、自らが言葉や行動を選択し、責任をもつ姿勢を意味します。「社員に主体性を身につけさせたい」「うちの社員は主体性がなくて困っている」といった声が、経営層や育成担当者からよく聞かれます。では、どうすれば社員の主体性を高めることができるのでしょうか。
本コラムでは、主体性と似た意味で使われる「自主性」とも比較しつつ、主体性を身につけるポイントを解説します。
主体性とは何か?意味と類義語、対義語
はじめに、主体性の辞書的な意味とビジネスにおける意味を確認するとともに、似た言葉である「自主性」「能動性」との違いを見ていきましょう。
主体性の意味と類義語・対義語
「主体性」の辞書的な意味は、ある活動や思考などにおいて「他のものによって導かれるのではなく、自己の純粋な立場において行う」態度や性格であるとされています。*
主体性の類義語には「自主性」や「能動性」などがありますが、厳密に全く同じ意味というわけではありません。対義語については、主体性のニュアンスから考えて「受動性」「指示待ち」「他人事」などがあるでしょう。
ビジネスの文脈では、主体性は「何をすべきか決められていないこと」について、自身の意思・判断によって自ら責任をもって行動する姿勢を意味します。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
主体性と自主性の違い
主体性の類義語として紹介した「自主性」ですが、そのニュアンスには違いがあります。
自主性とは、辞書的には「他者に依存せず、自分で行動できる性質」のこと。*
ビジネスでは、あらかじめ決められたことを自ら率先して行動する態度や性質のことを指します。
例えば、「常に整理整頓する」「出社時と退社時は必ず元気よく挨拶をする」などの組織内で決められたルールに従い、誰に言われずとも率先して行う若手社員について、「あの人は自主的に行動している」と周囲から評価をする場面があるのではないでしょうか。自主性がある人とは、いわば率先垂範する優等生のようなイメージともいえるでしょう。
一方で、主体性は、常にルールに縛られているわけではありません。目的に応じて必要とされる行動を率先してとる点に特徴があります。
したがって、主体性と自主性の違いは、行動の前に決め事があるか否かで区別できます。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
主体性と能動性の違い
もう1つの類義語である「能動性」と主体性の違いは、ビジネスの文脈においては「責任をもって行動する」というニュアンスの有無です。
能動性の辞書的な意味は、「自己の作用を他におよぼすこと」。*
ビジネスでは、誰かに言われてから行動するのではなく、自ら率先して動くことを指します。自主性や主体性と重なる部分も大きい言葉です。
しかし、能動性には「責任をもつ」というニュアンスがあるわけではありません。自身が働きかける立場として行動するのであれば、それは能動的な行動となります。この能動性に「責任をもつ」という意味合いが加わることで、ビジネスで求められる主体性になります。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
『7つの習慣』における主体性
主体性が大切であることを強調した考え方の1つが、スティーブン・R・コヴィー博士による『7つの習慣』です。
世界的名著である『7つの習慣』では、「主体性を発揮することとは、自分の人生を自ら選択し、自ら責任をとるということである」と定義されています。責任(responsibility)は反応(response)と能力(ability)が合わさったものであるため、責任とは「自分の反応を選択する能力のことである」という考え方です。
この考え方の特徴は、「刺激」と「反応」の間に自らの言葉・行動を選ぶスペースがあるとする点。「主体的な人」の対義語は「反応的な人」です。主体的な人が刺激と反応の間のスペースで言葉・行動を選択するのに対して、反応的な人にはそのスペースがなく、刺激に対してすぐに反応します。
参考:スティーブン・R・コヴィー(ジェームス・J・スキナー&川西茂 訳)『7つの習慣 解説DVD付き』キングベアー出版、2011年、pp.77-123
主体性はビジネスでなぜ必要なのか?
そもそも、主体性はなぜ多くの企業で求められているのでしょうか。ビジネスパーソンに主体性が求められる背景と、企業が求める主体性の内容を具体的に解説します。
ビジネスパーソンに主体性が必要な理由
ビジネスパーソンに主体性が求められる理由は、主に2つあります。1つはVUCAの時代に対応するため、もう1つはリスクマネジメントのためです。
VUCA時代への対応
まず、VUCAの時代への対応という観点では、現代が不確実性の高い状況にあることです。何が起こるか先の見通しが立たない中で企業が生き残るには、時代の流れに合わせて柔軟に考え方や行動を変えていかなくてはなりません。
大きな技術発展、社会情勢・価値観の変化から、過去の成功事例が役に立つとは限らない昨今、少数の幹部だけで意思決定をして組織を動かしていくことは非常に困難です。顧客や市場の変化に気づき現場レベルでの判断を軽視せず、幹部以外の人材も組織存続のために自ら目的・課題を設定し、責任をもって行動しなければなりません。
すなわち“主体性の高い人材”がいなければ、組織は立ち行かなくなってしまうのです。
コラム「VUCA(ブーカ)とは?OODAループが求められる理由」はこちら
リスクマネジメント
不確実性の高い時代にビジネスを継続するには、適切なリスクマネジメントも欠かせません。
情報技術の大きな発展により、個人の発信はSNSなどを通じて一気に世界へ伝達されるようになりました。これまでは「内輪ネタ」で済んだ事案も、ふとしたきっかけで社外に知られ、一気に燃え広がってしまう恐れがあります。
こうしたリスクを回避するには、社員一人ひとりがルールに従って仕事を進めると同時に、自らの行動が組織・社会にどのような影響を与え得るかを意識する姿勢が重要です。言葉・行動の選択と責任こそが、主体性の発揮です。
社員が主体性をもって仕事に取り組むことは、機密情報の取り扱い、顧客や社内メンバーとのコミュニケーション、商品・サービスの質と安全性の確保など、多様な面で役立つでしょう。ときには、役員や管理職が気づいていないリスクを指摘してくれることもあります。
決められたルール通りに行動する自主性だけでは、万が一の事態に対応するには不十分。自ら問題に気づき、改善策を提案し、さらに行動できる主体性を社員一人ひとりが身につけることが、より安定した企業活動につながります。
企業が求める主体性とは何か?
企業が社員に求める主体性の具体的な内容は、理念や事業分野によって異なります。ただ、以下の3点については、いずれの企業でも重視されるものです。
- 自身の仕事に対する責任感
- 業績向上や業務改善に向けた提案力・実行力
- 新規プロジェクトのアイデアなどの具体的な提案力
自身の仕事に対する責任感
自身の仕事に対する責任感には、割り当てられた仕事を求められる品質で完遂するとともに、手持ちの業務がなくなった際に自分から仕事を取りにいく積極性も含まれます。例えば、上長や周囲のメンバーに声をかけて新しい仕事の割り当てをもらったり、自身に与えられた権限の範囲で次になすべきことを整理し、実行したりすることです。
さらに、責任を持って業務を遂行するには、それまでの成功体験・失敗体験の振り返りと課題の発見を自ら行う力も重要。いわば“自分で成長する力”です。先輩社員や管理職にサポートを求め、知識・スキルを吸収する姿勢も欠かせません。
業績向上や業務改善に向けた提案力・実行力
組織の業績向上や業務改善に向けた提案力・実行力とは、例えば、業務フローについてボトルネックになっている部分を検討し、適宜改善していく力のことです。また、それまで「重要である」と考えられていた工程が「実は、なくても品質に影響はなかった」とわかった場合に、前例主義を捨ててより効率的なフローを提案するケースもあります。
基本的には組織の売上向上につながる要因を分析し、自身に与えられた権限の範囲で改善を図ることになるでしょう。ただ、改善すべき点が権限の外にある場合にも、上長や他部署の同期など、自分が働きかけられる範囲の社員に伝えることができます。
新規プロジェクトのアイデアなどの具体的な提案力
そして3つ目である新規プロジェクトのアイデアなどの具体的な提案力は、例えばプロジェクトやアイデアの社内公募に積極的に応募することなどがあげられます。
ここで重要なのは、ただ応募するのではなく、目的をもって応募すること。目的が明確化されていることでアイデアが採用されやすくなり、採用された際も自ら率先してプロジェクトを進めることができるでしょう。
主体性のある行動とは?主体性がない人・ある人の特徴
主体性についてさらに明確なイメージをつかむため、いわゆる「主体性のない人」と「主体性のある人」の特徴4つを比較していきましょう。
指示待ちか、積極的に動くか
主体性がない人の場合、上司や先輩から指示された業務は遂行しますが、それ以上のことをしない傾向にあります。また、業務中に「これは、やりにくい方法だな」「この数値は少しおかしいのでは?」と気づいても、その課題解決を図らず、従来のやり方で進めてしまいます。
主体性がない人の中には、「指示されていないことをやることは、自分にとって損である」と考えている人もいるでしょう。
一方で、主体性のある人は自ら目標を設定し、意欲的に取り組みます。そのため、手持ちの業務が終われば次の業務を探しにいくという行動に移ります。「このプロジェクトをやりたい人はいますか?」と問われた際、それが自身の目的や目標に合致するものであれば積極的に手を挙げ、他のメンバーが「仕事が増えて嫌だ」と考えている間に自身の行動を検討・決断しているのです。
言い換えれば、主体性がある人は「自分は、こうしたい」「こういう部分で貢献したい」という目的思考があるといえます。
他責か、自責か
責任に関する意識では、主体性のない人は他責傾向、主体性のある人は自責傾向にあります。
他責傾向とは、例えば「Aさんの指示でやりました」「先方が○○と言うので、仕方なく……」など、他の人の言動を自身の行動の原因とする姿勢です。特に主体性のない人は、自身がコントロールできないところに問題の原因を見いだそうとする傾向があります。周囲のメンバーには「言い訳が多い」と感じられる場面が多いでしょう。
これに対して、主体性のある人は自身の行動と結果に責任を負います。「このプロジェクトをやりたい人はいますか?」と聞かれて手を挙げたあと、「やっぱり無理なのでやめます」とは言いません。「やる」と手を挙げた以上は、試行錯誤しながらでも遂行し、必要に応じて上司や他のメンバーにサポートを求めます。
主体性のある人が意欲的に取り組み続ける理由は、その先に目的・目標の達成があるからです。他責をしていては、自己の成長は望めません。自らの課題を発見し改善する姿勢が根幹にあるということです。
「言われた」型か、「できるか」型か
同様のことが、問題への対応にも現れます。
主体性がない人の場合、思考や行動の起点が常に外部にあるため、他者からの指示や周囲の動きに合わせて行動します。言い換えれば、「自分で選ぶ」という姿勢が希薄なのです。
そのため、何かトラブルが発生した際に
「Aさんに、そう指示されたから(自分は悪くない)」
「これがこの場所に置いてあったから(自分がそれを使ったことに非はない)」
といった受け身の反応をしてしまいます。言ってしまえば「言われた」型の反応です。
これらの反応は有効なトラブルへの対処を遅れさせ、火に油を注ぐでしょう。最悪の場合、社員の意識や判断の根拠が「赤信号でも皆が渡っているから大丈夫」という状況になりかねません。
主体性がある人の場合は、トラブルに直面しても「Aさんのせい」とは考えません。トラブルに対して「自分は何をすべきか」「何ができるか」を考えます。
特に重要なポイントは、具体的な解決に向けて自分が働きかけられる範囲を知っており、実際に行動する算段をつけられることです。働きかけられる範囲とは、典型的には、管理職にとっての部下、先輩社員にとっての後輩社員、自身が権限をもつ範囲、他部署の同期メンバーなどでしょう。
営業職の場合、対話しやすい顧客であれば、その顧客は働きかけられる範囲に含まれるケースがあります。しかし、新規顧客や信頼関係が構築されていない顧客、決裁権を持つ人とのコネクションがない場合などは、働きかけられる範囲外です。
主体性のある人は、そうした自分が影響を与えられる範囲を見定め、その範囲で具体的なアクションを起こして問題解決を図ります。そのため、「自分にはなにができるか」という発想になるのです。
挑戦を避けるか、立ち向かうか
最後の特徴は、挑戦に対する態度です。
主体性がない人の場合、挑戦を避ける傾向にあります。なぜなら、挑戦とは自身で行動を選択し、失敗する可能性を引き受けたうえで実行することだからです。失敗への忌避感や他責の傾向が強いほど、挑戦的な業務やプロジェクトに手を挙げることは少ないでしょう。
仮に、そうした挑戦的な業務に無理に挑んでも、自分で判断すべき事態に遭遇した際に混乱状態に陥り、判断を誤ってしまう恐れがあります。これが失敗経験となり、ますます挑戦することが怖くなる悪循環に陥る恐れさえあります。
他方、主体性がある人は、困難な課題に挑むことができます。なぜなら、自身の行動の選択には目的があり、目の前の成功・失敗の先にある“目指すべきもの”を見据えて実行・改善していくからです。
主体性がある人にとってのゴールは目的・目標の達成であるため、そのプロセスにおける失敗は、成功の糧であり学びのステップアップ。これまで様々な意思決定をしてきた経験をもとに、失敗を成功につなげるマインドを持っています。
主体性が育たない職場環境の例
主体性があるか否かは、本人の性格の問題と感じられるかもしれません。しかし、実は職場環境が社員の主体性発揮を妨げている可能性もあります。
経営者や管理職の立場にある方は、メンバーに「主体性をもって行動しなさい」と言う前に、一度職場環境を見直してみましょう。チェックすべきポイントは、次の4点です。
【主体性の発揮を妨げる職場環境】
| 1 | 失敗を許容しない企業風土 |
|---|---|
| 2 | 競争にこだわり、協力関係がない雰囲気 |
| 3 | 上司からのフィードバックが常に叱責 |
| 4 | 過保護すぎる指導 |
順番に解説します。
(1)失敗を許容しない企業風土
1つ目のチェックポイントは、失敗を許容しない企業風土です。
例えば、現場に次のような特徴はありませんか。
- できないことばかりに注目する
- 「絶対失敗するな」「失敗は許されないぞ」と強く言う
- 一度失敗すると、周囲からの視線が冷たくなる
こうした傾向が見られる場合、その職場には失敗を許容しない文化が定着してしまっている恐れがあります。
失敗を許されない状況では、多くのメンバーが「確実なやり方」「他の人と同じやり方」にこだわり、自身が責任を負わなくても済む行動を選ぶでしょう。
自ら目標を立てる機会が与えられたとしても、保身を前提とする観点で目標設定され、意欲的な取り組みからは遠ざかってしまいます。
(2)競争にこだわり、協力関係がない雰囲気
2つ目は、個人プレーによる業績評価を重視するあまり、職場の雰囲気が競争的になり、メンバー同士の協力関係が生まれにくい環境です。
「失敗すれば負ける」「負けると周囲から軽んじられる」という空気が生まれやすい現場では、他者に勝つためにがむしゃらに働くことさえ「周囲から強いられている状況」への反応になってしまいます。
これでは、本人による責任ある選択とは到底いえません。いずれは、失敗を許容しない企業風土と同様に、自身が責任を負わなくても済むような行動を好むようになる恐れもあります。
他者との協力も選択できる職場こそ、主体性を発揮しやすい職場なのです。
(3)上司からのフィードバックが常に叱責
3つ目は、上司からのフィードバックが常に叱責の形をとることです。
自主性を育むには、社員が自ら考えて決断できる環境が必要になります。そして、自身で行動を選択し責任を負う姿勢は、自ら結果を振り返り改善する姿勢と表裏一体のものです。
仕事でミスをしたり適切でない業務の進め方をしたりした場合に、上司が一方的に叱責する形では、「なぜダメなのか」「なぜミスにつながったのか」を自分で分析する視点が育ちません。「怒られないように、教えられた通りのやり方で進めよう」という考えが先立ってしまうからです。
「どうすれば怒られずに済むか」という消極的発想では、ルールの範囲内でのみ行動する発想につながり、主体性の発揮にはたどり着けないでしょう。
(4)過保護すぎる指導
ここまでご紹介してきた職場環境は、社員に対して厳しすぎる目を向け、萎縮させるものでした。一方で、社員に対し必要以上に手取り足取り教えたり、失敗から守ったりする環境も、主体性を妨げる要因になり得ます。この過保護すぎる指導が、4つ目のチェックポイントです。
あらかじめ丁寧に指導して失敗から社員を守る職場環境は、一見のびのびと仕事ができる環境に感じられるかもしれません。しかし、失敗を事前に回避させようとする育成方針が行きすぎれば、育成対象者は失敗に対する向き合い方を学べないでしょう。実際に取り組む前に正解を教えられることで、試行錯誤するチャンスも逃してしまいます。
ひいては、「うまいやり方を教えてもらえなかったから失敗した」という好ましくない考え方を招く恐れもあります。
主体性のある部下を育てるには
では、社員の主体性を育てるには、どうすればいいのでしょうか。今回は、特に重要な3つの要素と、主体性の発揮に欠かせない信頼構築のためのポイントをご紹介します。
主体性の発揮に必要な3要素
主体性の発揮に欠かせない3つの要素は、有能感・自律性・関係性です。
有能感
有能感は、「自分には能力がある」「社会の役に立つ存在である」という感覚です。
有能感を高めるには、成功体験や他者からの賞賛が重要。特に管理職の方は、部下の良い面を褒めたり、成功に対してしっかりとポジティブフィードバックを行ったりすることが大切です。
賞賛がなく、できていないことばかりを指摘される文化では、有能感が醸成されにくいものです。部下や周囲の社員への接し方について、それぞれのメンバーが気をつける必要があります。
コラム「成果を上げている上司が「フィードバック」時にやっている5つのこと部下の成長を加速させる方法とは」はこちら
自律性
自律性とは、
「自分の言動を自分自身で決めている」
「他者からの強制や指示・命令で行っているのではなく、自分が自分の行動を律している」
と感じられることを意味します。主体性の発揮において、最も重要な要素といえるでしょう。
自律性は、自分で考えて決断し行動する経験の積み重ねによって育まれます。これには、役員や管理職が部下に一定の権限委譲をすることが有効です。はじめは不安かもしれませんが、周囲がサポートする環境を整備しつつ、思い切って権限を与えてみてください。
関係性
関係性とは、「他の人と精神的につながっている」という感覚や、「相互に信頼関係を維持している」という実感です。ビジネスにおいて重視されるのは、周囲と良好な関係を築き、共同して物事を行える状態。近年注目されている「心理的安全性」につながる要素です。
心理的安全性を確保した信頼関係の構築については、次項でさらに詳しく見ていきましょう。
信頼関係の構築に欠かせない3つのポイント
安心して主体的な選択ができる環境には、メンバー同士の信頼関係が不可欠です。信頼関係という土台を作り、提案や発言を否定せずに導くようにすれば、徐々に社員の主体性が育ってきます。根気強く続ければ、それが会社の風土として根付き、自然に主体性の高い人材が育つようになるでしょう。
まずは、信頼関係の構築に当たり3つのポイントに気をつけましょう。
相手の話を否定しない
何か意見すると否定される環境では、誰も何も言いたくなくなってしまいます。社員が主体的に自らの言葉・行動を選ぶには、提案や意見を出しても否定されない環境が重要です。
「否定しない」は、必ずしも全ての提案・意見を採用するということではありません。感覚や意見には多様性があることを認識し、まずは受け止めることです。そして、提案・意見の採否は必ず根拠をもって行い、「なんとなくダメそうだから」「嫌いな人だから」といった個人の感覚のみで却下しないようにしましょう。
採用しないと決定した場合も、決して相手を軽んじるような言葉を選んではいけません。
相手の本意をくみ取る
社員が管理職や経営者に提案するときは、緊張してどうしても言葉足らずだったり、知識不足から情報不足だったりすることがあります。提案や意見が、発言者の考えを適切に言語化されたものであるとは限らないということです。
そのため、社員から提案があった際は言葉尻で批判したりあら探しをしたりせず、「どうしてその提案をしようと思ったか」「何を課題として捉えたのか」といった本意をくみ取ることが重要です。
こうすることで、提案・意見を出した社員は自身の言葉足らずな部分を反省しつつ、「真剣に向き合ってもらえている」という感覚を得られます。この感覚は向上心につながり、より主体的な発信のモチベーションとなるでしょう。
普段からコミュニケーションをとる
業務上のコミュニケーションだけでは、主体性の発揮に必要な3要素を実践するには不十分です。より多くの機会を捉えて、コミュニケーションの練習を重ねましょう。
簡単にできる方法として、日々の雑談があります。天気の話であれば、誰のことも傷つけずに感覚の多様性を尊重した会話の練習が可能です。
例えば、気温については暑い・寒いといった感覚は人それぞれ。自分にとってはちょうどいい気温でも、相手は「寒い」と言うかもしれません。相手の感覚を否定せず、「過ごしやすいのはどのくらいの季節か」「オフィスの気温はどうか」など、話を広げてみてください。
コミュニケーションの頻度を高めることで、メンバー同士に話しやすい関係性が生まれます。そのような段階に入ったら、仕事に対する考え方やキャリアプランなど、より深い話題に進むとよいでしょう。
主体性を引き出すには新入社員・若手社員・管理職の階層別研修も
新入社員や若手社員は、「主体性を発揮しましょう」「主体的に行動しましょう」と言われても、ピンとこないかもしれません。
「主体性とは、どのように考え、行動することなのか」
「なぜ主体性が求められるのか」
といった、主体性が必要な理由や会社が求める人材像を明確に伝える場が必要です。
こうした“伝達”を中心とする学びには、研修の実施が効果的。多くの企業で人材育成に伴走してきたALL DIFFERENTでは、若手社員を対象に「セルフマインド醸成」「目的思考のすすめ」をテーマとする研修をご提供してきました。社員の主体性向上に向けた施策をご検討中でしたら、ぜひ以下の研修をお役立てください。
「若手社員研修~仕事に対するセルフマインド醸成~」の詳細はこちら
中堅社員や、管理職など部下をもつ立場の方に向けた研修では、次の2つの研修がおすすめです。
「周囲への影響を考えるセルフリーダーシップ」研修の詳細はこちら
「コーチング研修~部下を持つ管理職のためのコーチング~」の詳細はこちら
具体的なお困りごとや目的に応じた研修プログラムの作成も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。