ワールドカフェとは?やり方、事例、効果的な問いの作り方を解説
 更新日:2025.04.18
更新日:2025.04.18
 公開日:2024.07.19
公開日:2024.07.19
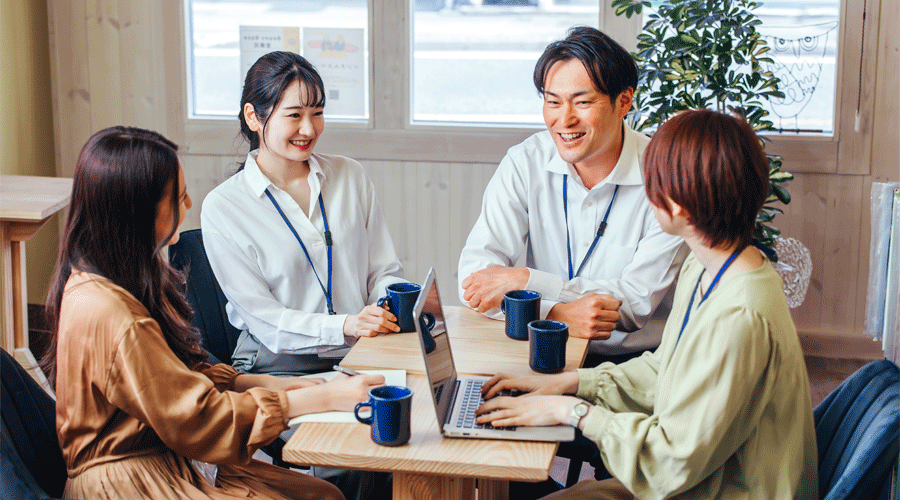
ワールドカフェとは、会議や議論を従来の堅苦しい形式で実施するのではなく、カフェのように自由でオープンな雰囲気の中でテーマや問いについて話し合い、組織内のコミュニケーション活性化を行う方式です。
ワールドカフェはビジネスの会議や研修にくわえ、自治体のプロジェクトが学校の授業など様々なシーンで活用されています。
本コラムでは、ワールドカフェの目的や実施方法、活用事例などについて詳しく解説します。
ワールドカフェとは
まずは、ワールドカフェとはどんな対話手法なのか、その定義や概要、由来、歴史について解説します。
ワールドカフェの定義と概要
ワールドカフェは、会議など話し合いを行う際に使える対話のやり方です。カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、メンバーを次々と入れ替えながら進めます。
参加者はそれぞれ4〜6人の小グループを作り、互いに自由に意見交換を行うのが特徴です。
話し合いの過程で参加者同士の相互理解が深まるため、新たな知見やアイデアが生まれやすいといわれています。
ワールドカフェの由来と歴史
ワールドカフェは、アメリカの組織開発論者であるアニータ・ブラウン(Juanita Brown)とデイビッド・アイザックス(David Isaacs)によって、1995年に提唱されました。
当時、彼らは知的資本経営にかかわる専門家たちを自宅に招き、活発な意見交換を促すために様々な工夫を凝らしていました。試行錯誤の中で、くつろいだ親密な雰囲気で対話を進めると、参加者たちの主体性や創造性を高める効果があることに気づいたのです。この経験から生まれた手法が、ワールドカフェの原型となりました。*
その後、ワールドカフェは世界中に広がり、現在では教育やビジネスなど、様々なシーンで活用されています。
ワールドカフェとワークショップの違い
ワールドカフェとワークショップは、どちらも「参加者が主体的に参加するグループ活動」という点では共通していますが、目的や進め方に違いがあります。
| 特徴 | ワールドカフェ | ワークショップ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 相互理解を促進する、自由な発想をする、アイデアを創出する | 知識やスキルを習得する、問題を解決する、成果物を作成する |
| 進め方 | 自由な対話形式で進める | 計画されたプログラムに沿って進行することが多い |
| ファシリテーター | 対話を促進する役割を担う | 参加者をリードし、活動を進める役割を担う |
| 成果物 | 明確な成果物は重視しない | 具体的な成果物を作成することが多い |
| 雰囲気 | リラックスした雰囲気で行う | 目的に応じて、真剣な雰囲気の場合もある |
どちらを選択すべきかは、目的によって異なります。例えば、「新しいアイデアや気づきを得たい」「参加者同士の相互理解を深めたい」という場合はワールドカフェが適しているでしょう。「具体的な成果物を得たい」「課題解決に向けて具体的な施策案を得たい」という場合は、ワークショップが向いています。
それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。
ワールドカフェの目的と効果
ビジネスにおいて、ワールドカフェはどのような目的で活用されているのでしょうか。
ここではワールドカフェの目的と効果について解説します。
ワールドカフェの目的
ワールドカフェの目的は、リラックスした雰囲気の中で参加者同士が自由に意見を交わし、お互いの価値観や考えを理解し合いながら対話を深めることです。
異なる意見に触れながら多様な考え方を共有することで、自分では気づかなかった視点やアイデアが生まれるきっかけになります。また、相手の意見に耳を傾け、その内容を理解しようと努力する過程自体も、ビジネスパーソンに不可欠なコミュニケーションスキルの向上につながるでしょう。
ビジネスシーンにおけるワールドカフェの効果
ワールドカフェの導入は、ビジネスに以下のような様々な効果をもたらします。
| 効果 | 説明 |
|---|---|
| 組織内のコミュニケーションが活性化する |
|
| 部署や役職を超えた交流が促進される |
|
| 1つのテーマに対する複数の見方を知り、知見を深めることができる |
|
これらの結果として、これまでより柔軟な思考ができるようになり、斬新なアイデアやユニークな解決策が生まれやすくなります。
ワールドカフェのやり方を徹底解説
ここからは、ワールドカフェを開催するために必要な事前準備と、実際の進め方について解説していきます。
ワールドカフェは、以下の進行をベースに、ラウンド数や時間、問いの設定などを調整して、自由にアレンジすることができます。
テーマ・問いの設定と事前準備
まずは、ワールドカフェで話し合う「テーマ」と「問い」を決めます。参加者の属性や人数、組織の目標などを考慮して、柔軟に設定しましょう。
次に、会場セッティングを行います。参加人数や会場にもよりますが、1つのテーブルを4〜6人で囲むように椅子を円形に配置すると、参加者全員が顔を見合わせながら対話しやすくなります。
テーブルの上にはあらかじめ模造紙やペン、ポストイットなどのアイテムを準備しましょう。筆記用具を使って話の内容を視覚化すると、相互理解が深まるからです。さらに飲み物やお菓子を用意して、本物のカフェのようなリラックス空間を演出するのもおすすめです。
具体的な会場設営方法やセッティングの工夫については、最後の章でも説明しますので参考にしてください。
イントロダクション
ワールドカフェは、ファシリテーターによる挨拶、ワールドカフェについての説明からスタートします。セッションを始める前には、メンバーが打ち解けるためのアイスブレイクとして、同じテーブルのメンバーに自己紹介する時間や雑談する時間を設けましょう。ワールドカフェは、いかに参加者の笑顔を引き出し、全員が話しやすい雰囲気を作れるかがポイントとなります。
会場の空気が和やかになったら、ファシリテーターが実際の対話の進め方やテーマ・問い、グランドルールを説明してください。参加者を萎縮させないように、「……は禁止」「……しないでください」といった否定的な表現は用いずに、「……するようにしましょう」とポジティブな言葉を使うように心がけます。
そして、各テーブルに1人ずつ「テーブルホスト」を選び、その役割について説明します。テーブルホストは、各ラウンドで新しく加わったメンバーに前のラウンドで話し合われた内容を伝え、議論を円滑に進める役割を担います。
全ての説明が終わったら、第1ラウンドの開始です。
第1ラウンド(20~30分)
第1ラウンドでは、ファシリテーターが発表したテーマ・問いに答える形で、テーブルごとに話し合いを始めます。テーブルの上に置かれた模造紙にペンでメモやイラストを書きながら、自由にアイデアを出し合いましょう。
このラウンドの目的は、参加者全員が自分の意見や考えを述べるとともに、他の人の意見も聞き、相互理解を深めることです。
第2ラウンド(20~30分)
第1ラウンド終了時刻になったら、各テーブルに1人ずつ「テーブルホスト」を残し、他のメンバーは「旅人」として別のテーブルに移動します。
第2ラウンド開始に際し、テーブルホストは新しくやってきた旅人に対して、第1ラウンドで話し合われた内容を共有しましょう。これを踏まえ、第2ラウンドの対話を進めます。旅人は、第1ラウンドで生まれたアイデアを他のテーブルに紹介する役割も担います。
このように、それぞれのテーブルでアイデアを交換することで多様性が増し、さらに革新的なアイデアが生まれやすくなるでしょう。
第3ラウンド(20~30分)
第2ラウンドで別のテーブルに移動していた旅人は、元のテーブルに戻ります。
第3ラウンドでは、まずそれぞれのメンバーが第2ラウンドで得たアイデアや気づきを共有しましょう。そして、テーブルのメンバー全員で様々な見解の関係性や共通点、傾向、意義などを検討します。
話し合いを進め、テーマ・問いに関する理解や考察を深化させましょう。
全体でのセッション
最後に、ファシリテーターが各グループの気づきや発見を回収し、参加者全員に共有してください。
全体でのセッションを行うことで、ワールドカフェの成果が、個人単位での気づき・発見だけでなく、組織全体としての発見につなげられます。
参考:厚生労働省「男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手引書(改訂版)」もとに作成
オンライン方式でのワールドカフェのやり方
ワールドカフェは活発な議論や意見交換がしやすいよう対面式で行われるのが基本です。しかし、近年ではビジネスのオンライン化が進んでいるため、オンラインのチャットツールやWeb会議ツールを活用してワールドカフェ方式のトークやイベントが行われる機会も増えています。例えば、ZOOMのアウトブレイクルーム機能を使えば、少人数グループに分けたセッションを行うことが可能です。
ビジネスチャットツールの中には、ホワイトボード機能や少人数グループ分け機能などが搭載されているものもあります。オンラインでの会議やイベントに、こうした機能を活用してワールドカフェ方式を取り入れることで、意見交換がオープンになり議論が活発化する効果が期待できます。
ワールドカフェのグランドルールと効果的なテーマ・問いを設定するコツ
ワールドカフェを成功させるためには、参加者が対話しやすい雰囲気を作り、議論を深める工夫が必要です。そのためには、基本的なルールを遵守し、テーマや問いを適切に設定することが重要となります。
ここでは、ワールドカフェの基本的なグランドルールや、対話を活性化させる「力強い問い」の特性、テーマ設定のポイントについて解説します。
これらの要素を意識することで、対話の質を高め、有意義な成果を得られるワールドカフェを運営できるでしょう。
基本的なグランドルール
ワールドカフェには、参加者がリラックスしつつも建設的な議論ができるようなルール設定が必要です。
例えば、以下のようなグランドルールを設定しておくと、活発で前向きな議論を行いやすくなります。ワールドカフェを実施する前に、ファシリテーターが参加者全員にグランドルールを伝えておきましょう。
他の人の意見に耳を傾ける
ワールドカフェは、全員が平等に自分の意見を述べることができる対話手法です。しかし、自分が発言するだけで他の参加者の話を聞かないのでは意味がありません。ワールドカフェの目的は「対話」であり、異なる視点や考え方を傾聴する経験自体を新しい気づきや視野の拡大につなげるものだからです。
セッション中は、相手の意見をすぐに否定したり批判したりするのではなく、いったんそのまま受け入れ、理解しようとする姿勢が大切です。
積極的に質問する
ワールドカフェのセッション中は、わからないことや疑問に思ったことがあれば、遠慮せず相手に質問して構いません。相手の意見やアイデアに対し、「なぜそう考えるのか」「もっと詳しく知りたい」と聞く行為そのものが、コミュニケーションの促進にもつながります。
一人の質問をきっかけに、グループ全員の理解が深まるという効果も期待できます。
対話中はテーマを意識する
対話を進めていく中で、意図せず話題がテーマから逸れてしまうことはよくあります。ワールドカフェのセッション時間は限られていますので、もしテーマから外れていると気づいたら、軌道修正を促すよう全員に伝えましょう。話し合いが盛り上がっている最中でも、できるだけテーマを頭に置いて対話するよう意識することが大切です。
結論よりも対話を重視する
ワールドカフェでは、リラックスした雰囲気で参加者が自由に意見交換し、相互理解を深めます。この過程こそ、ワールドカフェで最も重要な点です。話し合いの途中で、強引に意見をまとめようとしたり、急いで結論づけようとしたりする行為は推奨されません。
全員でアイデアを出し合い、じっくり意見を深め合う、対話そのものを楽しむスタンスで臨むのがマナーです。
「力強い問い」とは?
ワールドカフェで重要な役割を果たすのが「力強い問い」です。
ワールドカフェの創始者が主催する団体The World Café Community Foundationでは、ワールドカフェをデザインするための7原則(Design Principles)を定めていますが、このうちの1つに「重要な質問を設定する」ことがあります。この原則の中で、「Powerful questions=力強い問い」が、ワールドカフェのシステム全体に伝わり、参加者の考えを深めたり、創造的なアイデアを生み出したりするきっかけとなるとされています。*1
力強い問いの特徴として、アニータ・ブラウンとデイビッド・アイザックスは、次のような条件を挙げています。*2
- シンプルで明確
- 発想を促す
- エネルギーが湧いてくる
- これまでの仮説や思い込みを気づかせる
- 理想の状態や新しい可能性を開く
- より深い内省を促す
- 自分の事として考えられる
シンプルでわかりやすい言葉を用いながらも、深い考察や内省を促し、新しい発想や価値観の転換につながるような問いこそが「力強い問い」であるといえるでしょう。
*1 参考:The World Cafe | Design Principles
*2 引用元:四国地区大学教職員能力開発ネットワーク『ワールド・カフェの手引き』
テーマ、問いを設定する際のポイント
ワールドカフェでは、参加者自身が主体的に考えられるように、全体をうまく方向づけすることが大切です。その鍵となるのが、参加者の思考を刺激し、対話を活性化させる問いやテーマの設定です。
テーマや問いを設定する際は、次のようなポイントをおさえるとよいでしょう。
- オープンでポジティブな表現を使う
- チームの目的に沿ったテーマを選ぶ
- 具体的かつ広がりのある問いを作る
ワールドカフェにおけるテーマは、単なる現状分析や漠然とした問題提起ではなく、未来志向で具体的なイメージを持てるような、ポジティブなものにするとよいでしょう。否定的な言葉を避け、希望や可能性を感じられる表現を心がけます。不平不満につながるようなネガティブなテーマや問いは避けてください。
また、ワールドカフェの目的に合致するテーマを設定することで、参加者全員が共通の方向性を持って議論を進められます。あまりに抽象的な問いを設定してしまうと、参加者が当事者意識や具体的イメージをもちにくく、対話が活性化しませんので注意しましょう。
さらに、問いを設定する際には、「はい」か「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンではなく、参加者が自由に意見や考えを述べられるオープンクエスチョンにすることも重要です。
例として、「私たちの地域をより魅力的にするにはどうしたらよいか?」や「理想の働き方とは?」「良いチームとはどのようなチームか?」など、参加者の思考を広げるような問いが効果的です。
これらの工夫を取り入れることで、参加者が主体的に議論に参加し、成果のあるワールドカフェを実現できるでしょう。
ワールドカフェのメリットとデメリット
ワールドカフェは、適切なやり方をすれば多くのメリットにつながります。一方、やり方に慣れていないと「結論がでにくい」「時間がかかる」「進行が難しい」などのデメリットが大きくなってしまうかもしれません。どのような点に注意すればより大きなメリットを得られるのか、そのポイントを確認しておきましょう。
ワールドカフェのメリット
ワールドカフェには重要なメリットがあります。
逆に、このようなメリットが感じられない場合は、ワールドカフェの進行や運営に何か問題がある可能性があるので注意が必要です。
ここでは、ワールドカフェを行うメリットについて確認しておきましょう。
自由な発想と意見の交換が可能
ワールドカフェの最大の魅力は、参加者が自由に意見を交換し、発想を広げられる点です。リラックスした雰囲気の中で、少人数のテーブルに分かれて対話を行うため、発言のハードルが低くなります。
また、ラウンドごとにメンバーをシャッフルする仕組みが、多様な視点の共有を促進します。このような形式により、固定観念にとらわれず新たなアイデアが生まれる場として機能するのがワールドカフェの最大のメリットです。
相互理解が深まる
ワールドカフェでは、参加者が互いの意見に耳を傾けながら対話を進めます。このプロセスが、参加者同士の相互理解を深めるきっかけとなります。
テーブルごとに少人数で対話するため、お互いにリラックスした雰囲気でプライベートや個人的な意見など深いところまで交流できるのが特徴です。特に、部署間や職種間で行う場合には、職場の壁を取り払う効果も期待できます。
異なる立場や価値観を持つ人々が意見を共有し合うことで、自分の考えを見直し、新たな視点を得ることにもつながるでしょう。
チームワークが向上する
ワールドカフェを通じて築かれる信頼関係や協力体制は、チーム全体の結束力を強化します。少人数での対話形式により、一人ひとりが積極的に参加しやすい環境が整い、意見交換が自然と活発化します。
さらに、全体セッションで共有された意見がチーム全体のビジョンとして統合されることで、共通の目標意識を育むことができます。このように、ワールドカフェは単なる議論の場に留まらず、チームの一体感を高める機会としても有効です。
ワールドカフェのデメリット
ワールドカフェは、自由な意見交換や相互理解を促進する場として多くのメリットがある一方、特定の状況下ではデメリットも生じます。
デメリットを理解し、適切な運営方法を取ることで、ワールドカフェをより効果的に活用することができます。
ここではワールドカフェのデメリットとそれを避けるための方法について解説します。
意見が拡散しやすい
ワールドカフェの特徴である自由な対話環境では、時に意見が拡散しすぎてしまうというデメリットがあります。参加者が多様な視点を持つことで、新しいアイデアが生まれる一方、テーマから外れた議論や、具体性に欠ける話題が増える可能性が高まるからです。
この課題を防ぐためには、ファシリテーターが適度に議論を整理し、テーマに沿った方向へと導くことが重要です。
結論を求める場面では不向き
ワールドカフェは、自由な発想を広げる場として非常に有効ですが、具体的な結論や成果を求める会議には向いていません。これは、ワールドカフェが多様な意見を集めることに主眼を置いており、結論や合意形成を目的としていないためです。
そのため、結論を求める場面では、ワールドカフェだけで解決を目指すのではなく、ワールドカフェでアイデア出しをした後で関係者による会議を行うなど、補完する別の方法を組み合せるとよいでしょう。
ファシリテーターのスキルに依存する
ワールドカフェの成功は、ファシリテーターのスキルに大きく依存します。進行役が議論を適切に促進し、テーマから逸れた意見を整理できない場合、参加者が混乱したり、十分な成果が得られなかったりする可能性があります。
効果的な運営のためには、ファシリテーターが対話を活性化させつつ、必要に応じて軌道修正を行うスキルが必要です。ファシリテーターを担う人に対して、事前のトレーニングやシミュレーションなどを実施するようにしましょう。
ワールドカフェの事例
ワールドカフェは自治体、企業、教育機関など、様々な場面で活用されています。
ここでは、自治体の地域振興プロジェクトや企業の研修、学校の授業などでの具体的な活用事例を紹介します。
自治体での活用例
ワールドカフェは地域振興や政策策定の場で自治体によく活用されています。自治体が主催することで、地域の声を政策に反映しやすくなり、住民も主体的に参加する意識が高まります。
ここでは、滋賀県と青森県の自治体における活用例を紹介します。
滋賀県における男女共同推進のためのグループトーク
滋賀県では、男性も女性も暮らしやすい滋賀に向けた話し合いの場として「しが未来カフェ」を実施。立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授を講師にミニ講義の後、滋賀県在住の男女約100名によるワールドカフェ形式のイベントが行われました。身近な問題について、住民に当事者意識をもって考えてもらう機会として、ワールドカフェのような参加型イベントが活用されています。
参考:甲賀市商工会|しが未来カフェ ~滋賀のこれからを考えるワールド・カフェ~ 参加者募集!
青森県の若者育成事業
青森県では高校生などの若者に向けて、県内各地で活躍する地域活動家の手法を学んだり、活動に企画・参加することで、地域愛と県内への定着を図る取り組み「若者育成事業」を実施しています。若者育成事業の一環として、若者どうしや地域活動家との交流を深めるためのワールドカフェを開催。各地域の公民館やコミュニティセンターなどの施設を活用し、年間で10回以上のワールドカフェイベントを実施しています。
参考:青森県庁ホームページ|「地域の思いをつなぐ」若者育成事業
企業の研修などでの活用例
企業では、社員研修や部門間の連携強化を目的にワールドカフェが取り入れられています。
少人数での対話形式を採用することで、階層や職務にかかわらず、全員が意見を出しやすい雰囲気づくりができるからです。
ここでは、大手企業での研修やプロジェクトでのワールドカフェ活用事例について紹介します。
企業の社員研修での活用
大手商社三井物産およびそのグループ各社を対象とした人材開発・語学サービスを手がける三井物産人材開発会社は、組織活性化の研修メニューとして体験学習やワールドカフェを導入しています。
三井物産人材開発会社は東京大学と組織の包括性についての共同研究を実施しており、組織風土の改革やコミュニケーション活性化のための施策としても、ワールドカフェやグループディスカッションの手法が注目されています。
参考:三井物産人材開発株式会社MITSUI & CO. HRD INSTITUTE|カスタマイズ研修
NTTコミュニケーションズの企業変革プロジェクト
NTTコミュニケーションズは、2019年の創立20周年という節目を前に、2018年12月から企業変革プロジェクト“REBORN”を始動。経営企画部に所属する2人の有志から始まったプロジェクトは、ボトムアップの「オープン施策」を全社で展開しました。オープン施策の一環として、全社の異部門から約30名の参加者を募り、「3倍ワクワク働くには?」をテーマとしたワールドカフェを実施。4人1組でテーブルに座り、テーブルごとにホストを1人決め、模造紙やトーキングオブジェクトなどを活用しながら交代で議論を交わすというワールドカフェの手法を利用して、議論がよりオープンに活発になるよう工夫を重ねました。
プロジェクトは最終的に経営陣をも巻き込んで、96人の有志が参加する規模へと成長し、新たな企業理念と信条の策定という成果をもたらしています。
参考:組織づくりベース - 成長企業の人と組織をカガクするWebメディア Powered by HITO-Link組織づくりベース|【後編】NTTコミュニケーションズの企業変革プロジェクト
学校の授業など教育機関での活用
教育の現場でもワールドカフェは注目されています。
大学のゼミなどで課題解決型のワークショップとして活用されているほか、簡単に実施できるので小学校の授業でも導入されています。
日本大学ワールドカフェ
日本大学では、レポート作成やグループワーク・プレゼンテーション方法などの能動的な学習方法の習得を目的とした「自主創造の基礎」を全学共通教育科目に定めています。「自主創造の基礎」の授業において、16学部・短期大学部の1万6千を超える学生が混在してグループワークを行う「日本大学ワールド・カフェ」を実施。日本最大規模の大学であるスケールメリットを活かしながら、コミュニケーションとインクルージョンを学び、自分の学部の枠を超えて交流できる場を提供しています。
参考:日本大学|学生1.6万人の学部間大規模交流授業「日本大学ワールド・カフェ」
小学校の授業
兵庫県の三木市立広野小学校では、コロナ感染防止により子どもたち同士の接触やコミュニケーションの機会が減っていることを危惧して、5年生の授業内にワールドカフェを導入しました。
理科室という普段の教室よりも少し広く違った環境の中で少人数グループに分かれ、「友達の紹介」というテーマで交代にインタビューとスピーチ、最後には自分が知り得た友だちの情報やすばらしいことなどを報告する時間をもうけました。友だちとのつながりを主体的に発見し、クラスを活性化するための機会としてワールドカフェを活用しています。
ワールドカフェを効果的に運営するポイント
ワールドカフェを成功させるためには、計画や運営の工夫が欠かせません。目的を明確にし、全体の計画を練ること、ファシリテーターの役割をしっかり定めること、さらにセッティングやビジュアル化を工夫することで、参加者がリラックスしつつも活発な対話ができる環境を整えることが可能です。
最後に、ワールドカフェを効果的に運営するためのポイントを解説します。
目的と全体の計画を共有する
ワールドカフェを開催する目的と全体の計画を明確化し、参加者と共有しておくことが大切です。目的が曖昧だと、参加者の議論が散漫になり、期待した成果が得られない可能性があります。
第1ラウンドを始める前にその目的を全員に共有することで、参加者が話し合いの方向性や意図を理解し、自分の意見を出しやすくなります。各ラウンド中の対話をより積極的に進められるでしょう。
開催時間、各ラウンドの時間配分、休憩時間を含めたスケジュールを事前に決めて把握しておくことも重要です。ワールドカフェはオープンで議論が活発化しやすい分、収拾がつかなくなったり時間が長引いたりしがちですので、事前の準備段階での計画がスムーズな進行を支えます。
ファシリテーターが果たす役割
ファシリテーターは、ワールドカフェの成功を左右する重要な役割を担います。
ファシリテーターは、対話を活性化させながらスムーズに進行するために以下の点を意識するとよいでしょう。
対話を促進する
参加者全員が意見を出しやすい雰囲気を作ります。職場などで上下関係があるようなときは、部下や後輩でも臆せず意見が言えるようなリラックスしたオープンな場づくりが特に重要です。話が脱線した場合は、やんわりと軌道修正することも必要ですが、できるだけ参加者が気持ちよく主体的に発言できるような雰囲気をつくるようこころがけましょう。
中立的な立場を保つ
ファシリテーターは自身の意見を挟まず、議論の活性化に徹します。参加者全員が安心して意見を述べられるよう、中立的な立場で偏りのなく進行することが重要です。
ラウンド間のつなぎ役を担う
ラウンドごとに話し合いの成果を確認し、次のラウンドに引き継ぎます。これにより、対話の流れが途切れずに進行します。沈黙が続いたり、特定の参加者だけが発言したりしないように、会場全体を広く見渡しておく必要もあります。
セッティングや図解・ビジュアル化などの工夫
ワールドカフェの雰囲気作りには、会場のセッティングやビジュアル化の工夫が大きな影響を与えます。
最後に、会場のセッティングやビジュアル化のための道具などの具体的な例を紹介しますので参考にしてください。
会場のセッティング
テーブルは円形にし、参加者が顔を見合わせて対話できるよう配置します。
あるいは、企業や職場内でワールドカフェを実施する場合には、あえて机の向きを不揃いのレイアウトするのもよいでしょう。きっちりとした配置にすると、参加者は無意識に序列を意識してしまうからです。わざと机のレイアウトを不揃いにすることで、参加者間の序列意識が消え、全ての参加者が主体的に発言しやすい場をつくれます。
テーブルクロスや花、小物などを配置して、リラックスできるカフェのような雰囲気を演出するのもよいでしょう。軽食や飲み物も用意すると、参加者が和やかに交流しやすくなります。
模造紙を使った図解・ビジュアル化のメリット
ワールドカフェの対話では、模造紙などを使って対話中に出たアイデアやキーワードをビジュアル化するとよいでしょう。テーブルの上に模造紙を置き、カラーペンなどを使って、対話の中で出たアイデアや疑問などを、図形や絵などを使って自由に書きこんでいきます。図解することで対話の流れやプロセスがわかりやすくなり、情報が共有化しやすくなります。きれいに描くことを目的とするのではなく、対話を活性化するためのツールとして模造紙によるビジュアル化を行いましょう。
トーキングオブジェクトの活用
トーキングオブジェクトとは、会話の場で話す人が手に持つ道具のことです。オブジェクトの種類はペン、ボール、ぬいぐるみなどどんなものでもかまいません。
話したい人がトーキングオブジェクトを手に持って話すことで、発言中であることが明確になります。発言が終わったら、オブジェクトをテーブルの中央に戻すか、次の人に渡すかして対話を続けていきます。
トーキングオブジェクトを活用することで、特定の人が発言し続けることを避けたり、消極的な人にも発言を促したりしやすくなるメリットがあります。

