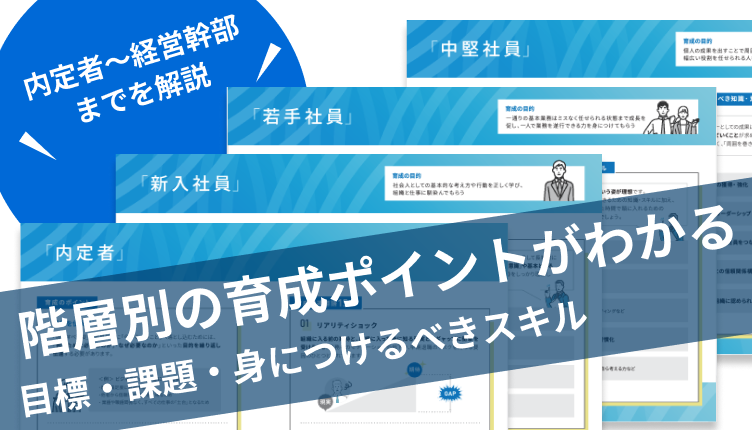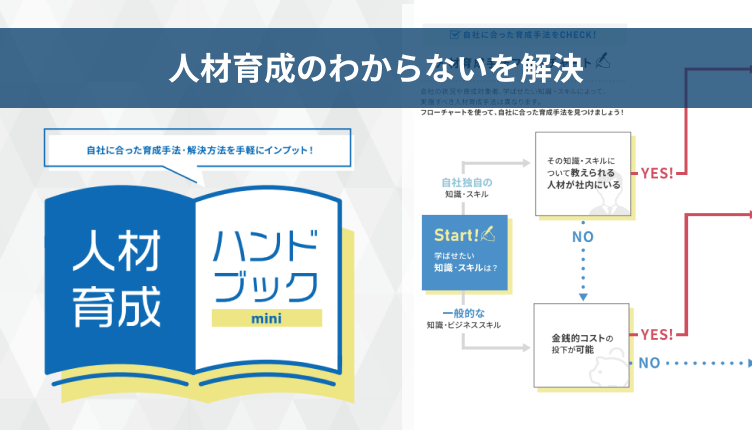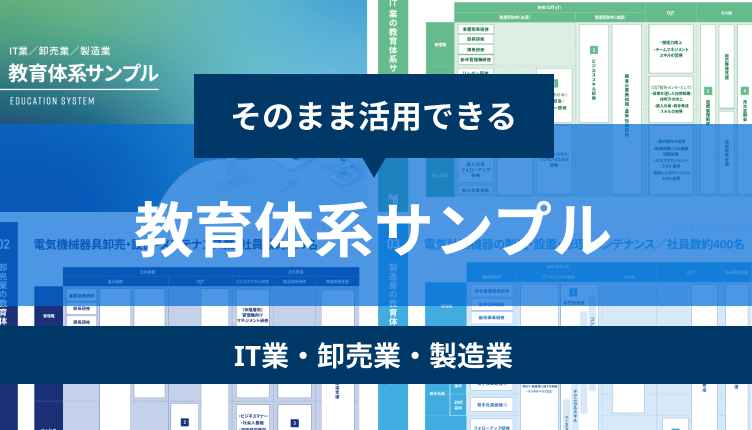論理的思考と合理的思考の違いとは?ビジネスでの重要性、鍛える方法
 更新日:2025.02.21
更新日:2025.02.21
 公開日:2022.03.08
公開日:2022.03.08
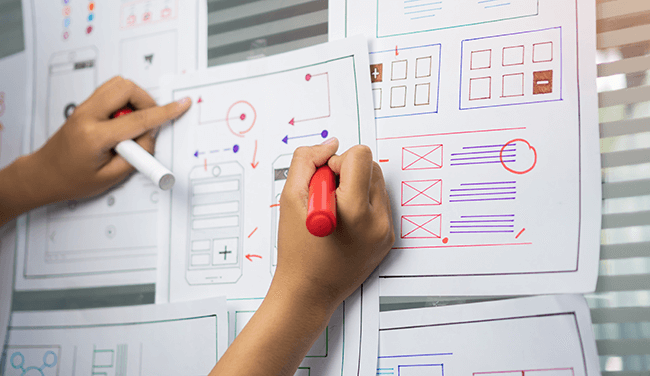
ビジネスパーソンにとって、「論理的思考」は問題解決に不可欠なスキルの1つです。さらに実務では、目的や制約条件を考慮しながら効率的な判断を導くための「合理的思考」も重要となります。
本コラムでは、これら2つの思考法の特徴と違いをわかりやすく解説。ビジネスで成果を上げるために欠かせない、合理的思考力を鍛える具体的な方法についてもご紹介します。
論理的思考とは
まずは、論理的思考の特徴から見ていきましょう。
論理的思考の定義と意味
論理的思考とは、伝えたい主張(結論)に向けて、根拠を筋道立てて考える思考法です。近年では「ロジカルシンキング」とも呼ばれ、問題解決能力の向上や合理的な意思決定の実現、コミュニケーションの円滑化に役立つビジネススキルとして注目されています。
【論理的思考の特徴】
- 情報を整理し、矛盾なく筋道を立てて考えることができる
- 複雑なテーマでも説得力のある形で結論を導き出せる
- 相手にわかりやすく考えを伝えることができる
論理的思考の基本手法
論理的思考の土台となる基本手法として、「演繹法」と「帰納法」の2つの思考法があります。
演繹(えんえき)法
演繹(えんえき)法は、大前提・小前提・結論の3段階で結論を導き出していく思考法です。具体例を挙げてみましょう。
- 大前提:成功するプロジェクトリーダーはコミュニケーション能力が高い
- 小前提:Aさんは成功するプロジェクトリーダーだ
結論:ゆえに、Aさんはコミュニケーション能力が高い
このように、演繹法では既知の事実から論理的に結論を導き出します。
帰納法
一方、帰納法は具体的な事例や経験から、一般的な法則や結論を導き出す思考法です。
- 観察1:A営業所がヒアリングシートを導入し、商談成約率が35%から50%に向上した
- 観察2:B営業所はヒアリングシート導入後に成約までの商談回数が平均5回から3回に短縮した
- 観察3:C営業所もヒアリングシート導入で顧客満足度調査のスコアが25%改善した
結論:ヒアリングシートの導入は営業プロセスの効率化と成果向上につながる
このように、帰納法は複数の具体例から共通点を見いだし、一般的な法則性を導き出す思考法です。ビジネスの現場では、過去の成功事例や失敗事例から法則性を見いだし、新しい施策を考える際によく使われます。
合理的思考とは
前章で見てきたように、論理的思考は物事を筋道立てて考える基本的なスキルです。しかし、実際のビジネスシーンでは論理的思考だけでは十分な成果を上げることが難しい場合があります。なぜなら、実務では目的や条件に応じて、より実践的な判断が必要となるからです。
そこで、ビジネスで特に重要となる合理的思考について詳しく見ていきましょう。
合理的思考の定義と意味
「合理的」という言葉には、「道理や論理にかなっているさま」「無駄がなく能率的であるさま」という2つの意味があります。ビジネスシーンでは、これらの意味が組み合わさり「目的に合わせて論理的で無駄がないさま」という意味で使われています。
したがって、ビジネスにおける「合理的思考」とは、「目的に合わせて論理的で無駄なく考える力」と定義できるでしょう。例えば、「この課題について合理的に考えてほしい」と言われた場合、「その課題を解決するために、論理的かつ効率的な方法を考えてほしい」という意味になります。
合理的思考ができる人の特徴
合理的思考ができる人には、次のような特徴があります。
目的・条件に合う基準で判断できる
ビジネスの現場では、利用可能なリソースには限りがあります。合理的思考ができる人は、これらの制約を考慮したうえで、実現可能な解決策を導き出します。机上の空論ではなく、実践的な選択肢を提示できるのが特徴です。
根拠と情報の信頼性を重視する
インターネットの発達により、世の中には様々な種類の情報が溢れています。中には個人の主観的な意見もあれば、科学的な根拠に基づく情報もあるでしょう。
合理的思考ができる人は、情報の信頼性を以下のように入念にチェックします。
- 複数の情報源を比較検証する
- 信頼性の高いデータを重視する
- 専門家の見解を参考にする
このような慎重な確認作業により、後から判断の前提が覆されるリスクを最小限に抑えることができます。
思考プロセスが明確で筋道が通っている
合理的思考ができる人は、使用する言葉の意味を明確にします。言葉の意味が曖昧だと、細かい条件分けができず、印象に頼った推論になってしまうからです。
例えば、部下への指示も「なるべく早く資料を提出してほしい」という曖昧な表現ではなく、「5ページ程度の基本仕様書を3日後の午前10時までに作成してほしい」というように、具体的かつ明確に伝えます。これにより、部下は迷うことなくスムーズに指示を理解できます。
正解のない問題に強い
ビジネスの現場では、誰もが正解を知らない問題に直面することが少なくありません。そんなときでも、合理的思考ができる人は「現時点でわかっていること」を手がかりに、状況を段階的に理解し、必要な情報を収集しながら最適解を導き出します。
判断に必要な情報が不足している場合は、その入手方法も考えます。このような経験を重ねることで、正解のない問題への対応力がさらに高まっていくのです。
論理的思考と合理的思考の違い
ビジネスにおける合理的思考と論理的思考の違いは、目的や条件にかなっているか否かです。論理的思考は、演繹法や帰納法といった手法を用いて、結論に至るまでの過程を論理的に明確にする思考法です。一方、合理的思考では、論理的であることに加えて、「目的・条件にかなっている」ことが重要になります。
ある企業の業務改善を例に、両者の違いを具体的に見てみましょう。
論理的思考のアプローチ例
論理的思考では、問題の原因を分析し、それに対する最適な解決策を導き出します。例えば、「残業時間が多い」という問題に対して、原因を次のように分析します。
- 作業プロセスの効率が悪いのではないか
- 特定の人にしかできない業務が多いのではないか
- 指示系統が明確になっていないのではないか
これらの問題に対する解決策は以下の通りです。
- 新しい業務管理システムを導入してはどうか
- 業務の手順をマニュアル化してはどうか
- 組織の体制を見直してはどうか
このように論理的思考では、実現可能性は別として、問題の原因と解決策を順序立てて考えることで、理論的に正しい結論を導き出します。
合理的思考のアプローチ例
対して、合理的思考では論理的な分析に加え、現実的な制約条件も考慮します。
- 予算に余裕がないため、高額なシステム導入は難しいのではないか
- 人員を増やすことができないため、今の体制でできることを考えるべきではないか
- 一度に全ての改善を実施するのは難しいため、段階的に進めてはどうか
これらの制約を考慮し、実行可能な改善案として
- まずは既存ツールを使った業務の可視化から着手してはどうか
- 次に重要業務のマニュアル作成を進めてはどうか
- その後、段階的な業務移管を実施してはどうか
このように考えます。
つまり、合理的思考では論理的な分析を土台としながら、実務上の様々な制約も考慮することで、より実現可能性の高い解決策を導き出すことができるのです。
合理的思考力を鍛える6つのポイント
ビジネスで成果を上げるために必要な合理的思考力を鍛えるには、日々のトレーニングと実践が欠かせません。以下の6つのポイントを意識して分析・検討することで、より効果的に思考力を向上させることができます。
【合理的思考力を鍛える6つのポイント】
- (1)目的・条件を明確にする
- (2)情報リテラシーを身につける
- (3)適切なデータや判断の根拠を探す
- (4)知識・経験を増やす
- (5)人は感情で動くことも考慮する
- (6)失敗を想定してプランBを考える
(1)目的・条件を明確にする
合理的思考の基本は、目的と条件を明確にすることです。例えば、「顧客の労務管理の工数を削減するサービスを提案する」という場合、項目ごとに検討すべき内容を具体的に掘り下げていきます。
【合理的思考による目的・条件の洗い出し例】
| 確認項目 | 具体的な検討内容 |
|---|---|
| 目的の具体化 |
|
| 条件の明確化 |
|
上記の条件を数値化することで、より具体的な判断基準を設定できます。例えば、
- 工数30%削減
- 3ヶ月以内に導入完了
- 投資回収1年以内
- 月額費用50万円以内
といった数値目標を設定すれば、より精度の高い解決策を導き出すことができるでしょう。
(2)情報リテラシーを身につける
合理的思考には、信頼性の高い情報が必要です。しかし、誰もが発信者になれる社会では、入手できる情報は玉石混交であるというのが現実です。
そこで重要になってくるスキルが、情報リテラシーです。パソコンなど情報を得るためのツールを使えるだけでなく、情報自体の扱い方も習得しなければなりません。
情報の信頼性を確認するには、発信者と内容の両方に注目する必要があります。
発信者については、省庁や地方自治体、大学、研究所、大きな業績のある専門家などは、信頼性の高い情報を発信している場合が多くあります。社内のエキスパートに意見を聞くのもよいでしょう。もちろん、ファクトチェックが行われた百科事典や辞書も使えます。
消費者の価値観を知るには、主観的な文章が掲載されているSNSやブログなども選択肢に入ります。「どのような人の意見なのか」を確認するため、必ず投稿者のプロフィール欄もチェックしましょう。
情報の内容面では、既知の情報との整合性、専門家の見解との突き合わせによって、信頼性を確認します。複数の知見と比較して、誤解や矛盾がないかを確かめましょう。
(3)適切なデータや判断の根拠を探す
合理的思考力を高めるには、「なぜそういえるのか」を示す根拠を探しましょう。ここで注意すべきことは、データや根拠の質と量です。
例として、「A社の業績が大きく伸びたのはなぜか」についての2つの説明を見てみましょう。
【A社の業績が大きく伸びた理由の比較】
| 説明1 |
A社の業績が大きく伸びたのは、2年前に就任した新社長のおかげだ。 SNSでも新社長の人柄が話題になっている。 |
|---|---|
| 説明2 |
A社では2年前に大きな変革を行い、新体制に移行した。 A社の年次報告書を確認したところ、新体制ではB氏が新社長となり、 ビジョンの決定には一般社員も関わり、その結果、従業員のエンゲージメントが大きく向上したと報告されている。 新ビジョンを体現する新しい事業が始まり、社外の評価も高い。 以上のことが、新体制下でもA社の業績向上に寄与していると考えられる。 |
説明1と説明2を比較すると、より納得感の高い説明は後者です。説明1は情報量が少なく、判断の根拠が「SNS」や印象のみであるのに対して、説明2では「年次報告書」に記載された新体制の概要や社内の事情、新事業に対する社会的評価を根拠としているからです。
このような違いは、実践的な判断にも影響を与えます。説明1では情報不足により「SNSで話題になるような人を新社長に迎えよう」という表面的な判断になりかねません。しかし、説明2では、「重要なのは社長の変更よりも社員が賛同し前向きに業務に取り組めるビジョンとその実現方法である」という本質的な判断が可能になります。
(4)知識・経験を増やす
情報リテラシーを高めて正確なデータや根拠情報を入手できても、その情報を正確に理解できなければ誤った判断をする恐れがあります。これを防ぐには、合理的思考を巡らせる分野について、最低限の基礎知識を習得することが重要です。
一般に、特定の分野の深い知識や豊かな経験がある人ほど、その分野の資料を正確に読み、適切な判断を行います。逆に、知識・経験が浅いと情報を誤解したり見落としたりして、考察が不十分になる傾向があります。
基礎知識を学ぶには、辞書・事典・入門書などを足がかりに、専門書や研修で学ぶとよいでしょう。さらに、その分野で活躍する人々の経験を書籍やセミナーなどで学びながら、得た知識を自分の視点で考察することも大切です。「自分ならどうするか」という問いを日々投げかけることで、知識を実践的な判断力へと昇華させることができます。
(5)人は感情で動くことも考慮する
合理的思考に慣れてくると、「感情を抜きにして考える」という姿勢から、自分や他人の感情を無視しがちになります。しかし、ここに合理的思考の落とし穴があります。それは、「人間が感情をもとに判断する」という基本的な傾向を軽視してしまうことです。
例えば、自社がA社に提供している業務管理システムの契約更新時期が迫っているとしましょう。A社に次期の契約を持ちかけたところ、管理システムの質やカスタマイズの内容自体に問題はないとしながらも、更新をしないと言っています。なぜでしょうか。
更新をしない理由を確認すると、自社の担当者Bが失礼な物言いをしていたことが明らかになりました。担当者Bが用いる表現は、システムの善し悪しに影響は与えません。しかし、A社の担当者は、やり取りのたびにBの言動に不快感を覚えていたのです。
このように、合理的思考を実践する際は、目的・条件、根拠、論理的正しさをベースとしながらも、結果に大きな影響を与える「人間の感情」という要素も十分に考慮するように心がけましょう。
(6)失敗を想定して「プランB」を考える
合理的思考では、導き出した結論が必ずしも望ましい結果につながるとは限りません。よりレベルの高い合理的思考をするには、「失敗の可能性」を想定することが重要です。
そもそも、人間の感情や行動は、完全には予測できないものです。また、社会情勢の急激な変化、関係者の感情の変化、他社による新技術やサービスの投入、市場の急激な変動など、予期せぬ変化が起こる可能性も常にあります。
そのため、1つの計画や施策だけでなく、複数のバックアッププランを用意する必要があります。具体的には、まずプランAで「望ましい展開」を想定し、次に「もし〜だったら」と前提条件を変更して、別パターンの推論と対策を行いましょう。
合理的思考を意識して日々実践することで、こうした「合理的思考のクセ」を身につけることができます。