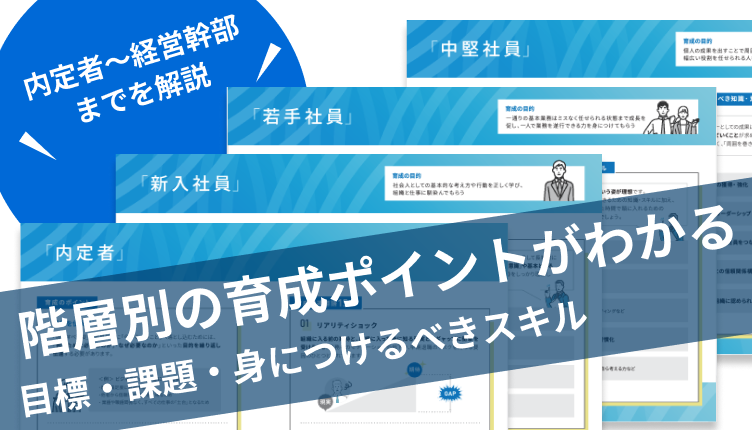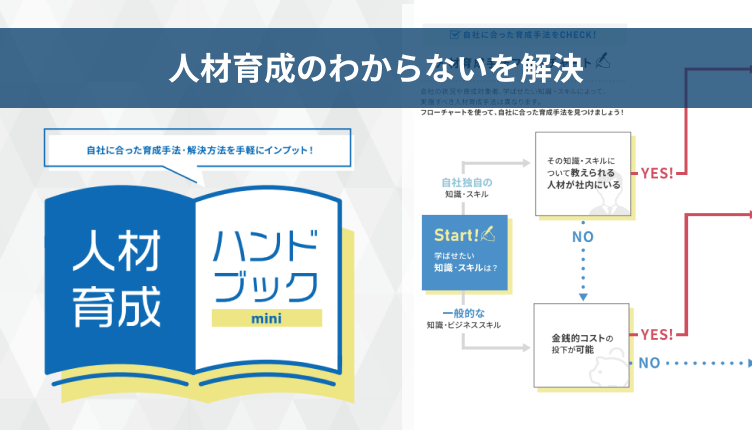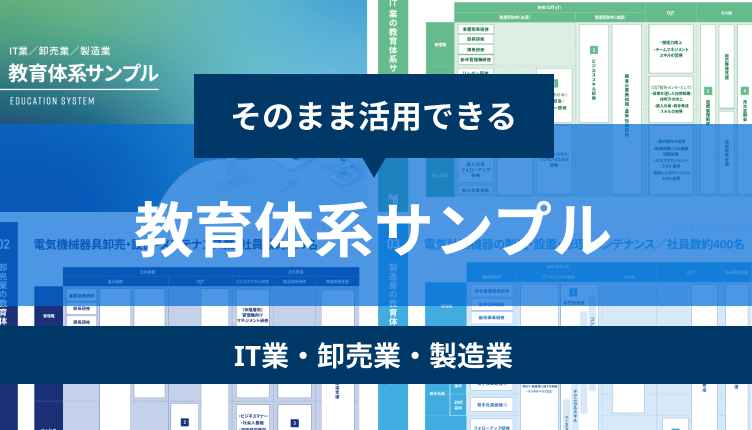コアコンピタンスとは?意味、企業事例と自社の強みの見つけ方
 更新日:2025.03.04
更新日:2025.03.04
 公開日:2023.12.13
公開日:2023.12.13

コアコンピタンスとは、他社に真似されにくい独自の技術や特徴など、「自社ならではの強み」を意味する概念です。市場環境が激しく変化する現代において、コアコンピタンスを軸とした戦略や経営が重要性を増しています。本コラムでは、コアコンピタンスの基本的な考え方から実際の企業事例、そして自社の強みの見つけ方まで、わかりやすく解説します。
コアコンピタンスとは
「コアコンピタンス(Core Competence)」とは、日本語に直訳すれば「核となる能力」となります。具体的にどのような能力なのか、まずはその意味や概念の特徴を見ていきましょう。
コアコンピタンスの意味と特徴
コアコンピタンスは、競合他社よりも優位性がある中核的な技術やノウハウ、事業プロセスなどを意味します。製造業においては、他社が真似できないような独自の技術や生産体制がコアコンピタンスとなります。
コアコンピタンスの概念は、G.ハメルとC.K.プラハラードの著書『コア・コンピタンス経営』(日本経済新聞出版社、1995年)によって広められました。その定義として、以下3つの特徴があげられています。
- 顧客に何らかの利益をもたらす自社能力であること
- 競合相手に真似されにくい自社能力であること
- 複数の商品・市場に推進できる自社能力であること
コアコンピタンスの言い換え、例文
コアコンピタンスとは、端的に言えば「自社の強み」のことです。ビジネスの現場では、以下のような使い方が一般的です。
- 「当社のコアコンピタンスは高い技術力です」
- 「コアコンピタンスを活かして新事業を展開します」
- 「品質管理こそが、私たちのコアコンピタンスです」
なお、関連する用語として「コンピタンス・マネジメント」「コンピタンス分析」などがあります。
コアコンピタンスの企業事例
コアコンピタンスをより具体的に理解するため、特徴的な強みを持つ3つの企業の事例を見ていきましょう。
サプライチェーン管理に強みを持つネスレ、技術の転換力で知られる富士フイルム、製造業の自動化をリードする三菱電機の事例から、それぞれのコアコンピタンスとその活用方法を解説します。
ネスレのサプライチェーンマネジメント
ネスレのコアコンピタンスは、マーケティング、営業、生産の各部門と密接に連携したサプライチェーンマネジメントです。同社のSCM部門は、需要・供給計画の立案から原材料の調達、製品の補充、顧客対応まで一貫して管理し、国内の緻密な物流対応とグローバルな視点での調達を両立させた供給体制を構築しています。
日本市場では、全国の販売網と連携した需要予測や在庫管理により、「キットカット」や「ネスカフェ」などの人気製品を安定的に供給することで競争優位性を確立しています。
富士フイルムの技術転換力
富士フイルムは、デジタル化による写真フィルム市場の激減という危機に直面しながらも、独自の技術を異分野に展開することで成長を続けています。同社のコアコンピタンスは、フィルム製造で培った化学技術と、それを新分野に応用する技術転換力です。
例えば、写真フィルムの技術は以下の分野に活かされています。
- 医療分野:画像診断技術を活かした内視鏡やAI診断支援システム
- 化粧品分野:フィルムの抗酸化技術を応用したスキンケア製品
- 電子材料分野:液晶ディスプレイ用のTACフィルムなど
参考:FUJIFILM「value from innovation」
三菱電機のファクトリーオートメーション
三菱電機のファクトリーオートメーション(工場自動化)事業は、工場の生産ラインを効率化するために幅広い製品を展開しています。製品の組み立てを行うロボットから、それらを制御するコンピュータまで、一括して提供できる総合力が同社の強みです。
さらに、製品の開発から製造、アフターサービスまで一貫した品質管理体制を構築しているのが大きな特徴です。国内の中核工場を中心に、世界各地の開発・生産拠点が連携し、グローバルな競争力を確保しています。
コアコンピタンスとケイパビリティ・コンピテンシーの違い
企業の「強み」を表す言葉として、コアコンピタンスとケイパビリティ、そして個人の能力を表すコンピテンシーという3つの関連概念があります。ここでは、それぞれの定義や意味の違いについて確認しておきましょう。
コアコンピタンスとケイパビリティ
コアコンピタンスは、特定の分野、プロセスにおける企業独自の優れた能力を指す言葉です。一方、ケイパビリティは、組織の仕組みや戦略など、企業全体としての他社に対する強み・能力を意味します。
例えば自動車メーカーの場合、以下のような違いがあります。
【コアコンピタンスとケイパビリティの違い】
| コアコンピタンス | 優れたエンジンを開発・製造する技術力 |
|---|---|
| ケイパビリティ | その技術を支える品質管理体制や効率的な生産システム |
コアコンピタンスと同様、ケイパビリティも企業によって様々な事例が見られます。
コアコンピタンスとコンピテンシー
コンピテンシーは、「高い成果を上げる人材に共通して見られる行動特性」を意味する言葉です。コアコンピタンスが組織全体の強みを表すのに対し、コンピテンシーは個人の能力や特性を表す点が大きな違いです。
【コアコンピタンスとコンピテンシーの違い】
| コアコンピタンス | 組織が持つ技術力や特許など |
|---|---|
| コンピテンシー | 社員の問題解決力やリーダーシップなど |
コンピテンシーとコアコンピタンスは、本質的に異なる概念です。ただし、個々の社員のコンピテンシー(個人の能力)を高めることが、結果として組織全体のコアコンピタンス(企業の強み)の強化につながる場合もあります。
コアコンピタンス経営とは
コアコンピタンスを軸とした戦略や経営は「コアコンピタンス戦略」「コアコンピタンス経営」と呼ばれています。なぜビジネスにおいて、コアコンピタンスがこれほど注目されているのでしょうか。まず、「コアコンピタンス経営」について概要をおさえておきましょう。
コアコンピタンス経営とは、市場における競争優位性を持つ自社の強みを軸として行う経営のことです。コアコンピタンスの強化につながる戦略や施策にリソースを多く投じます。
コアコンピタンス経営の具体的な戦略の1つに、自社の強みが市場においてどのような立ち位置にあるかを分析し、それをもとに事業活動を進める方法があります。「アウトサイド・イン戦略」と呼ばれるものです。外部環境の状況や社会的ニーズに応じて自社の強みを打ち出したり事業内容を決定したりします。
一方で、近年のような外部環境が激しく変化するVUCA時代では、アウトサイド・イン戦略だけではトレンドに大きく影響され、事業活動の安定に支障をきたす恐れもあります。そこで、コアコンピタンスを出発点として社会的ニーズに対応するという、内から外へ視点を向けるアプローチも考慮しなければなりません。
社会が抱える課題と自社のコアコンピタンスを比べつつ、どのような点を強化すれば競争優位性が高まるかを考える必要があります。
コアコンピタンス経営のメリットと課題
コアコンピタンス経営には、多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。
コアコンピタンス経営のメリット
コアコンピタンス経営には、主に以下の4つのメリットがあります。
【コアコンピタンス経営の4つのメリット】
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 明確な経営方針の確立 | 不安定なビジネス環境においても、自社の強みを軸とした明確なビジョンを持つことができる |
| 市場変化への柔軟な対応 | コアコンピタンスは製品やサービスを生み出す根源的な技術や能力であるため、市場ニーズの変化に応じて新たな製品開発や異分野への展開が可能 |
| 経営資源の集中投資 | 自社の強みを明確に理解することで、限られた経営資源をコアコンピタンスの強化に効率的に投入できる |
| 戦略的提携の促進 | 他社との効果的な連携が進めやすくなり、それぞれの強みを活かした相乗効果を創出できる |
これらのメリットは相互に関連しているため、1つのメリットを活用することで、他のメリットも相乗的に高まっていく好循環を生み出すことができます。
コアコンピタンス経営の課題
一方で、コアコンピタンス経営には以下のような課題もあります。
【コアコンピタンス経営の3つの課題】
| 課題 | 説明 |
|---|---|
| 技術者依存のリスク | 特定の技術者に依存している場合、その技術者の離職により競争力を失う可能性がある。技術の継承と人材育成の体制構築が重要 |
| 技術の陳腐化 | どんなに優れた技術でも、時代の変化とともに陳腐化するリスクがある。コアコンピタンスの継続的な進化と更新が不可欠 |
| 環境変化への対応の遅れ | コアコンピタンスへの過度な依存により、市場の大きな変化に対応できなくなるリスクがある。市場動向の注視と適切な見直しが必要 |
これらの課題に適切に対応しながら、コアコンピタンス経営の強みを活かせるような戦略が求められます。
コアコンピタンス経営における戦略策定のポイント
コアコンピタンス経営の成功には、以下の3つの要素が鍵となります。
まずは、コアコンピタンスの強化と進化に向けた継続的な投資が不可欠です。技術開発や研究開発に注力することで、競合他社との差別化を図り、新市場への展開可能性を探ります。
次に重要なのが人的資本の形成です。技術やノウハウを確実に継承できる人材の育成が重要となります。従業員を投資対象と捉え、働き方改革やダイバーシティを推進し、人材の定着・確保のための制度整備を進めましょう。
そして、産業の将来性を見据えた中長期的な戦略策定も求められます。顧客ニーズの変化に注目しつつ、既存のコアコンピタンスに固執しない柔軟な姿勢でいることが大切です。
コアコンピタンスを見極めるための5つの視点
自社のコアコンピタンスを見極めるには、まず評価の基準となる5つの視点を理解しましょう。
【コアコンピタンスの5つの視点】
| 模倣可能性(Imitability) | 競合他社が簡単には真似できない |
|---|---|
| 移動可能性(Transferability) | 1種類の製品や分野だけでなく、多くの製品や他の分野に応用できる、幅広い展開ができる |
| 代替可能性(Substitutability) | 他社の製品などに置き換えられない |
| 希少性(Scarcity) | 市場において希少価値がある |
| 耐久性(Durability) | 長期間にわたって競争優位性を保てる |
これらの視点は、後述する具体的な分析プロセスの基準として活用します。ただし、全ての条件を完璧に満たす必要はありません。自社の状況や市場環境に応じて、特に重視すべき視点を選択することが大切です。
コアコンピタンスを絞り込む3つのステップ
続いて、先ほどの5つの視点を基準として、実際にコアコンピタンスを絞り込んでいきましょう。具体的には、以下の3つのステップで進めます。
- (1)自社の強みを列挙する
- (2)列挙した強みを評価する
- (3)真似されにくく長期にわたって活用できるものを選ぶ
それぞれの手順を詳しく解説します。
(1)自社の強みを列挙する
第一のステップでは、自社の強みと思われる技術や特徴を思いつく限り書き出していきます。経営層や開発部門、営業部門の社員だけでなく、様々な部門の社員に協力してもらいましょう。カスタマーサポートを担う社員なら、自社製品・サービスのどこに顧客が満足しているか、あるいは不満を持っているか示してくれます。競合他社の技術や特徴などと比較しながら進めることも重要です。ブレインストーミングのように、とにかくどんどん出していくことを意識しましょう。
(2)列挙した強みを評価する
第二のステップでは、第一ステップで列挙したそれぞれの強みを評価します。このときに、先ほどの「コアコンピタンスを探す5つのポイント」を活用します。それぞれの強みに対して5つのポイントから点数をつけていきましょう。比較対象として競合他社の類似項目も点数化しておくと基準が明確になります。
(3)真似されにくく長期にわたって活用できるものを選ぶ
最後のステップでは、強みを絞り込んで自社のコアコンピタンスを決定します。点数の高いものを優先することになりますが、長期間にわたって優位性を維持し、活用できる技術や特徴であるという点も重視してください。これには、従来とは異なる市場に展開できるかどうかという視点も含まれます。
なお、時代の変化によってコアコンピタンスの大胆な変更や更新が求められることもあります。特に技術面は日進月歩で発展しており、市場や競合の動向を考慮した分析・評価が欠かせません。一度コアコンピタンスを決定したあとも、それが現在あるいは将来も有効であるのか、定期的にチェックしていきましょう。
自社の強みで市場獲得・拡大へ
自社の強みにリソースを投じるコアコンピタンス経営は、時代の変化の中で柔軟に対応し、多様化するニーズをしっかり捉えて顧客に価値を提供し続けるために不可欠な視点です。コアコンピタンスを検討する際は、経営層だけで行うよりも、社内の様々な部門の社員や顧客の声も大切にしましょう。視野を広げることで、思わぬ強みが浮かび上がるかもしれません。
強みや市場の分析、コアコンピタンスの決定で行き詰まりを感じていらっしゃる場合は、ALL DIFFERENTが分析・評価そして決定をサポートいたします。「まずは何をすればいい?」という疑問から、より具体的な課題解決方法まで、お気軽にご相談ください。