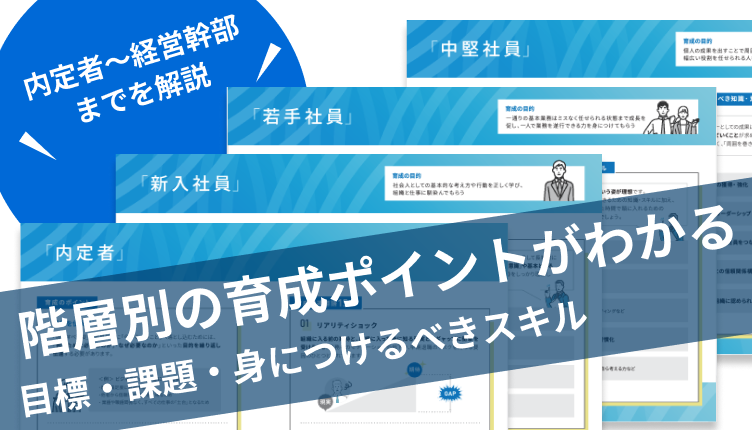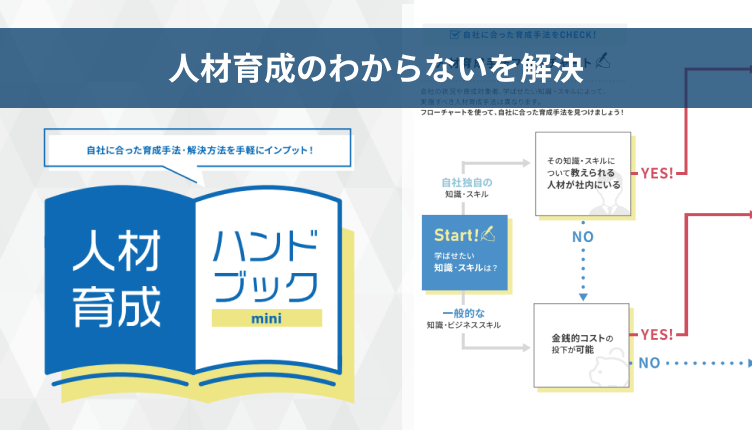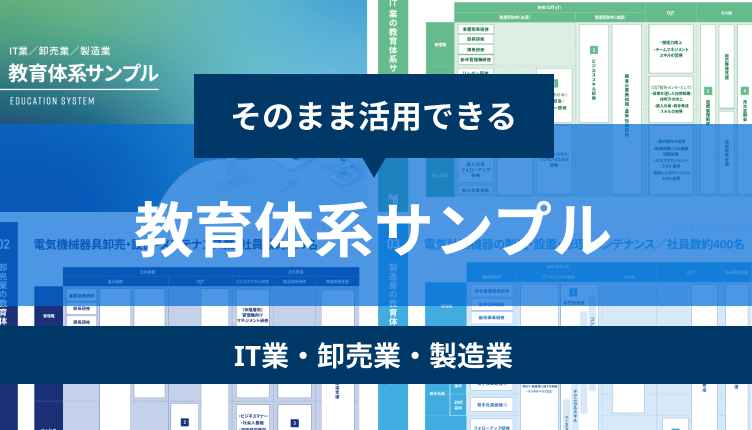これってバーンアウト(燃え尽き症候群)?症状・原因・回復方法
 公開日:2024.06.18
公開日:2024.06.18

熱心に仕事をしていた人が突然意欲を失い、業績も急激に低下したということはありませんか。それは、バーンアウト(燃え尽き症候群)かもしれません。職場でのバーンアウトを予防するには、具体的な意味や症状、要因、本人が取り得る回復方法や周囲の適切な接し方の理解が重要です。
本コラムでは、心理学などでのバーンアウト研究から導かれた知見をもとに、その特徴や回復方法、会社や上司が行うべき対策などを解説します。
バーンアウト(燃え尽き症候群)とは
「バーンアウト(burnout)」とは、それまで熱心に物事に取り組んできた人が、突然燃え尽きたように意欲を失ってしまう状態を意味します。日本語では「燃え尽き症候群」という言い方でも知られています。
仕事やスポーツ、学生生活、ときに家庭生活でも見られ、過度な心身の疲労、特に精神面での疲弊が特徴です。
バーンアウトという言葉をはじめて論文で取り上げたのは、アメリカの精神心理学者であるハーバート・フロイデンバーガーです。1970年代に対人サービスに従事する人が増え、そうした労働者が燃え尽きたように意欲を失う様子が多く見られたことが研究の背景にありました。
その後、社会心理学者のクリスティーナ・マスラークを中心とする研究グループがバーンアウトの定義を確立。「情緒的消耗感」「脱人格化」「個人的達成感の低下」という3つの尺度から重症度を評価するMBI(Maslach Burnout Inventory)を作成しました。この尺度は、現在も活用されています。
バーンアウトは、対人サービス従事者に多く見られると考えられてきました。具体的には、医療職や福祉職、教師などです。しかし現在は、これらの職種に限らず、より多様な職種でバーンアウトが見られるとされています。
バーンアウトの主な症状・特徴
MBIによれば、バーンアウトの主な症状や特徴は3つの観点から捉えられます。先にご紹介した「情緒的消耗感」「脱人格化」「個人的達成感の低下」です。
情緒的消耗感
「情緒的消耗感」は、「仕事を通じて情緒的に力を出し尽くし、消耗した状態」と定義されます。仕事であれば、熱心に業務に取り組んできた結果、精神的に疲れ果ててしまった状態です。
これは、ただ「疲れている」ということではありません。顧客や周囲の人に共感し、思いやりをもって対応してきたり、仕事へのモチベーション維持・向上やより良い成果を求めて熱心に取り組んできたりした結果、心のエネルギーを使い果たしてしまうのです。
脱人格化
情緒的消耗感が生じると、心のエネルギーを節約しようとして「脱人格化」が生じます。脱人格化は、「クライアントに対する無情で、非人間的な対応」と定義されています。もともと対人サービス従事者についての研究で定義されたことを考慮すれば、「クライアント」については、より解釈を広げて「上司や同僚」なども含めてよいでしょう。
脱人格化の状態では、他の人々との共感的な交流を避ける傾向が見られます。典型的には、
- 周囲の人に思いやりのない言動をする
- 相手に対して「○○だから」とレッテルを貼って悪口を言う
- 相手の名前を呼ばなくなる
などが見られます。
個人的達成感の低下
情緒的消耗感や脱人格化が起こると、当然、周囲との人間関係が悪化し、うまくコミュニケーションができなくなります。仕事への集中力も低下して、これまでの業績や成果からは考えられないような仕事の質の低下も起きやすくなるでしょう。
こうした「仕事がうまくいかない」状態が、今度は「個人的達成感の低下」を生みます。自分が期待する成果を上げられず、さらに意欲ややりがいを失い、プライドも傷ついてしまうでしょう。
個人的達成感の低下による気分の落ち込みが激しい場合、「うつ病」と診断されることもあります。
なぜバーンアウトする?2種類の要因と兆候
バーンアウトの大きな要因は、ストレスです。では、どのようなストレスがバーンアウトを引き起こすのでしょうか。これには、「個人要因」と「環境要因」があります。
個人要因と環境要因
バーンアウトを引き起こす要因として「個人要因」と「環境要因」の2種類があります。「個人要因」は、バーンアウトを起こした本人の性格や特性に注目したもの、「環境要因」は本人以外の要素に注目したものです。久保真人教授による2007年の論文*をもとに、各要因の概要を見ていきましょう。
まず個人要因では、「真面目で仕事熱心である」「完璧主義である」などがあげられます。
「求められている成果以上のものを出さなければ」
「期待されている役割以上の働きをしなくては」
といった傾向が強くある場合、バーンアウトにつながりやすいでしょう。
他方、環境要因では、仕事の量だけでなく質も本人にとって過重な負担になっている場合、バーンアウトしやすくなります。具体的には、長時間労働の多さや厳しいノルマ、役割のあいまいさなどです。
長時間労働や厳しいノルマについては、本人の体力や能力との関係を無視できません。一律に同じ基準で課し、それが一部の従業員にとって体力や実力を大きく超えるものである場合、バーンアウトが発生しやすくなるでしょう。
役割のあいまいさも、バーンアウトしやすい環境を作ってしまいます。「誰が何をやるのか」が不明瞭なため、あれもこれもと自分が引き受けてる従業員が出てしまうためです。具体的な目標の立てにくさにつながり、達成感も得にくいでしょう。
同時に、従業員が自律的に仕事を進められない環境も危険です。管理職や先輩から一方的に指示を出すだけでは、実際に業務にあたる側の事情や能力を無視した職場環境になってしまうためです。
*参考:久保真人(2007)「バーンアウト(燃え尽き症候群)―ヒューマンサービス職のストレス」
よく見られる兆候
厚生労働省のe-ヘルスネットによれば、バーンアウトでは次のような症状が見られるといいます。
- 朝起きられない
- 職場に行きたくない
- お酒を飲む頻度や量が増える
- 仕事が手につかなくなる
- 対人関係を避けるようになる
これらの状態が既に発生しているようであれば、バーンアウトの可能性を疑うほうがよいかもしれません。
ここまでの状態になっていない場合でも、以下のような症状が見られるなら休養が必要です。
- 集中力が続かず、注意力散漫になりやすい
- それまで読めていたレベルの文章が理解できない
- 頭がぼんやりして、仕事が進まない
- 「仕事をしなくては」という焦りが常にある
- 上司や同僚、家族から「休んだほうがいい」とよく言われるようになる
- 人間関係が悪化したり、よく交流していた人と疎遠になったりする
バーンアウトしかけているかどうかは、なかなか自分で気づかないものです。周囲からこうした助言がある場合、まずは本人が睡眠と食事をしっかりとって休養する必要があります。
バーンアウトになりやすい人の特徴
前述したバーンアウトになりやすい人の特徴を個人要因と環境要因に分けてまとめたものが、下の表です。
【バーンアウトの個人要因と環境要因】
| 個人要因 |
本人の性格や特性における特徴
など |
|---|---|
| 環境要因 |
本人を取り巻く環境の特徴
など |
また、年齢や性別で比較すると、若者や女性のほうが、年代が上の従業員や男性よりもバーンアウトしやすい傾向があるとされています。
特に年齢については、社会経験や業務経験の少なさが要因です。経験が少ないと、自分自身や職場環境、会社のサポート体制に必要以上の高い期待を抱いてしまったり、受けたストレスへの適切な対処法がわからずため込んでしまったりするためです。
統計で見るバーンアウトと職場でのデメリット
バーンアウトに悩んでいるのは、日本人だけではありません。アメリカの調査会社Future Forumが実施した世界の1万人以上の労働者を対象とする調査結果でも、42%の労働者がバーンアウトを経験したと回答しました。この割合は近年高い傾向が続いていましたが、前回調査からさらに2%増えたとのことです。
どのような人々がバーンアウトしているのかを分析すると、「柔軟な働き方」がひとつのポイントになっているようです。職場における柔軟な働き方について、満足している労働者ではバーンアウトの割合が37%だったのに対して、不満を感じている労働者では半数を超える53%がバーンアウトしていました。
そして、バーンアウトが会社にもたらすデメリットも示唆されています。バーンアウトしている労働者とそうでない労働者を比較したとき、下表のような違いが見られたのです。
【統計で見るバーンアウトのデメリット】
| 全体的な満足感 | バーンアウトしている人のほうが、約1.8倍低い |
|---|---|
| 転職活動の意向 | バーンアウトしている人のほうが、今後1年間に「確実に」転職活動をする傾向が、約3.4倍強い |
| 企業や同僚との 関係 |
企業理念に共感できなかったり人間関係にネガティブな感情を抱いていたりする傾向が、約2倍強い |
*出典:Future Forum “Future Forum Pulse Winer 2022-2023 Snapshot”
これらの他にも、バーンアウトの症状から次のようなデメリットが会社に生じます。
- 仕事の進捗が遅れる
- 仕事の質が低下する
- 職場の人間関係が悪化する
- 気分が大きく落ち込み、欠勤が増える
- 休職や退職につながり、人手不足を招く
これらの項目からわかるように、チームワークや人員確保の面で大きなデメリットが生じるのです。
それまで熱心に仕事をしてきた人材であるにもかかわらず、突然仕事ができなくなるバーンアウト。過度な負担が心身にかかり消耗しきってしまうことが原因ですので、「バーンアウトは甘えだ」とは決していえません。大切な人材に活躍し続けてもらうためにも、会社や組織全体での対策が必要です。
本人におけるバーンアウトからの立ち直り方
バーンアウト対策を講じるには、バーンアウトした本人がどのような過程を経て立ち直っていくのかを押さえておきましょう。ポイントは、仕事と距離をとり、十分に休養すること。久保真人教授の論文では、6段階の回復過程が紹介されています。
*参考:久保真人(2007)「バーンアウト(燃え尽き症候群)―ヒューマンサービス職のストレス」
(1)問題を自覚する
最初の段階で大切なことは、本人がバーンアウトしていることを自覚することです。
仕事熱心な従業員の場合、現在の不調を「ただ疲れているだけ」と認識している可能性があります。しかし、バーンアウトの原因は単純な疲労ではなく、心のエネルギーの枯渇です。これまで過度な負担がかかっていたこと、それによって精神的に大きく消耗していることを認めることが、第一歩となります。
本人による自覚が難しい場合、家族や上司、同僚からアドバイスすることも有効です。
(2)仕事から離れる
問題の自覚ができたら、次は仕事から距離をとります。熱心に取り組んできた状態から、少し冷静な視点をもつということです。
目の前に仕事があると、焦りが募ってなかなか距離を取れないかもしれません。そのため、休暇や休職制度を活用して、仕事そのものから離れる方法をとらなければならない場合もあります。
「自分が仕事を休めば、周囲に迷惑がかかる」と感じるタイプなら、まずは産業医や保健スタッフに相談したり、カウンセリングを受けたりするのもよいでしょう。
職場の上司や同僚にできることは、ノルマや目標の見直し、専門家への相談をすすめることなどです。
(3)休養して健康を取り戻す
休暇や休職制度の利用などで休養できるようになったら、しっかりと睡眠・食事をとり、健康の回復に努めます。焦らず、リラックスして過ごすことが大切です。
心身が回復してくると、これまで忘れていた趣味や新しい活動に楽しみを感じられるようになるでしょう。
本人が仕事から心理的な距離をとるべき期間ですので、職場の人は「あなたがいなくてプロジェクトがうまく進まない」など、不安や罪悪感を引き起こすようなことを言ってはいけません。
休職する場合、バーンアウトからの回復期間は平均3カ月半といわれています。とはいえ、個人差が大きいものですので、しっかり回復できるように本人のペースを優先しましょう。
(4)これまでの生活の課題を分析する
休養する中で、バーンアウトする前の働き方について、自分自身で振り返る期間が訪れます。生活の中に占めていた仕事の量、プライベートでも仕事のことばかり考えていたことなど、本人にとってつらい気持ちになることもあります。
しかし、こうした振り返りが「自分にとって何が大切なのか」の見直しにつながり、今後の働き方につながります。バーンアウトから立ち直るためにも、欠かせないステップです。
一人で考えることがつらい場合は、家族や医師、カウンセラーと話しながら課題と改善策を見いだしていくとよいでしょう。
(5)社会復帰を目指す
バーンアウト前の生活の問題点と改善策が見えたら、いよいよ社会復帰を目指す段階です。
休職前の職場に復帰する場合もあれば、別の部署への異動や、転職を検討する場合もあるでしょう。転職するケースでは、新たな仕事のために学び直しを行う人もいます。
この段階で会社としてできることは、本人のスキルやワークライフバランスの希望を考慮し、業務内容・業務量・職場における役割・働き方を本人と相談しながら調整することです。バーンアウト前の状況のままでは、再発しかねません。過度な負担がかからないよう、仕事内容や働き方について、慎重に調整しましょう。
(6)新しいライフスタイルを実践する
無事に職場復帰できたら、本人が無理な働き方をしていないかを職場の上司や人事担当者は適宜確認するとよいでしょう。
本人にとって、バーンアウトからの復帰は、新しいライフスタイルの実践を意味します。これまでの仕事一辺倒だった生活から、プライベートの時間を確保し適切に休養できる生活に慣れていく段階です。
復帰後に「働き過ぎているのでは」と感じられるなら、周囲から本人に声かけを行うとよいでしょう。同時に、次項で紹介するバーンアウト対策や周囲の接し方も意識してみてください。
会社や上司が行うべき対策・接し方
従業員や部下がバーンアウトしないためには、バーンアウトの環境要因を改善しなくてはなりません。そこで、最後にバーンアウト予防のための声かけや接し方、特に新入社員で気をつけたいポイント、再発防止のためのセルフチェックリストをご紹介します。
バーンアウト予防のための声かけ・接し方
日頃のバーンアウト対策では、主に4つのポイントを意識するとよいでしょう。
【バーンアウト予防 4つのポイント】
- 働き過ぎ(過度な長時間労働など)を防ぐ
- 役割・目標は本人の実力に応じたものを設定し、言語化して明確にする
- 仕事に必要な人間関係構築をサポートし、権限付与を行う
- バーンアウトの兆候がないか定期的にチェックする
まず従業員の働き過ぎに気をつけてください。個人要因にあるような「真面目で仕事熱心」「完璧主義」「他の人との感情的交流が深い」といった特性をもつ従業員は働き過ぎる可能性がありますので、注意が必要です。
また、各メンバーの役割や目標は、本人の知識・スキルに合ったものにし、言語化して明確にしましょう。自身の担当範囲を認識することで、必要以上に仕事を抱え込むリスクを減らせますし、心理的負担の軽減にもつながります。もし目標達成状況が思わしくないようなら、本人に過重な負担が生じていないか、1on1面談などでヒアリングしましょう。
仕事に必要な人間関係の構築や権限付与も重要です。指示を仰いだり協力を要請したりする相手が誰なのかわからない、あるいは話しかけにくい状況は、本人に意欲があっても仕事の障害となるでしょう。必要なシステムやファイルにアクセスできない、決定権がなく自律的に仕事ができないなども、大きなストレスの原因となります。
もし過重な負担がかかっている場合は、早期に環境を再調整しましょう。これには、バーンアウトの兆候がないかの定期的な確認が必要です。
「業務時間が常に長い」「仕事の質が大きく低下した」「人間関係が悪化している」などの大きな変化が見られる場合、既にバーンアウトしかけている可能性があります。本人に状況を聞くだけでなく、産業医や保健スタッフ、メンタルヘルス対策担当者などの相談窓口を伝えるとよいでしょう。
新入社員で特に気をつけたいポイント
前項のチェックポイントに加えて、新入社員には、よりきめ細やかなサポートが必要です。特に新卒の新入社員は社会人経験が少なく、自身の能力や職場に対して大きな期待を抱いているため、リアリティ・ショック(理想と現実のギャップによるショック)を受けやすいです。新人への対応で気をつけたい4つのポイントを見ていきましょう。
【新入社員をバーンアウトさせないための4つのポイント】
- 期待する役割や目標、会社のサポート体制を丁寧かつ正確に説明する
- 業務で混乱している場合は、業務範囲やレベルの適切さも確認する
- 休憩時間は休憩するよう呼びかける
- 仕事上の苦情や批判は人格攻撃ではないことを繰り返し伝える
期待する役割や目標については、組織の中での役割やそれを行うことの重要性、期待する仕事内容や成果を丁寧に説明しましょう。同時に、会社に対して高すぎる期待を抱かないよう、職場でできるサポート内容や利用可能な制度も、正確に伝えなければなりません。
新入社員が業務で混乱しているようなら、業務を進める手順やツールの扱い方を教えるとともに、取り組む業務の範囲やレベルが適切かを確認しましょう。困った時に誰に相談すればよいかも伝えると安心です。ただ、相談相手となる従業員に過度な負担がかからないように注意してください。
ノルマ達成に必要な知識・スキルが不足している場合は、まずはそれらの習得を目標に設定するほうが無理なく取り組めます。
もし休憩時間にも働いているようなら、休憩を呼びかける必要があります。仕事の遅れを取り戻そうとしているとしても、休憩は労働者の権利であり、1日の後半を乗り切るためにも欠かせません。「上手に休憩をとることも仕事のうち」と伝えるとよいでしょう。
意欲が高く、顧客や周囲の従業員と必死に関係づくりをしている場合も要注意です。相手の立場に寄り添いすぎると、仕事で生じた苦情や批判を自分自身の人格への攻撃と勘違いしてしまう可能性があるためです。
良好な関係を築くことは望ましいものですが、そこにはやはり一定の冷静さが必要です。「苦情や批判を受けても、それは人格への攻撃ではない。システムややり方への指摘である」という考え方を都度伝えるとよいでしょう。
再発防止のためのセルフチェックリスト
バーンアウト予防には、本人が自身の状況を定期的にチェックできるリストも有用です。
バーンアウトのチェック項目としては冒頭でご紹介したMBIが広く使われていますが、より日本の労働環境に合った尺度として、久保真人教授らが作成したJBS(Japanese Burnout Scale)があります。
JBSの項目は広く公開されているため多くの現場で活用されてきました。実際にバーンアウトしている人の特徴とも適合性が高いとされており、信頼のおける尺度のひとつです。
【日本版バーンアウト尺度(JBS)】
| 項目 | 内容 | 分類 |
|---|---|---|
| 1 | こんな仕事、もうやめたいと思うことがある。 | E |
| 2 | われを忘れるほど仕事に熱中することがある。 | PA |
| 3 | こまごまと気配りすることが面倒に感じることがある。 | D |
| 4 | この仕事は私の性分に合っていると思うことがある。 | PA |
| 5 | 同僚や顧客の顔を見るのも嫌になることがある。 | D |
| 6 | 自分の仕事がつまらなく思えてしかたのないことがある。 | D |
| 7 | 1日の仕事が終わると「やっと終わった」と感じることがある。 | E |
| 8 | 出勤前、職場に出るのが嫌になって、家にいたいと思うことがある。 | E |
| 9 | 仕事を終えて、今日は気持ちのよい日だったと思うことがある。 | PA |
| 10 | 同僚や顧客と、何も話したくなくなることがある。 | D |
| 11 | 仕事の結果はどうでもよいと思うことがある。 | D |
| 12 | 仕事のために心にゆとりがなくなったと感じることがある。 | E |
| 13 | 今の仕事に、心から喜びを感じることがある。 | PA |
| 14 | 今の仕事は、私にとってあまり意味がないと思うことがある。 | D |
| 15 | 仕事が楽しくて、知らないうちに時間がすぎることがある。 | PA |
| 16 | 体も気持ちも疲れはてたと思うことがある。 | E |
| 17 | われながら、仕事をうまくやり終えたと思うことがある。 | PA |
*E:情緒的消耗感、D:脱人格化、PA:個人的達成感(逆転項目)
久保真人(2007)「バーンアウト(燃え尽き症候群)―ヒューマンサービス職のストレス」より作成、ビジネスパーソンに活用しやすいよう、「患者」を「顧客」に変更
上の表では、PAに該当する項目が「個人的達成感」の逆転項目となっています。そのため、PAの項目では、「いいえ」や「あまりそう思わない」などが増えるほど、バーンアウトの可能性が高いという評価になります。EやDとなっている項目は、「はい」「わりとそう思う」などの回答が増えるほど危険です。
職場におけるストレスチェックと併せてバーンアウトのセルフチェックを実施し、より多くの人材が活躍できる職場づくりを目指しましょう。