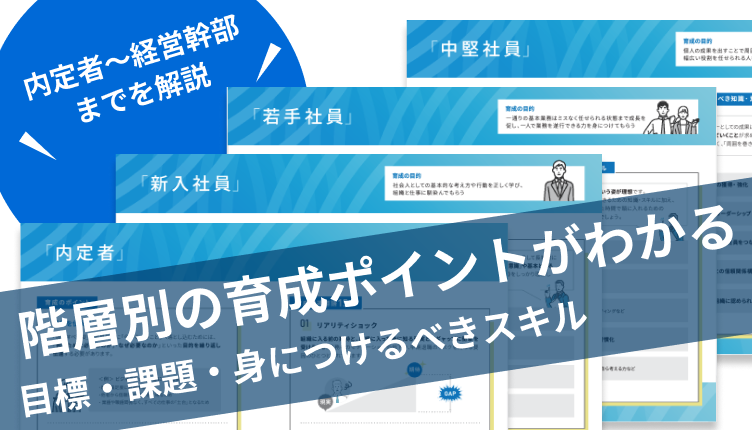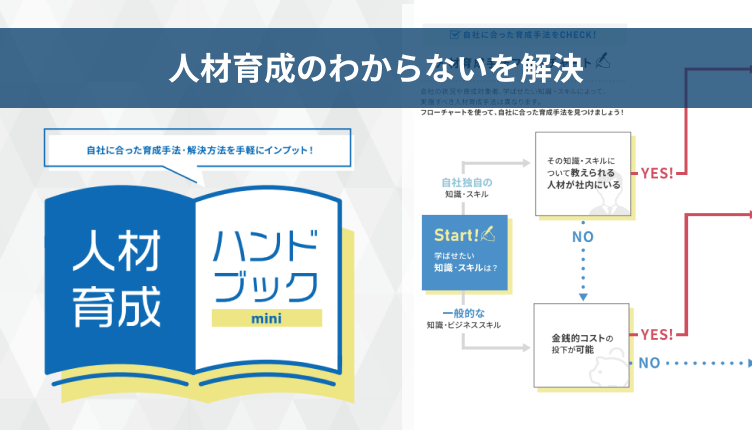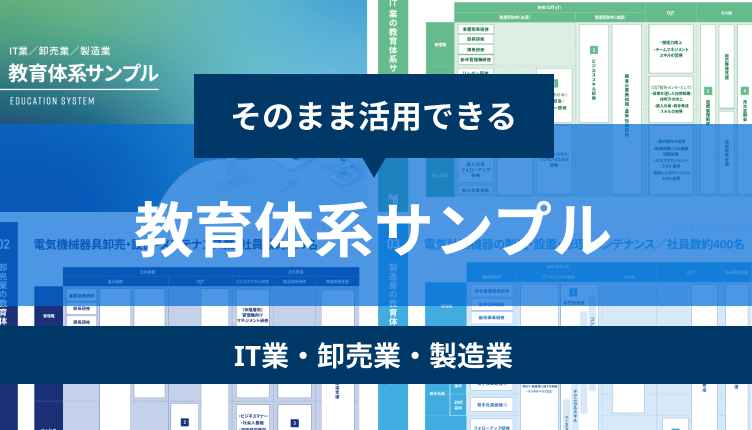Off-JTとは?OJTとの違い、Off-JT研修のやり方や具体例を解説
 更新日:2025.01.15
更新日:2025.01.15
 公開日:2022.07.22
公開日:2022.07.22

Off-JTとは職場や通常業務から離れた場所で行われるセミナーや研修のことです。業務だけでは吸収できない専門知識や働くマインドを育てるのに有効です。
Off-JTのメリット・デメリット、Off-JT研修のやり方や企業での導入事例などについて解説します。
Off-JTとは?定義とOJTとの違いを解説
Off-JTとは「職場外訓練」とも呼ばれ、職場とは離れた場所でセミナーや研修を行い学習することをいいます。
Off-JTと似た言葉に、OJTやSD(自己啓発)などがあり、違いがよくわからないと感じている人も多いかもしれません。
ここでは、Off-JTの定義や、OJT、自己啓発との違いについて解説します。
Off-JTの基本的な定義と意味
Off-JTとは「Off the Job Training」の略称で、読み方は「オフジェイティー」です。職場とは離れた場所で学習することをいい、Off-JT研修とは、社外や職場外で研修することを指します。
日常業務や職場から離れた環境で、ビジネスの基礎や体系的な知識を学べるのがOff-JTのメリットです。Off-JTは人材開発の現場で広く支持され続けており、新入社員研修や管理職研修、ビジネスマナーに関する研修など様々な分野で取り入れられています。
OJTとの違い
Off-JTと同じく人材育成の場面でよく使われるOJTは、「On the Job Training」の略で、読み方は「オージェイティー」といいます。OJTは、現場で実際に仕事を進めながら助言・サポートする育成手法です。
Off-JTとOJTには主に以下のような違いがあります。
| Off-JT | OJT | |
|---|---|---|
| 場所 | 職場外 | 職場内 |
| 育成方法 | 日常業務とは別で講習などを行う | 実際に仕事をしながら学習する |
| 期間 | 短期間 | 中長期間 |
| 内容・目的 | 業務外の専門的知識・スキルなどの習得 | 業務知識やスキルの習得 |
場所の違い
Off-JTは職場外で実施される教育施策を指すのに対し、OJTは職場内で行われる育成手法のことを指します。実施場所は両者の大きな違いです。
育成方法の違い
Off-JTは日常業務とは別に、講習形式で学習を行います。一方、OJTは実際に業務をこなしながら、現場で上司や先輩などに教わって仕事を覚えるやり方です。
Off-JTは座学を通したインプットが主体となるのに対し、OJTは実践しながらスキルを身につけるアウトプットが重視されている点に違いがあります。
このように育成方法が異なることから、Off-JTで基礎を学んだ後にOJTで実践するという、2段階で指導を行う方法も有効です。
期間の違い
Off-JTは研修・セミナー形式で実施されるため、短期的な限られた期間で実施されることがほとんどです。対してOJTは、日常業務を通じて意図的・計画的・継続的に指導を行うので、中長期的に継続されるケースもあります。
内容・目的の違い
Off-JTは新入社員研修や管理職研修など、個別のスキルを高める知識や、仕事を進めるうえでの基本的な知識をインプットする内容が一般的です。対して、OJTは特定の業務に直結するノウハウを指導するケースが多いといえます。
自己啓発との違い
職場外で学習する方法としては、Off-JTのほかに自己啓発の方法が挙げられます。Off-JTと自己啓発の大きな違いは、Off-JTでは、学習機会を企業側が主導しているのに対し、自己啓発では社員の自主性に任せられているということです。
Off-JTの研修では、プログラムを企業側が準備し受講を強制するので、通常、受講時間は業務時間としてカウントされます。一方、自己啓発では、企業側や受講費用の助成やeラーニング講座の準備などといった面で支援を行えますが、実際に受講するかどうかは社員の意思に任せるしかありません。
Off-JT教育のメリットと求められる背景
Off-JTを活用した教育法や研修制度は、多くの企業で導入されていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、Off-JTが求められる背景とメリットについて解説します。
Off-JT教育や研修が求められている背景
Off-JT教育や研修が求められている背景には、慢性的な労働力不足により、企業側が現場に負担のかからない人材育成を必要としていることがあります。従来のOJT制度には、上司や先輩が日常業務をこなしながら部下や後輩を指導するため、現場に負荷がかかってしまうというデメリットがありました。Off-JT教育であれば、社外から講師を招くなど追加コストは発生するものの、既存社員の仕事を増やすことなく効果的な人材育成が可能です。
また、DX推進や事業環境の急速な変化により、新しいスキルや知識が必要とされていることも、Off-JT教育や研修のニーズを高める要因になっています。ITや外国語スキルなど、既存社員には不足しているスキルやノウハウを効果的に習得するために、社外のリソースを活用できるOff-JT研修が必要とされているのです。
体型的な知識の習得
Off-JTの大きなメリットの1つに体系的な知識やノウハウの習得を促すことができる点があります。社員は、普段は目の前の業務に追われて後回しになっているインプットの機会が与えられることで、仕事に必要な知識の土台を強化できるでしょう。Off-JT研修では、講習やセミナー形式でまとまった時間が設けられるため、社員はじっくりと学習ができ、実務への理解をより深められることが可能です。
育成効果の均一化
複数社員に対して一斉に実施できるため、育成の効果を均一化しやすいのもOff-JTのメリットです。
業務を進めながら助言やサポートを受けるOJTでは、1対1の教え方になる傾向が高いため、先輩社員の育成スキルによって後輩の理解度や成長度にムラが出てしまうリスクがあります。Off-JTでは、集合型研修で同じ内容を1名の講師が同時に教えるため、研修を受けた社員の習熟度に差が出にくい傾向があります。e-ラーニングを活用した場合も、同じ内容の講習を受けるため、育成効果が均一化されやすいといえるでしょう。
現場の負担軽減
基本的にOff-JTは、外部の講師に依頼してセミナーや研修を実施します。職場内での研修やサポートでは、社歴の長い社員や管理職員が、仕事をこなすのと同時に育成カリキュラムの作成や指導に時間を割く必要がありました。Off-JTであれば、基礎的な教育を外部に委託したり、配属前に基礎知識を固めたりしておくことで、現場社員の教育負担を軽減することが可能です。
さらに、社内に対応できる社員が少ない専門分野や新しいスキルの教育については、外部のセミナーを利用することで学習度がより深まるでしょう。
横のつながりを広げられる
ワークショップやチーム作業などを研修メニューに取り入れることで、参加者同士の交流機会が提供できるのもOff-JTのメリットです。新入社員向けのマナー研修や管理職向けの研修など、同じ階層の社員のつながりを広げることで、職場の安定感やチームワーク強化につながります。
Off-JTのデメリットと課題
Off-JTは、企業の人材育成において重要な手法の1つですが、実施に際していくつかのデメリットや課題もあります。
これらを理解し、適切な対策を講じることで、効果的な人材育成が可能となります。
以下では、Off-JTの具体的なデメリットとそれに伴う課題について解説します。
実務とかけ離れて定着が見えない可能性
Off-JTは座学やワークショップ形式で行われるため、実務とかけ離れた内容になる場合があります。テーマによってはそのときに対応している実務との関連イメージがわかず、短期的には効果が見えにくいケースがあるので注意が必要です。場合によってはOff-JTの必要性を疑問視され、育成にかけられる時間や予算を減らされてしまうかもしれません。
これを防ぐためには、Off-JTの内容を実務と密接に関連付け、研修後に具体的な実践の機会を設けることが重要です。また、長期的な育成計画を策定し、社内で共有する仕組みをつくるとよいでしょう。
受講者の意識やモチベーション
Off-JT研修は座学形式のものが多いため、受講者が受動的になりがちで、意識やモチベーションの低下が起こりやすいことがデメリットとして挙げられます。参加者が「聞いているだけ」「その場にいるだけ」になってしまうと、学びの効果が薄くなり、結果的に知識が定着しにくくなります。
これを解決するためには、研修内容を魅力的かつ実践的に構成し、ディスカッションやグループワークを取り入れて、受講者が積極的に参加できる仕組みを整えることが必要です。
コストがかかる
Off-JTは、特に外部講師を招いたり、社外で研修を行ったりする場合に高額なコストがかかることがデメリットです。
また、研修期間中の社員は業務から離れるため、業務の停滞や生産性の低下も懸念されます。
人材育成は企業の将来的な競争力を高めるための投資と捉えることが重要です。事前に研修内容やコストの効果をしっかりと検討し、適切な予算を立てて実施することで、コストに見合う成果を得ることができます。
Off-JTのやり方と研修プログラムの実施方法
Off-JTは、企業内研修や外部講師を招いてのセミナーなど、様々な形で取り入れることができ、社員のスキル向上を目的とした取り組みとして効果を発揮します。
ここでは、Off-JTの具体的なやり方や研修プログラムの具体例について解説します。
Off-JTの実施手順とやり方
Off-JTを実施する際は、まず研修の目的とゴールを明確に設定することが重要です。
次に、受講者のニーズや学習目標に基づいて、講義やワークショップ形式の研修プログラムを設計します。講師の選定や資料の準備を行い、研修を効果的に進められるよう環境を整えましょう。
研修後には、学んだ内容を実際の業務にどう活かすかを振り返り、フォローアップを実施することも効果的です。これにより、学習効果の持続と実務への反映が促進されます。
研修プログラムにおけるOff-JTの取り入れ方
研修プログラムにOff-JTを取り入れる際には、受講者が学ぶべきテーマや内容を事前に明確にし、プログラム全体を体系的に設計することが重要です。
例えば、新入社員向けにはビジネスマナーやロジカルシンキングの研修を、管理職向けにはリーダーシップやマネジメントスキルに関する講座を用意するなど、対象者に合わせたカリキュラムを作成します。
Off-JTの実施方法は、集合型研修とe-ラーニングの大きく2つに分けられます。
集合型研修は、複数人を対象にミーティングルームや会場を借りて、また近年ではWEB会議ツールなどを用いてライブ配信型で実施する研修です。研修の目的に合わせて受講する社員を選別でき、必要な時期に必要な層に対して研修が行えます。
e-ラーニングは、スマートフォンやタブレットで社員の都合の良い時間・場所で受講できるタイプの研修です。近年は動画コンテンツが増えており、非対面でも臨場感のある研修を実施できるようになっています。
e-ラーニングで知識レベルをそろえ、集合研修でより高いレベルの研修を実施するなど、異なる実施形式を組み合わせて効果を高めるケースも見られます。集合型研修と比べると、比較的低コストで実施できる点も、e-ラーニングの魅力です。
また、研修後のフィードバックを受けることで、効果的な知識の定着と実践につなげることができます。研修内容が実際の業務にどのように反映されるかを明示することで、受講者のモチベーションも高められるでしょう。
Off-JT研修プログラムの具体例
Off-JT研修プログラムは、階層別・業務別・ビジネススキル別などに分けると研修の目的やニーズが捉えやすくなります。
それぞれの研修プログラムの具体例は以下の通りです。
| 研修の目的 | 具体例 |
|---|---|
| 階層別 |
|
| 業務内容別 |
|
| ビジネススキル別 |
|
階層別研修に、Off-JTの業務内容別やビジネススキル別の研修プログラムを組み合わせるのもよいでしょう。
階層や職務に関係なく通用するOff-JT研修プログラムの代表的な例としては、ビジネスマインド研修・コンプライアンス研修などがあります。
ビジネスマインド研修では、プロフェッショナリズムやリーダーシップ、コミュニケーションスキルを学び、業務の質を向上させることが目的です。コンプライアンス研修では、法令遵守や倫理観、個人情報保護に関する知識を習得し、企業リスクを未然に防ぐスキルを養います。これらの研修は、社員が業務を円滑に進めるための基礎を築くだけでなく、企業全体の信頼性を高める役割も果たします。
研修効果を高めるためのポイント
Off-JTの研修効果を最大化するためには、事前準備と研修後のフォローアップが不可欠です。
まず、研修前に受講者の学習目的を明確にし、自分が何を学びたいのかを整理させます。次に、研修中はディスカッションや実習を取り入れることで、参加者同士が意見交換を行い、学びを深める機会を設けます。最後に、研修後は学んだ内容を実際の業務にどう適用するかを具体的に計画し、上司や同僚と共有することが、効果的な学びの定着につながります。
Off-JTの活用事例と活用のポイント
Off-JTでいくら知識を蓄えても、実務で実践できなければ意味がありません。Off-JTで習得した知識や技術をOJTで実践し、不足した部分はまたOff-JTで補っていくサイクルをつくることが大切です。
最後に、実際の企業におけるOff-JTの活用状況や導入事例、活用のポイントを解説します。
企業のOff-JT研修実施の状況
厚生労働省の令和5年度「能力開発基本調査」によると、Off-JTに費用を支出した企業の割合は49.2%で、前年度の調査と比べて上昇傾向にあります。
Off-JTに支出した労働者1名当たりの平均額は1.5万円で、自己啓発支援に支出した費用の労働者1名当たり平均額 0.3万円と比較すると、コスト的には割高になっていることがわかります。
Off-JT研修の実施内容の割合は、「新規採用者など初任層を対象とする研修」が74.8%と最も高く、続いて「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」が48.0%、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」が47.2%です。
今後の実施したいOff-JT研修の内容については、「新たに管理職となった者を対象とする研修」が39.7%、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」が36.3%となっており、新人研修よりも管理職やマネジメント向けの研修ニーズが高まっていることがうかがえます。
*参考:厚生労働省|令和5年度「能力開発基本調査」の結果を公表します
企業におけるOff-JT活用事例
Off-JTに費用を支出している企業は多くありますが、積極的にOff-JTを導入し活用している企業はどのような取り組みを行っているのでしょうか。
ここでは、企業におけるOff-JT活用事例を3つご紹介します。
伊藤忠商事株式会社
総合商社の伊藤忠商事株式会社では、重要施策の1つを「人的資本の強化」においており、優秀なグローバル人材の育成を推進しています。
研修体系を必須・選抜・選択の3つのグループに分け、特に選抜・選択の研修では、海外短期ビジネススクール派遣・IMBA・コーチングやマネジメント研修など多くのOff-JT研修プログラムを取り入れているのが特徴です。
多様な価値観に応じたキャリア形成支援として、場所を選ばず、マネジメントスキルから、DX、ファイナンス・マーケティング・語学など、約13,000講座を受講できる選択型のオンライン研修プログラムを提供しています。
合同会社ユー・エス・ジェイ
アミューズメント施設USJを展開する合同会社ユー・エス・ジェイでは、2010年度に社内大学「Universal Academy」を立ち上げました。勤続年数や年齢にかかわらず、社員の希望者なら誰でも、各自の役割の大きさや成長段階に応じて必要なものを必要なときに受講できるような場を提供しています。
Universal Academyでは、ロジカルシンキングやマーケティングなどの「ビジネススキル」に加え、ユー・エス・ジェイの経営方針や哲学を学ぶ「マインド」、各部門・職種・グレードに必要な知識スキルを習得する「プロフェッショナル」の分野でOff-JT研修を実施しているのが特徴です。受講者主体の研修プログラム構築や研修環境の整備などを行うことで、社員アンケートでも高い満足度や活用度を示す結果が出ています。
盛岡セイコー工業株式会社
盛岡セイコー工業株式会社は、時計メーカーセイコーウォッチの子会社で岩手県に工場を構え時計製造を行う企業です。
盛岡セイコー工業株式会社では、外部講師を含む社内研修と外部機関主催の社外研修を組み合わせ、積極的にOff-JTを取り入れています。新入社員・係員・主任・副主査の階層別研修から、管理・監督者向けの研修まで、充実した社外研修や社内講座を実施しているのが特徴です。外部機関主催の研修では、各種通信教育のほか、岩手経済研究所・労働基準協会・産業技術短期大学など、様々な外部機関に委託して研修を行っています。
全社員に教育・自己啓発の環境を整え、自発的な学びの機会を提供することで、社員のモチベーションが高まり、定着率も向上しています。
Off-JTを活用するポイント
Off-JTについては、その場その場での導入では、期待する効果がなかなか得られないため、各部署に任せきりにせず人事担当者が全体を管理することが大切です。
Off-JTのメリットを活かし上手に活用するために以下のようなポイントをおさえておきましょう。
- 人材育成計画は長期的な視点で策定し、社内で共有する
- OJTや自己啓発と組み合わせる
- インプットだけでなくアウトプットの場・機会を提供する
- 環境や時代の変化に合わせてアップデートする
スポットで短期的にOff-JTを導入しても、なかなか思うような効果は得られません。人材育成計画について長期的な視点でロードマップを敷き、進捗を追っていくようにしましょう。人材育成の方針や将来を見据えた全体像について、社内で十分共有しておくことも大切です。
また、全体の研修や教育体系は、必要に応じてOff-JTだけでなくOJTや自己啓発メニューと組み合わせて構成するとよいでしょう。Off-JTもOJTも、教わるという意味では受け身になります。社員の成長を引き出すためには、自発的な学びを推進することも大切です。教わりながらインプット・アウトプットする場とともに、自ら学ぶ場を与えることで、Off-JT研修の効果もより高まることが期待できます。
さらに、Off-JTは導入しておしまいではなく、時代や環境の変化に合わせてアップデートする必要があります。研修内容がずっと同じ内容だったり、使い回しの内容だったりすると、研修を受ける側のモチベーションも下がってしまうでしょう。業界の最新動向や社員の世代・キャリア観に合わせ、常に内容やテーマのアップデートを怠らないことが大切です。