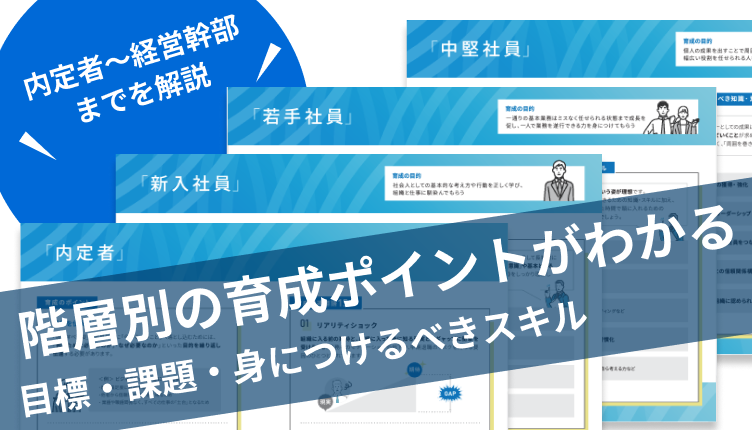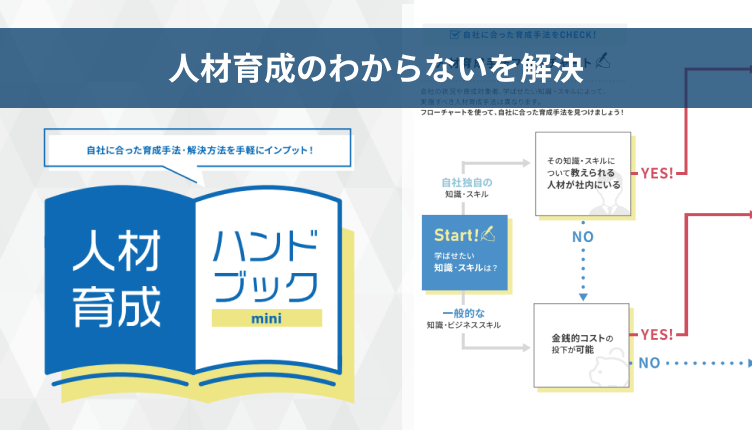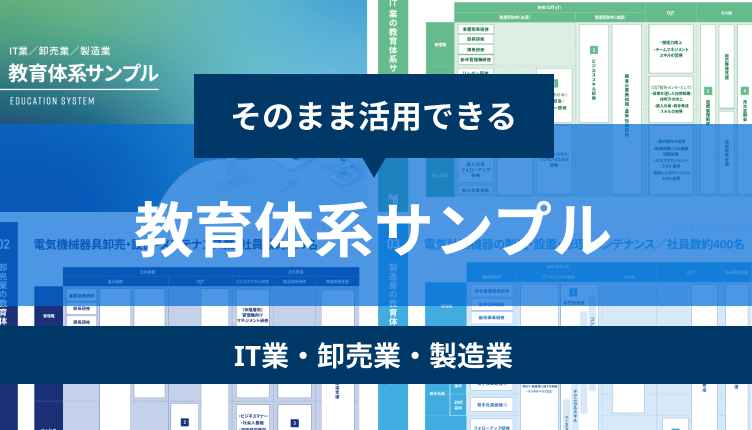チームビルディングとは?意味・目的・手法と効果を高めるポイント
 更新日:2025.03.19
更新日:2025.03.19
 公開日:2019.07.02
公開日:2019.07.02

チームビルディングとは、成果を出す組織を作るために行う様々な取り組みのことです。具体的な手法は、研修やゲーム、アクティビティなど多岐にわたりますが、最も重要なことは目的に合った施策を選ぶことです。
本コラムでは、チームビルディングの意味や目的、リーダーに求められるスキル、チームビルディングのフレームワークとして有名な「タックマンモデル」などを詳しく解説します。
チームビルディングとは
はじめに、チームビルディングとは何かを確認しましょう。チームビルディング自体の意味とともに、よく比較される「チームワーク」や「チームマネジメント」との違いをおさえると、より具体的なイメージがわかります。
チームビルディングの意味
チームビルディング(team building)とは、文字通り「チーム作り」という意味です。しかし、ビジネスで求められるチームビルディングの意味合いには、「成果を出すために各メンバーの強み・能力を組み合わせ、相乗効果を発揮させる」ことも含まれます。
簡単にいえば、「各メンバーが能力を発揮しながら協働し、チームとして付加価値や生産性を高めるために行う取り組み」といえるでしょう。
チームビルディングとチームワークの違い
チームでの活動というと、「チームワーク」を思い浮かべる人も多いでしょう。チームビルディングとチームワークの違いは、目的・目標の方向性にあります。
チームワークとは、部門や部署、部門横断的に結成された集団など、比較的小規模の集まりにおいて、メンバーが力を合わせて効率的にタスク(仕事)を遂行することです。「作業を遂行する」という所に力点があるため、あらかじめ「何をするか」というタスクが見えてなければ発揮できません。
これに対し、チームビルディングは、具体的なタスクが明確になる前から取り組みが始まります。“チームのビジョン・ミッションを実現する”という点が重視され、チームワークを発揮できるような組織を作る取り組みです。
チームビルディングとチームマネジメントの違い
チームビルディングを主導するのは、主にチームリーダーです。チームリーダーは、同時に「チームマネジメント」も行わなければなりません。両者には「有効に機能するチーム作りを行う」という共通点がありますが、「誰が取り組むか」という点で異なります。
チームビルディングについては、特に初期段階ではチームリーダーが主導する場面が多いでしょう。しかし、常にリーダーが先頭に立つわけではありません。多様な取り組みの中でチームメンバー全員が参加し、積極的にチームの結束を高め、連携しながら活動することが、チームビルディングの特徴だからです。
チームがうまく機能し始めれば、リーダーはそれを見守りながら、必要な部分だけサポートするという時期がくるでしょう。
一方、チームマネジメントは、どの時期においてもリーダーが主体となって取り組むものです。チームマネジメントには、メンバーへの指示・指導、チームの予算管理、業務進捗管理、働きやすい環境の整備・維持などが含まれます。
チームビルディングの目的と必要性
ただメンバーを集めてグループを作るのではなく、「チーム」として機能するようにしなければならない主な理由は、人材の多様化や激しい外部環境の変化にあります。チームビルディングによって何を目指しているのかという目的と合わせて、状況に合う適切な手法を選ばなければなりません。
ビジネスにおけるチームビルディングの必要性
チームビルディングの必要性が説かれる最大の理由は、近年進むビジネスのグローバル化・多様化にあります。従来の日本で重視されてきた「あうんの呼吸」や「察しと思いやり」といった文化は、多様なバックグラウンドをもつ人材が参加する組織・チームでは通用しません。
暗黙の了解を見える化し、明確なビジョンのもとでチームが一丸となって取り組める組織作りを意識的に行うことが、成果を出す鍵となります。
国籍を問わず多様な人材と働いたり、フレックスタイム制やリモートワークなどの多様な働き方に対応したりできるチームを作るには、チームメンバーがお互いを理解・尊重し、それぞれの能力を効果的に発揮できる協力体制の構築が必要なのです。
チームビルディングの主な目的
チームビルディングの目的は、チームに与えられた目的・目標を達成できるチーム作りです。これをより詳しく見ると、
- ビジョン浸透とマインドセットの形成
- メンバー同士の相互理解と円滑なコミュニケーションの促進
- 役割分担と協働関係の促進
という3つの具体的な目的が出てきます。
ビジョン浸透とマインドセットの形成
まず、チームが与えられた目的・目標を達成するには、どのようなビジョンのもとに活動するかをメンバーが理解していなければなりません。そうしたビジョンの浸透と、ビジョンに合致するマインドセットの形成が、チームビルディングの1つ目の目的です。
マインドセットとは、それまでの教育や経験などから形成される思考パターンのこと。「無意識の思考のクセ」と言い換えることもできます。
チームビルディングでは、各メンバーがもともと持っている思考のクセを調整し、チームのビジョン実現に必要な考え方の基準を習得しなければなりません。個人プレーで目標達成をするのではなく、“チームで”達成するという姿勢がなければ、情報共有やコミュニケーションで大きな課題が発生し、成果を出すチームにはならないからです。
メンバー同士の相互理解と円滑なコミュニケーションの促進
ビジョンの浸透やマインドセットの形成と同様に重要な取り組みが、メンバー同士の相互理解とコミュニケーションの促進です。これが、チームビルディングの2つ目の目的となります。
チームが結成された初期の段階は、基本的に「よく知らない人同士の集まり」です。そのままでは各メンバーが個人プレーで仕事を進める状況とあまり差がありません。チームとして動けるようになるには、他のメンバーがどのような人なのか、何が得意なのかを知る必要があります。
つまり、機能するチームには各メンバーがもつ知識・スキルを把握し、強みを活かし合いながら連携できる人間関係が不可欠なのです。
役割分担と協働関係の促進
チームメンバーの能力を最大限に引き出すには、各メンバーの知識・スキルに基づく適切な役割分担も必要です。
さらに、誰が何を担当しているかが明確になれば、「全てのタスクを一人で抱え込む」「自分が苦手なタスクに必要以上に時間をかけてしまう」といった事態を防ぎ、チーム全体の業務効率を向上させることができるでしょう。こうした強みを活かす役割分担と協働関係の促進が、チームビルディングの3つ目の目的となります。
ただし、チームで目的・目標の達成に向かうマインドセットと良好な人間関係があってこそ、適材適所を実現したチーム作りができます。役割分担だけで終わらせず、他の2つの目的とあわせて取り組むことが、何よりも重要です。
チームビルディングのプロセス「タックマンモデル」と施策の方針
チームビルディングのプロセスには、結成から成果を出すまで4つのステップがあります。これにチームの解散までを含めた5ステップが「タックマンモデル」と呼ばれるフレームワークです。
【タックマンモデルにおけるチームビルディング5ステップ】
- (1)形成期
- (2)混乱期
- (3)統一期
- (4)機能期
- (5)散会期
各ステップの概要とチームビルディングの方針を見ていきましょう。
形成期
1つ目のステップである形成期は、チームを構成するメンバーが決定したばかりの段階です。メンバー同士はお互いのことをよく知らず、ビジョンやチームの具体的な目的・目標も理解していません。
形成期でリーダーが取るべき施策は、
- ビジョンの明示と浸透
- メンバー間の相互理解の促進
- チーム全体の方向性を踏まえた良好な人間関係の構築
- コミュニケーションを取りやすい雰囲気の醸成
- 交流機会の提供
などです。
形成期におすすめの手法は、「ペアインタビュー」です。メンバーがペアになって、与えられたテーマについて交互にインタビューを行い、お互いを知る機会とします。インタビュー後、メンバー同士で感想を伝え合うことで、さらなる理解促進につなげられます。
混乱期
2つ目のステップは、混乱期です。混乱期は、ビジョンや目的・目標が明確になりつつも、どのように目標を達成するかが定まっていない段階。試行錯誤が続き、メンバー同士で衝突することもあります。
混乱期にリーダーが留意すべきことは、
- 発言力のあるメンバーに迎合せず、各メンバーの率直な意見を聞く
- 建設的な話し合いと模索を進める
- 意見を出し合える環境を整備・維持する
などです。それぞれの考え方・能力を確認し、チームの動き方を決めていきましょう。
混乱期は、メンバーの衝突が増えるからこそ「協働する」ことの大切さを感じられる取り組みが重要です。具体的な手法としては、混乱期に入る前に「ペーパータワー」や「レゴゲーム」など、協力体制が鍵を握るゲームを通じて混乱期の疑似体験ができるワークショップを実施する方法があります。
こうしたワークショップは、2回に分けて行うと、チーム内での役割分担の重要性をより感じられるでしょう。1回目は役割分担をせずに進め、2回目は「どのような役割分担が必要か」を考えながら進める方法です。こうすることで、役割分担をするほうがチームとしての一体感が生まれ、良い成果を得やすくなることを理解できます。
統一期
混乱期を乗り越えると、3つ目のステップである統一期に入ります。チームとしての行動規範や役割分担が形成され、メンバー間の衝突も減るでしょう。混乱期をチームで乗り越えた経験が礎となり、団結力も高まります。
統一期では、リーダーが行うべき取り組みは多くありません。
- チーム全体がうまく動き始めたら、メンバーの主体性を尊重しながら見守る
- 特定のメンバーに多くの業務が集中するような場合は、役割や業務の割り振りを見直す
- 業務に必要な知識・スキル向上のサポートを行う
といった取り組みを行うとよいでしょう。
機能期
続く4つ目のステップである機能期では、よりチームとして安定した活動ができるようになり、具体的な成果も出せるようになります。
各メンバーが自分の役割を理解して自律的に業務を進められる状態を維持できるよう、
- チームにおける心理的安全性の確保
- メンバーのサポートやフィードバック
- PDCAやOODAループによる課題解決と成果の維持・向上
などを行ってください。
なお、PDCAとは、計画を立てて実行し、その振り返りと改善を行って次のアクションへつなげるサイクル。計画の策定と承認のプロセスがあるためOODAループよりも丁寧に進める手法です。
これに対して、OODAループは観察から状況判断を行い、意思決定と実行へ進む短いサイクルが特徴です。外部環境の変化が激しい業界でよく用いられます。
散会期
最後のステップとなる散会期は、チームの目的・目標を達成し、解散する時期です。それぞれのメンバーは、そのチームでの役割を終えて次のプロジェクトへ向かいます。
ここでリーダーが行うべきことは、各メンバーが満足感を得られる“解散”にすることです。
「このチームに参加してよかった」
「このチームで、自分は成長できた」
といった感覚をもって離れられるよう、1on1などで感謝とフィードバックを伝えるとよいでしょう。
- そのメンバーが具体的に何でどう活躍したのか
- チームにどのように貢献してくれたのか
- そのメンバーの強みは何か
といったポジティブ・フィードバックを行い、次の飛躍に向けた激励の言葉を贈ってください。
チームビルディングの実施形態別の手法
タックマンモデルの解説の中で、ステップに応じたチームビルディングの手法をご紹介しました。具体的な手法は、ほかにも多数あります。
そこで、本項では「いつ・どのようにやるか」という実施形態の観点から、さらにいくつかの手法をご紹介します。
日常業務や休憩時間でのやり方
メンバー同士の交流と相互理解を深めるという観点で重要な取り組みは、日々のあいさつや声のかけ合いです。あいさつは「あなたがいることに気づいています」と伝える基本手段であり、声のかけ合いは協働体制の基本だからです。
声かけの具体例としては、
- 進捗が遅れているメンバーに対してサポートを申し出る
- 業務の不明点や手伝ってほしい点が出てきたときに、サポートを依頼する
- 休憩時間になっても根を詰めて業務を進めているメンバーに、休憩時間であることを知らせたり、食事などに誘ったりする
などが考えられます。
また、朝礼・終礼も情報共有や相互理解の深化に活用可能です。朝礼では、その日に取り組むタスクや抱えている課題を報告することで、「誰が何をしているのか」を確認できますし、他のメンバーからアドバイスを受ける機会にもなります。
ランチ会や飲み会では、業務を離れた交流ができます。形成期で気軽なコミュニケーションが難しい場合は、話しやすいテーマを設けるとよいでしょう。その場合、意見が対立しやすいテーマや否定的な言い回しは避けることが成功のポイントです。
ゲーム・アクティビティ・イベントでのやり方
お互いの緊張をほぐしたいときや人間関係構築のきっかけを作りたいとき、協働して動く体験の場を設けたいときは、ゲーム・アクティビティ・イベントといった施策がおすすめです。
例えば、ゲームでは「共通点探し」「マシュマロチャレンジ」「ペーパータワー」が有名です。いずれも屋内でできるゲームです。
【チームビルディング・ゲームの具体例】
| ゲーム名 | やり方 |
|---|---|
| 共通点探し |
|
| マシュマロチャレンジ |
|
| ペーパータワー |
|
アクティビティの場合、ゲームよりも活動的なため、チームの一体感をより高めることができます。試行錯誤の中で失敗の原因を分析したり、戦略を立てたりする機会にもなるでしょう。
アクティビティの例には、「NASA」や「脱出ゲーム」があります。NASAは社内でもできますが、脱出ゲームは社外の法人向けサービスを利用すると便利です。
【チームビルディング・アクティビティの具体例】
| アクティビティ名 | やり方 |
|---|---|
| NASA |
|
| 脱出ゲーム |
|
イベントは、アクティビティよりも規模が大きな施策です。活動時間や役割分担にかかる負担が大きくなりますが、「皆で一緒に達成した」という充実感が大きくなるでしょう。具体的な取り組みは、スポーツ大会やバーベキューなどです。
スポーツ大会は、戦略を立てたり競技の練習をしたりなど、イベント以外の時間も交流や協働体制を促進させるチャンス。バーベキューでは、食材の準備や調理、片付けの分担など、「食べて話すだけ」ではない参加ができるよう工夫すると、より協力して楽しむことができます。
研修・セミナー・ワークショップのやり方
ビジョン浸透や知識・スキルの向上といった座学向きの取り組みには、研修・セミナー・ワークショップなどがおすすめです。
チームビルディングにおいて求められるビジネススキル、マネジメントには、例えば下表のようなものがあります。
【研修・セミナー・ワークショップなどの例】
| 研修・セミナーのテーマ | 内容例 |
|---|---|
| 管理職向けのチームビルディング研修 |
|
| セルフマネジメント |
|
| 傾聴・質問力 |
|
| 伝え方 |
|
以上は、様々な企業の人材育成をお手伝いしてきたALL DIFFERENTが実際にチームビルディングに役立つ研修としてご提供している内容でもあります。具体的には、次のような研修です。
「ストーリーで学ぶ ビジネスリーダー研修~ビジョン・仕事の構想浸透/チームビルディング編~」研修の詳細はこちら
「セルフマネジメント研修~ハイパフォーマーが実践するセルフマネジメント研修~」研修の詳細はこちら
「伝え方研修~相手に理解・納得してもらうための伝え方~」研修の詳細はこちら
体系的な知識や方法を習得することで、より効果的なチームビルディングの実現につながります。
オンラインでのやり方
オンラインでチームビルディングを進める場合は、会話中心で成立する手法が適しています。具体的には、座学やグループディスカッションを扱う研修・セミナー、コミュニケーションの促進を目的として行う「共通点探し」や「NASA」が実施しやすいでしょう。
ほかに、コロナ禍で普及したオンラインランチ会、オンライン飲み会などもあります。ランチ会や飲み会に必要な食事については、経費で注文して各メンバーの自宅に配達されるサービスも利用できます。普段とは異なる食事を楽しみながら会話ができますので、“特別感”の演出によいでしょう。
チームビルディングの効果を高める3つの大切なこと
このように、チームビルディングの具体的な手法は多岐にわたります。ただ、これらを漫然と実施しても、なかなか効果は現れません。
効果的なチームビルディングには、
- 目的・目標設定を行う
- 役割分担と自主性を尊重しつつ、放任主義にならない
- 情報共有と心理的安全性を意識する
という3点が非常に重要です。
目的・目標設定を行う
チームビルディングには、チームのビジョン浸透や成果を出すためのチーム作りといった目的がありました。このために多くの具体的な施策を行いますが、施策そのものにも、「なぜそれをやるのか」という観点が必要です。ゲームにせよアクティビティにせよ、それを実施することでメンバーに何を得てほしいのかを必ず設定しましょう。
目的・目標をメンバーに説明して理解してもらうことは、そうした取り組みに参加する納得感を高めます。目的・目標と手段の関係が明確になるため、取り組みの中で「これはどうする?」という疑問が出ても、目的・目標に立ち戻って判断できますし、その後の現場にも気づきを活用しやすくなるからです。
なお、目標設定の際に役立つフレームワークに「SMARTの法則」があります。SMARTの法則を意識すれば、ただやみくもに「頑張ろう」と言うだけではない、明確でわかりやすい目標を設定できるでしょう。
【SMARTの法則】
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| S | 具体性(Specific) | 第三者が見てもわかりやすい具体的な目標を設定する |
| M | 定量性(Measurable) | 達成感がわかりやすい指標を使った定量的な目標を設定する |
| A | 現実性(Achievable) | メンバーにとって達成可能な現実的な目標を設定する |
| R | ビジョンとの関連性(Related) | 組織のビジョンに関連している目標を設定する |
| T | 期限(Time-bound) | 目標達成の期限を設定する |
SMARTの法則は、チームビルディングの施策だけでなく、プロジェクト管理にも便利なフレームワークです。様々な場面で5つの項目を意識すると、より効果を出せるチーム作りができます。
役割分担と自主性を尊重しつつ、放任主義にならない
チームの機能性を高めるには、メンバー一人ひとりの役割の明確化および自主性の尊重と、適切なサポートが重要です。「メンバーの自主性に任せているから」という理由で放任主義になってはいけません。
放任主義の弊害は、全ての判断をメンバーに丸投げし、チーム全体が方向性を失い、結束力を弱めてしまう恐れがあることです。これを防ぐには、メンバーを放置するのではなく、誤った判断や対応があった場合やメンバーが悩んでいる場合に、リーダーがその原因と対処法を本人やチームと話し合い、進め方の方向性を定める必要があります。このとき、頭ごなしに否定したり一方的に叱ったりすると逆効果ですので、あくまで対話を前提に進めてください。
役割分担についても、一方的にリーダーが割り振るのではなく、本人の仕事に関する希望と得意分野に合う役割にすると、各メンバーの当事者意識を高められます。責任をもって主体的に動くマインドが醸成されますので、あとはメンバー同士がサポートし合えるよう、全体のバランス調整や声かけを行いましょう。
情報共有と心理的安全性を意識する
そして、常に情報共有と心理的安全性に配慮することが重要です。情報共有はチームの円滑な活動には不可欠であり、心理的安全性は建設的な話し合いと解決策の模索ができる環境の大前提だからです。
情報共有が適切に行われない場合、重要な情報を特定のメンバーだけが知っている状態になります。これを知らない他のメンバーは、次の行動に移れなかったり、知っておくべき情報を得られず判断を誤ってしまったりするでしょう。
なお、共有すべき情報は大きく4つに分類されます。いずれも成果を出すために必要な情報ですので、これらがきちんと共有されているかどうかを日々確認しましょう。
【共有すべき4つの情報】
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 業務に関する情報 |
|
| 顧客に関する情報 |
|
| 活動に影響を与えそうな外部環境の情報 |
|
| 目標達成のための計画・指標・進捗 |
|
心理的安全性については、組織やチーム内で安心して自身の意見を発信できる“風通しの良い”環境を作り、維持します。
これには、
- 意見の内容が人事評価に影響しないという前提の共有
- 他のメンバーや常識と異なる意見を出しても、人間性を否定しないという前提の共有
- お互いの個性や能力の違い、価値観の多様性を尊重する文化の醸成
- 意見を否定される場合でも、根拠と結論の妥当性、結論がもたらす周囲への影響が検討される文化の醸成
などを進めると効果的です。
心理的安全性については、以下の関連コラムでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
チームビルディングの成功には管理職から学びの更新を
以上のように、チームビルディングはチームリーダーがトップダウンで一方的に進めるものではありません。成果を出すチーム作りには、メンバーと協働しながら一緒に結束力を高め、一丸となって動ける関係性構築、環境作りが欠かせないのです。
これを実現するには、まずリーダーとなる管理職やリーダー職の人材が、チームビルディングを体感的に学ぶとよいでしょう。
ALL DIFFERENTでは、「1人で仕事をする」から「チームで仕事をする」へ移行するための知識・スキルを体感的に学べる研修をご提供しています。今回ご紹介したタックマンモデルに基づき、リーダーとして行うべきアクションも実践的に解説。ワークショップで他の受講者と協働しながらご理解いただけます。
チームの在り方や、成果をあげるチーム作りにお悩みの方は、ぜひご活用ください。