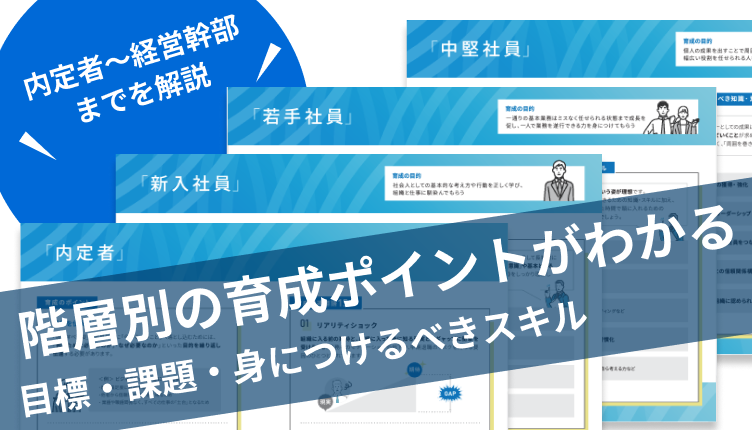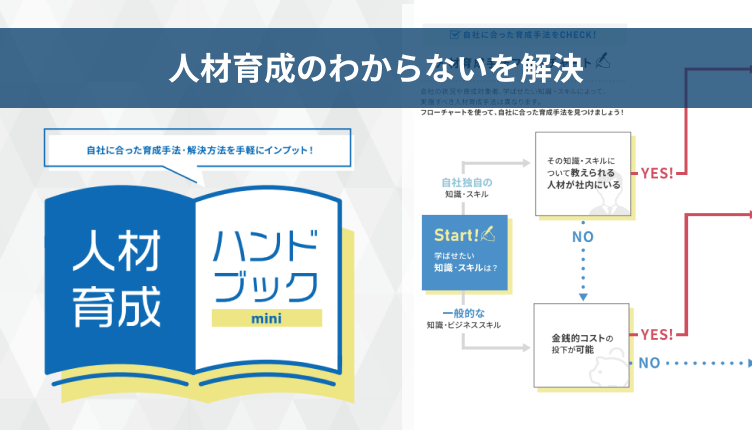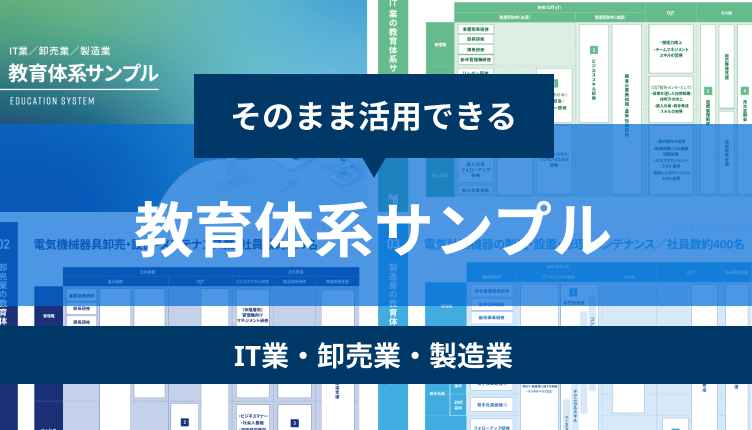シナジーとは?意味と効果、ビジネスでの活用法を解説
 更新日:2025.07.03
更新日:2025.07.03
 公開日:2024.09.27
公開日:2024.09.27

ビジネスの世界でよく耳にする「シナジー」という言葉。シナジーとは、単なる協力関係以上の価値を相乗効果により生み出すことですが、企業の成長戦略において重要な役割を果たします。
本コラムでは、ビジネス上のシナジーの意味や使い方、シナジーを生み出す方法や実際の事例などについて解説します。
シナジーとは何か?基本的な意味と使い方
「1+1が2以上になる」とも表現されるシナジー効果は、現代のビジネスシーンにおいて、企業の成長戦略や経営判断における重要な概念として注目されています。
まずは、シナジーの基本的な意味から、ビジネスにおける具体的な効果まで、詳しく見ていきましょう。
シナジーの意味と使い方
シナジーは英語で「synergy」と表し、ギリシャ語の「syn(一緒に)」と「ergon(働く)」に由来する言葉です。日本語の訳語としては「協働」や「相乗作用」などといった言葉が充てられます。
つまり、シナジーとは、複数の要素が組み合わさることで、個々の合計以上の効果や価値を生み出す現象を指します。
ビジネスや経営学におけるシナジーの意味
シナジーという言葉はビジネスでもよく用いられています。例えば、異なる強みを持つ企業同士のM&A(合併・買収)を考えてみましょう。この場合、互いの弱点を補い合い、新たな顧客層を獲得できるといった効果が期待できます。企業内で部署間が連携したり、既存の事業に加えて新規事業を立ち上げたりする場合でも、同じような効果が期待できるでしょう。このような状況で、「シナジーを生み出す」「シナジー効果を追求する」などの表現が用いられるのです。
シナジーという概念を経営学に最初に取り入れたのは、「戦略的経営の父」と呼ばれた経営学者イゴール・アンゾフだといわれています。アンゾフは、製品・サービスやミッションを組み合わせることでお互いのシナジー効果が生まれる「アンゾフの成長マトリックス」と呼ばれるフレームワークを提唱しました。*1
また、成功哲学・ビジネス哲学の名著といわれているスティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』でも、第6の習慣として「シナジーを創り出す」が挙げられており、ビジネス上でシナジーを活用することの重要性が注目されています。*2
*1 参考:J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] | 経営ハンドブック |アンゾフの成長マトリックス
*2 参考:フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社|7つの習慣®「第6の習慣 : シナジーを創り出す」
医療・ゲームなどのシナジーの意味と使われ方
シナジーとは、生物学や薬学などで用いられていた言葉です。そのため、医療用語としては、「(筋肉や神経などの)連動・協力作用」や「複数の薬品を組み合わせた相乗効果」などの意味で使われます。
また、最近ではゲーム用語としてシナジーという言葉が使われています。ゲーム用語としてのシナジーは、オンラインゲームで複数人が連携してプレーすることで大きな効果を生み出すという意味です。
シナジーという言葉の普及に伴い、特定の業界では独自の意味で使われているケースがあるので注意しましょう。
アナジー効果とは
アナジー効果とは、シナジー効果の逆で、複数の要素が組み合わさった結果、マイナスの効果が生じたり価値が減少したりする現象を意味する言葉です。「負のシナジー効果」や「マイナスシナジー」と呼ばれることもあります。
ビジネスにおけるシナジー効果は、基本的には双方に利益のあるWin-Winの関係を目指すものですが、必ずしも成功するわけではありません。ときにはアナジー効果が生じ、負の結果をもたらす場合もあります。
具体的な例としては、M&Aの際に異なる企業文化の衝突によって社員のモチベーションが低下し、結果として生産性が落ちてしまうケースなどが挙げられるでしょう。
ビジネスでシナジー効果を目指す際は、常にアナジー効果のリスクも念頭に置いておく必要があります。
ビジネス上のシナジー効果とは?その種類と特徴
ビジネス上のシナジー効果とは、複数の企業や部門などを組み合わせ協働させることにより、足し算以上の相乗効果を生み出すことです。
シナジー効果を企業活動における機能や領域で分類すると、主に以下の3種類に分けられます。
- 事業シナジー
- 財務シナジー
- 組織シナジー
それぞれの特徴と具体例を見ていきましょう。
事業シナジー
事業シナジーとは、複数の事業や企業が協力し合うことで、単独時よりも大きな経済的利益を得られるような相乗効果を指します。
【事業シナジーの具体例】
| シナジー効果 | 具体例 |
|---|---|
| 売上の増加 | 新たな販売チャネルの獲得や顧客基盤の拡大 |
| コスト削減 | 重複部門の統合や規模の経済による調達コストの低減 |
| 技術力の向上 | 異なる技術やノウハウの融合による革新的な製品開発 |
例えば、自動車メーカーと電機メーカーの提携によって高性能な電気自動車の開発が可能になるケースが、事業シナジーに該当します。
財務シナジー
財務シナジーとは、企業の合併や統合などによって得られる経済的メリットのうち、特に財務面に関する相乗効果を指します。
【財務シナジーの具体例】
| シナジー効果 | 具体例 |
|---|---|
| 資金調達力の向上 | 企業規模の拡大による信用力の向上 |
| 税務上のメリット | 繰越欠損金の活用による節税効果 |
| 資本効率の改善 | 余剰資金の有効活用や投資機会の拡大 |
例えば、安定収益を誇る企業Aが、成長力は高いものの資金繰りに苦しむ企業Bを買収するケースを考えてみましょう。企業Aの安定した収益性や財務基盤、Bの将来性や成長性とのシナジー効果で、資金調達力の改善が期待できます。
組織シナジー
組織シナジーとは、企業内で組織や社員が互いに協力し合うことで、単独での活動よりも大きな成果を上げられるような相乗効果を指します。
【組織シナジーの具体例】
| シナジー効果 | 具体例 |
|---|---|
| 人材の最適配置 | 異なる部門間での人材交流による新たな価値創造 |
| 組織文化の融合 | 多様な価値観や働き方の融合によるイノベーションの促進 |
| 知識やスキルの共有 | 部門を越えた情報共有による業務効率の向上 |
例えば、営業部門と研究開発部門の連携によって、顧客ニーズに即した製品開発が可能になるケースが挙げられます。
シナジーのビジネス上の使い方や例文
シナジーは、ビジネスの様々なシーンで活用され、組織やチームにとって重要な成功要因となります。
ここでは、シナジーのビジネス上の例文や組織でシナジーを具体的に活用する方法について解説します。
会話例文1「シナジーを生み出す」
ビジネス会話の中で「シナジー」を適切に使うことで、プロジェクトやコラボレーションにおける期待感を効果的に伝えることができます。
「シナジーを生み出す」の例文
「このプロジェクトでは、異なる部署の専門知識が集まり、大きなシナジーを生み出せるでしょう。」
「新商品の開発において、マーケティング部と技術部が協力してシナジーを最大化することを目指します。」
「この商品は、既存の商品ラインナップと組み合わせることでシナジーを生み出し、顧客満足度を向上させられるでしょう。」
会話例文2「シナジーを感じる」
「シナジーを感じる」という表現は、協力や統合の中で生まれる調和や一体感を示す際に使われます。
「シナジーを感じる」の例文
「今回の提携で、当社と貴社の間に明確なシナジーを感じます。」
「異なるバックグラウンドを持つメンバーが一緒に働くことで、シナジーが実現しています。」
「先日の合同会議では、異なる部署の視点がうまく合致し、シナジーを感じる瞬間が何度もありました。」
チームや組織内でのシナジー活用法
シナジーを活用するには、チーム内の強みを引き出し、それを連携させる仕組みが重要です。具体的な活用方法としては、例えば以下のようなものがあります。
- クロスファンクショナルなチーム編成
- オープンなコミュニケーション
- 明確な目標と役割分担
クロスファンクショナルなチーム編成とは、異なる専門分野やスキルを持つメンバーを集め、相互に補完し合う形でチームを編成することです。例えば、営業と技術部門が共同で顧客課題を解決するプロジェクトを立ち上げることが挙げられます。
また、情報をオープンに共有し、全員が同じ目標を意識することで効果的な協力体制を築けます。ミーティングやツールを活用すれば、さらにコミュニケーションを円滑化できるでしょう。
チームでシナジー効果を高めるためには、チーム全員が共有する目標を設定し、それに向けた具体的な役割を明確化することも重要です。
シナジー効果を生み出す方法とプロセス
ビジネスでシナジー効果を最大限に活用するには、目的に応じた戦略的アプローチが不可欠です。
ビジネスの現場で実践されているシナジー効果を生み出す4つの主要な方法を紹介します。
業務提携によるシナジー効果
業務提携は、異なる技術や商品を持つ企業同士が協力関係を結ぶことで、シナジー効果を生み出す経営戦略です。技術開発や販売ルートの共有・拡大などを通じて、お互いの経営課題の解決を目指します。
例えば、人材紹介企業と人材教育企業が業務提携した場合、単独で行うよりも、求職者に対してより総合的なサービスが提供できます。結果、市場での競争力強化や企業価値の向上といったシナジー効果が得られるでしょう。
M&A(企業買収)でのシナジーの実現
M&Aは、既存事業の拡大や新規事業参入、節税効果などを目的とした経営戦略です。買収する側の企業にとっては、時間や費用を抑えながら事業を拡大できるメリットがあります。一方、被買収企業にとっては、事業の継承や発展、企業存続などのメリットが期待できます。
財務面でも、売上増加、リスク分散、スケールメリットによる仕入れコスト削減など、様々なシナジー効果を期待できるのがM&Aです。
多角化戦略とシナジー
多角化戦略は、主力事業とは異なる分野への進出を図る戦略です。
多角化戦略は、以下の4つのタイプに分類されます。
| 水平型多角化戦略 | 同じ業界内で新しい製品やサービスを展開する戦略 |
|---|---|
| 垂直型多角化戦略 | サプライチェーンの上流または下流に事業を拡大する戦略 |
| 集中型多角化戦略 | 既存の技術や市場を活用して新事業を展開する戦略 |
| 集成型多角化戦略 | 既存事業と全く関連のない新事業に進出する戦略 |
具体的な例としては、オンライン小売りを主力事業としていた企業が、テクノロジーを基盤にクラウドサービスやAI関連の分野に進出するケースなどが挙げられます。多角的に事業を展開することで、売上や収益の拡大、リスク分散、企業価値の向上など、多くのシナジー効果が得られます。
グループ一体経営
グループ一体経営は、グループ会社を複数持つ企業が、共通業務を一体化させることでシナジー効果を生み出す経営戦略です。
例えば、共通業務を統合することで、業務の効率化やシステムの一元化が進み、大幅なコストカットにつながる可能性があります。
また、グループ全体の経営体制をシンプルにすることで、意思決定のスピードアップや経営資源の効率的な活用が実現できるでしょう。
さらに、グループ全体で顧客情報を共有すれば、個々の顧客ニーズに合わせた商品やサービスの提供が可能となり、顧客の利便性や満足度の向上が期待できます。
シナジーの具体的な効果とメリット
ビジネス上のシナジーの意味や活用法について解説しましたが、シナジー効果によりどんなメリットがあるのでしょうか。
シナジーを生み出すことは、一時的な効果だけではなく、企業にとって持続的な成長を可能にするための重要な要素となります。
シナジーがもたらす具体的な効果とメリットについて解説します。
収益の向上
ビジネス上のシナジーは、収益を向上させる大きな原動力となります。例えば、異なる分野の企業が協業することで、新しい製品やサービスを開発し、新たな市場を開拓することが可能です。あるいは、既存のリソースを共有して効率的に活用することで、収益性の高いビジネスモデルを構築できます。
実際、異業種提携によるシナジー効果で、新商品の市場投入に成功した企業が増えています。このように、シナジーは売上を拡大するだけでなく、販売チャネルの拡大や収益源の多様化などにより、利益率を高めるためにも重要な役割を果たします。
コストの最適化
シナジーは、コスト削減にも寄与します。例えば、複数の部門や企業が連携して業務プロセスを統合することで、重複する作業やリソースを削減できるでしょう。特に、物流や調達業務の統合は、スケールメリットを活かしコストの大幅な削減が期待できます。
また、M&Aにおいても、同種の事業を持つ企業同士が統合することで、本部やシステムを統合するなどして経費を最小限に抑え、組織を効率的に運営することが可能です。
競争力の強化
シナジーは、競争力の強化にもつながります。異なる企業や部門が技術やノウハウを融合させることで、革新的な製品・サービスを創出できる可能性があります。例えば、技術力のある企業とマーケティング力のある企業が提携すれば、競争力の高い製品を迅速に市場に投入できるでしょう。また、シナジー効果で得られる規模の経済やブランド力の向上も、競争優位性を高める要因となります。
このように、シナジーを活用することで、企業は多様な顧客ニーズへの対応力を向上させ、市場でのポジションをさらに強化できます。
経営資源の有効活用
シナジー効果は経営資源の有効活用にもつながります。例えば、企業同士が合併する際、コストのかかる大型の施設や設備を共同で利用すれば稼働率が向上して、有効に活用できるでしょう。
事業規模が大きくなることで、財務体質が強化され、資金調達力が向上するなどの効果も期待できます。また、常に人材が不足している企業では、人材配置も場当たり的な対応になってしまいがちです。提携やM&Aなどにより人材の量・質ともに改善すれば、最適な人材配置や能力開発・人材育成などを行う余裕が生まれ、結果的に貴重な人的資本の有効活用につながります。
シナジー効果を活用した成功事例とシナジーを生み出すためのポイント
ビジネス上でシナジー効果を生み出すことには様々なメリットがありますが、実際にM&Aや業務提携などの手法を活用する場合には、ハレーションやデメリットが生じるリスクがあるのも事実です。
最後に、実際にシナジー効果を活用した企業の成功事例と、シナジーを生み出すために気をつけるべきポイントを解説します。
事例(1)M&Aによるシナジー:資生堂の米国ベンチャー企業買収
化粧品大手の資生堂は、2017年にアメリカ連結子会社を通じて米国のベンチャー企業Giaran, Inc.の企業買収を行いました。GiaranはAI技術を駆使して、ディープラーニングや予測モデリングなどの新しいアルゴリズムを開発するベンチャー企業です。
GiaranのAI技術をメイクアップのアドバイスやカラーマッチング、顔の測定、肌色判定などに活用し、商品・サービスのビューティーパーソナライゼーション化を推進することが買収の目的です。これにより、新たな市場開拓や製品ポートフォリオの拡充、ブランド力の向上などのシナジー効果が期待できます。
事例(2)多角化経営によるシナジー:ファミリーマート
コンビニエンスストア大手のファミリーマートは、以下のような事業多角化を行っています。
- ENEOSとの提携、ガソリンスタンドの併設
- コインランドリー併設店舗
- フィットネス事業への参入
- ファミペイなど金融事業への参入
- デジタルサイネージ広告事業の開始
ファミリーマートは、小売大手との資本提携だけでなく、ガソリンスタンドやコインランドリー、フィットネス事業など多様な事業を展開しているのが特徴です。最近では、ECやファミペイなどデジタル金融サービスを強化しているほか、デジタルサイネージを活用した広告・メディア事業も展開しています。こういった事業の多角化により、収益を安定させるだけでなく、サービスの差別化やブランド価値向上などのシナジー効果を創出しているのです。
シナジーを意識した組織づくりのポイント
ビジネス上でのシナジー効果は、双方にメリットがあり、市場に新しい価値が生まれる点が魅力ですが、協業や提携、M&Aによる軋轢が生まれ、マイナスの効果をもたらす危険もあります。
最後に、企業が持続的な成長を行うため、シナジーを意識した組織づくりのポイントを解説します。
異なる組織や企業文化間での軋轢が生じるリスクを和らげる
シナジー効果を狙って協業や提携を行う際には、異なる組織や企業文化の間で軋轢が生じるリスクを回避する工夫が必要です。現場の職員に協業や提携の意義・目的について十分に時間をかけて説明する、双方のメンバー間でコミュニケーションを活性化できるイベントを企画するなど、できるだけ相互理解を深め軋轢を生じないように工夫しましょう。
リスク管理や情報管理を徹底する
業務提携やM&Aなどを検討する際には、リスク管理や情報管理を徹底してください。特に社外のパートナーと交渉する際には、事前に情報がリークされる恐れや、内部者によって機密情報が洩れるリスクなどを精査し、管理を徹底することが重要です。
顧客や外部に混乱や不安を与えないようにする
シナジー効果を狙って、組織を変更したり社外パートナーと提携・協業したりする際には、既存の顧客や取引先などに混乱や動揺を与えないように配慮することも大切です。必要に応じて、個別説明の実施や問い合わせ窓口の一元化などの対応を行うとよいでしょう。