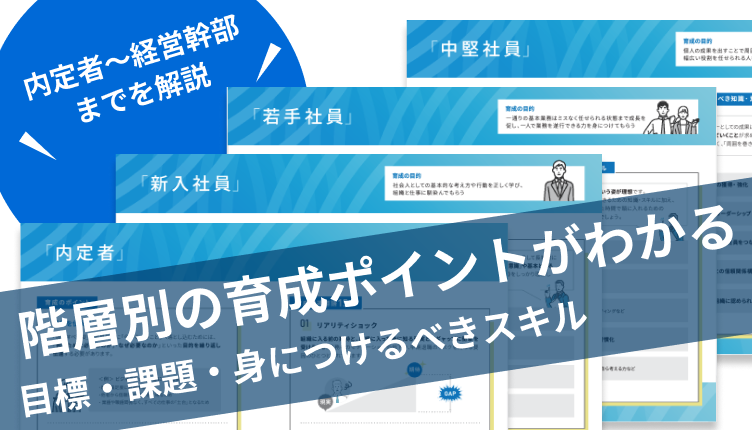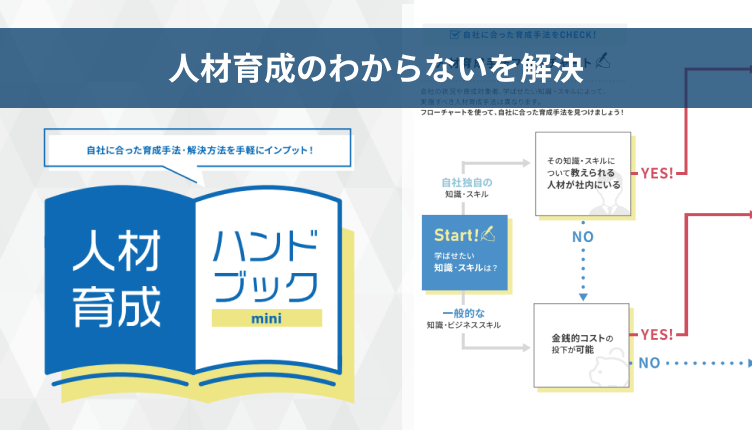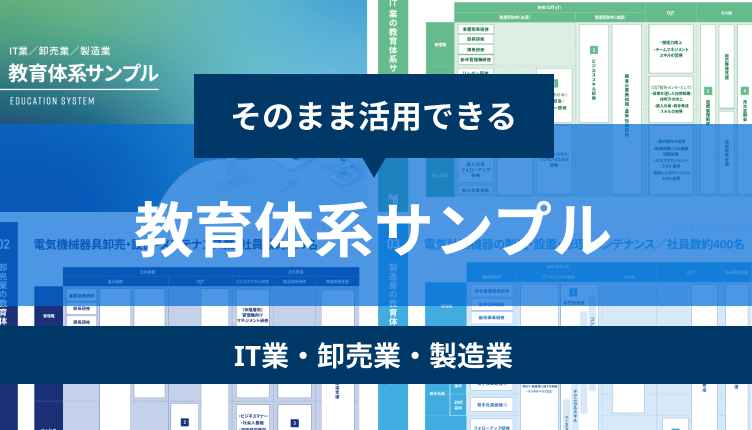自主性とは?企業にとってのメリットと自主性がある部下を育てる方法
 公開日:2025.02.10
公開日:2025.02.10
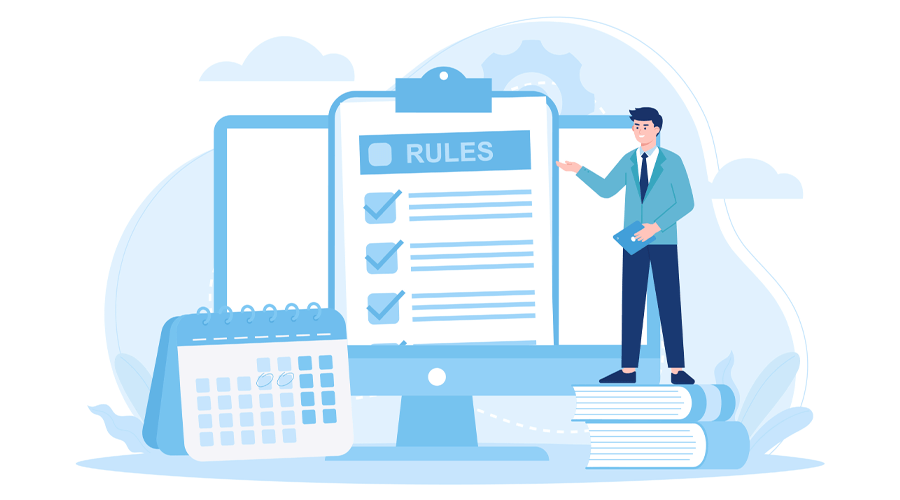
自主性とは、ビジネスにおいてはルールにしたがい率先して行動する姿勢を意味します。ただ、課題解決や対応において「部下の自主性に任せる」と言うだけでは、必ずしも明瞭ではありません。本コラムでは、自主性とは何か、自主性がある人の行動傾向や企業にとってのメリット、自主性のある部下を育てる方法を解説します。
自主性とは?辞書的意味と自発性・自律性との違い
自主性の意味について、まずは広辞苑における説明とビジネスで求められる「自主性に任せる」の意味合いを比較しながら確認していきましょう。類語として言及されることが多い「自発性」「自律性」との違いもご紹介します。
「自主性に任せる」の意味
「自主性」の意味を広辞苑で調べると、「他者に依存せず、自分で行動することができる性質」とあります*。
言い換えれば、「誰かに指示されなくても、率先して自分から動くことができる性格・態度」となるでしょう。
ビジネスにおける自主性は、こうした基本的な意味に加えて「会社のルールにしたがう」という枠組みがあります。
わかりやすい例でいえば、「始業・終業時にあいさつをする」というルールなら、必ず始業・終業時に自分から元気にあいさつをすること。「来客へのお茶出しは新人が担当する」というルールなら、上司や先輩社員に言われずとも自分で来客に気づき、お茶を出すことです。また、適切なお茶の入れ方や出し方を自ら進んで練習することも、自主性の発揮です。
したがって、何らかの業務を遂行する際に「部下の自主性に任せる」と伝える場合、それは「会社や法令が定めるルールにしたがい、率先して行動する姿勢に任せる。具体的な指示は原則として出さない」という意味合いになります。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
自主性と自発性の違い
自主性の類語の1つに「自発性」があります。自発性の辞書的な意味は「ほかからの教示や影響によるのでなく、内部の原因・力によって思考・行為がなされること」*。
類義語には「自動性」があげられており、対義語は「受動性」です。
ビジネスにおける自発性の意味合いをより具体的にいえば、「周りから指示・指摘されなくても自分で意思決定を行い、行動する姿勢」となるでしょう。
自主性と自発性の違いは、自身の内部に行動の理由があるか否かです。自主性の場合は、行動の理由が自身の内部にあっても、あるいは外部にあっても、どちらでも構いません。しかし、自発性の場合は、自身の内部に動機・理由が必要です。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
自主性と自律性の違い
自主性のもう1つの類語である「自律性」は、「外部からの支配や制御から脱して、自身の立てた規範にしたがって行動すること」という意味です*。
ビジネスにおいても概ね同じ意味合いで使われています。
ビジネスで「自律性」が関わる場面は、近年では「自立型社員」や「キャリア自律」などです。これは、仕事の目的や規範を自ら定め、それにしたがって業務や学びを進めること。就業規則などのルールは守らなければなりませんが、自主性よりもさらに個人の意思決定を重視する考え方といえるでしょう。
そのため、自律性におけるルールからの逸脱の許容や本人の意志決定の尊重という点が、自主性とは異なります。
*出典:新村出 編『広辞苑 第7版』岩波書店、2018年
自主性がある人の行動傾向
自主性がある人がどのような人かをより具体的にイメージするには、その行動傾向を見るとよいでしょう。今回は、主な5つの行動傾向をご紹介します。
率先して行動する
1つ目の傾向は、率先して行動することです。自主性がある人は、ルールにしたがって自ら判断し、行動することができます。
特に、自主性のある人は組織のルールが社員に求めていることを理解しており、どのような状況でどのようなルールを適用すべきかをよく理解しています。そのため、指示を待たずに自ら動けるのです。
もし適用すべきルールが不明瞭な場合は、上司や先輩社員に対応方法を相談することもできます。こうした経験の積み重ねにより、対応の柔軟性も獲得していきます。
責任感がある
2つ目の傾向は、責任感があることです。
自主性のある人は、自分に割り当てられた仕事を最後までやり切ります。途中で投げ出せば周囲に迷惑がかかることを理解しているからこそ、組織の一員として行動する責任感があるのです。
基本的には、自身の権限の範囲内でできることを最大限に活用し、取り組みます。仮に達成が困難な課題を与えられたとしても、既存のやり方を応用したり周囲にサポートを求めたりして、完遂を目指すでしょう。
探究心がある
自主性のある人には、探究心もあります。簡単にいえば、課題解決に向けた学びやトライ&エラーをいとわない傾向です。
自主性のある人は、難しい課題に対して「できない」と簡単に諦めるのではなく、「どのようにすれば解決できるか」を考えます。基本的にポジティブ思考であり、失敗も恐れません。失敗は、解決に向けたプロセスの一部にすぎないことを理解しているからです。
自主性のある人は、「失敗を乗り越えて挑戦を続ければ、より良い結果を得られる」と信じて行動するのです。
成長意欲が高い
先述した探究心にも通じることですが、自主性のある人は、成長意欲が高い傾向も見られます。これが4つ目の傾向です。
課題解決に向けた積極的な取り組みは、本人の成長を促します。できなかったことができるようになる、新しい視点で考えられるようになる、周囲のアドバイスから学ぶなど、自主性のある人は知識・スキルの向上に意欲的。自己成長のための努力を惜しみません。
そうした成長が、よりスムーズな業務遂行につながり、成功体験となります。この成功体験の蓄積が、次の学びを促します。
自信がある
5つ目の傾向は、自信です。自信は、自主性のある人がこれまでに取り組んできたトライ&エラーと成功体験、組織への貢献や周囲からの感謝によって形成されます。
たとえ小さな成功体験でも、
「自ら進んで実行できた」
「自分が行動したことで、周りのメンバーや組織に貢献できた」
という実感が生まれます。この実感は、「次も頑張ろう」というポジティブな循環を生み出すでしょう。
ポジティブな循環によって高まるのが、「頑張れば達成できる」「自分には、力がある」という感覚です。
自分に自信があれば、一度や二度の失敗には動じません。提案をして上司や他のメンバーから指摘を受けても、それを自分への攻撃とは捉えず、「改善のためのサポートをしてくれている」と考えられるでしょう。
このような好循環を自ら生み出せる人こそ、自主性のある人といえます。
自主性がない人に見られる失敗の原因
では、反対に自主性のない人にはどのような特徴があるのでしょうか。
自主性のない人は多様な場面でネガティブな反応を示し、これが仕事上のミスや失敗につながってしまうことが少なくありません。今回は、主に4つの例をご紹介します。
組織のルールを軽視する
自主性に欠ける人は、ルールを軽視することが多くあります。ルールの目的を見ずに
「ルールが多い、面倒くさい」
「こんなルールは時代遅れだ」
などとネガティブに考えてしまうからです。
目的を理解するという姿勢がないため、仕事で「○○してはいけない」「必ず△△する」などのルールを定めても、なかなか定着しません。その結果、必要な手順を怠り、ミスやトラブルを招いてしまいます。
他人のせいにする(他責傾向がある)
自主性がない人は、任された仕事への責任感も希薄です。そのため、いざミスやトラブルが発生すると、自身に非があったという発想にはならず、自分以外の誰か・何かのせいにしようとします。いわゆる“他責”です。
責任感が生まれにくいのは、他のメンバーや状況に流れながら行動していることが原因です。「なぜそれをするのか/しないのか」という目的を理解していないことが、責任感にも響いてくるのです。
たとえ不適切なやり方に対して注意を受けても、なぜ注意を受けたのかわからないまま、反発したり言葉だけの謝罪で済ませようとしたりするでしょう。
自己の成長に投資しない
さらに、自主性のない人は「どうすればできるか」よりも「いかに面倒ごとを避けるか」に関心が向く傾向があります。
成長には、失敗経験の分析、行動や考え方の改善が不可欠です。言ってしまえば、いずれも「面倒くさい」ことです。これを乗り越えるには、成長の必要性や学ぶ目的を考え、納得しなければなりません。
しかし、自主性がない人の場合、成長や学びの目的をじっくり考えずに“学ぶ”ことの大変さにばかり注目してしまいます。「こんなことは、自分にとって損だ」という結論に至ってしまうこともあるでしょう。
提案・意見を出せない
以上のような傾向は、自主性のない人の消極的な姿勢を生みます。新しいアイデアや改善提案を求められても、黙ったまま視線をそらし、上司が諦めるのをただ待っていたりするような態度です。ネガティブ思考・他責傾向・学びの少なさにより提案能力が育っていないことが原因として考えられます。
例えば、ルールの改善を検討することになったとしましょう。自主性のない人は、そもそもルールの目的や意義を考えていません。極論すれば「ルールを守るか、無視するか」という二者択一の発想により、その先に進むことが難しいでしょう。
こうした事情から、提案すべき内容を思いつかなかったり、実現不可能な提案をしてしまったりするなど、なかなか建設的な意見を出せないのです。
自主性のある社員が増えることによる4つのメリット
自主性のある人・自主性のない人の傾向から、社員の自主性を高めるメリットが浮かび上がります。自主性のある社員が増えれば、企業にとって以下のようなメリットが生まれるでしょう。
【自主性のある社員が増えることによるメリット】
| (1) | 組織の秩序が守られる |
|---|---|
| (2) | 各メンバーの成長スピードが速くなる |
| (3) | チームワークを発揮しやすい |
| (4) | 生産性向上につながる |
順番に解説します。
(1)組織の秩序が守られる
1つ目のメリットは、組織の秩序が守られることです。
自主性は、定められたルールに納得し、率先して行動する姿勢です。そのため、自主性を身につけた社員が増えれば、社内全体の秩序立った活動を実現できるでしょう。
例えば、コンプライアンスを意識した情報の取り扱いに関して社内でルールを明文化すれば、そのルールにしたがった運用が実現します。社外に漏洩しては困る個人情報を個人的な都合で勝手に持ち出し、あまつさえ個人的利益のためにそれを外部に送信したりはしません。自主性のある社員は、自社の信頼と社員、顧客を守るためのルールだと知っているからです。
ほかにも、休業やハラスメントなどに関する社内制度の活用が適正化され、より働きやすい環境につながるでしょう。
(2)各メンバーの成長スピードが速くなる
2つ目のメリットは、社員それぞれの成長スピードが速くなることです。
企業では、社員の知識・スキル向上のために階層別研修を実施するケースが多く見られます。自主性のある社員は、そうした研修の目的や、自身にどのような役割・スキルが求められているのかを理解しようとします。役割と“あるべき姿”に納得感が生まれれば、そうでない社員よりも習得に向けて積極的に取り組めるでしょう。
自主性のある社員が増えれば、意欲的に自己成長に取り組む社員が増え、やがて組織全体で学ぶ姿勢が育ちます。
先輩社員や上司の学ぶ姿は、後輩・部下の手本となるだけなく、具体的な学びのノウハウの共有にもつながります。ひいては、新入社員の成長もより速く進めることができるでしょう。
(3)チームワークを発揮しやすい
3つ目のメリットは、チームワークを発揮しやすくなることです。
自主性のある社員が増えることは、チームのルールや方針にしたがって業務を行うメンバーが増えること。自主性のある人は、定められた業務フローや方針にしたがって積極的に活動します。決して、「自分がよければ他のメンバーのことはどうでもいい」とは考えません。
「皆で目標を達成する」という目線で行動できるからこそ、困っているメンバーをサポートしたり、自身が困難に直面した際に周囲に助けを求めたりすることもできます。
自主性のある社員が増えることは、チームの方針・目標を理解して周りと連携するメンバーが増えるということなのです。
関連コラム:協調性を高め、組織力を強化する3つのポイントとは
(4)生産性向上につながる
そして、4つ目のメリットは、組織全体の生産性向上につながることです。
チームワークを発揮しやすい環境が実現されることで、組織全体がより連携を強め、一体的に活動できるようになります。これに加えて、自主性のある社員は自己成長にも意欲的。それぞれの社員が成長しながら連携して活動できれば、組織全体の生産性が向上します。
先述したように、もし既存のルールが生産性における課題を生んでいるのであれば、自主性のある社員は、自身の権限の範囲内でルールの改善提案も可能です。ルールの目的を理解しているからこそ、どのように改善すべきかも具体的に考えられるのです。
部下の自主性を高める方法
自主性のある社員を増やすには、経営層や管理職、育成担当者が積極的に育成に取り組まなければなりません。
今回は、特に管理職が部下に接する際に意識すると良いポイントを5つにまとめました。全社的に連携しながら進めると、より効果的です。
組織の理念・目標と期待する役割を伝える
まずは、全てのルールの基盤となる組織の理念・目標を各社員が理解することが重要です。
「なぜそのルールが生まれたのか」「そのルールにしたがうことで、組織にとってどのようなメリットが生まれるのか」といったことを、組織の理念や目標と結びつけて捉えられるようになるからです。
さらに、各メンバーに対して、会社や上司が期待している役割を伝えましょう。会社の中での自身の立ち位置や貢献できる分野といった自覚が促され、「組織の一員である」という実感をもてるようになります。
ルールの目的・意義を伝える
組織の理念・目標を理解できれば、それを軸として現場でもルールの理解が進みます。
基本的なビジネスマナーであれば、
- 業務上必要なコミュニケーションを円滑にできる
- 来訪者や取引先、顧客に対して適切な対応ができる
- 対外的な信頼を向上させられる
といった点に納得しながら習得できるでしょう。
組織内のルールの場合も、それが安定した企業活動や売上向上にどのように寄与するかをイメージしやすくなります。先ほど例にあげた情報漏洩を防ぐルールでいえば、
- 顧客の個人情報を社外に持ち出してはいけないのは、置き忘れ・盗難・ウイルス感染による漏洩を避けるため
- 顧客に安心して取引してもらうため
など、情報の取り扱い全体に対する意識づけが行われます。さらに、「クラウドにデータを保存し、会社支給のデバイスで作業を行う」というルールがあれば、その理由をより深く理解して実践できるでしょう。
「手挙げ」の文化を醸成する
部下の自主性を高めるには、自主性を発揮できる機会を多く設定することも重要です。具体的には、研修への参加、アイデアの社内公募、プロジェクトチームへの参加などの機会です。
階層別研修であれば、対象者の意思とは関係なく「参加してください」と通知を出す方法が一般的でしょう。業務に必須の知識・スキルを習得する研修なら、そうした義務的な参加も必要です。
一方で、現在の業務能力からステップアップを図るような研修については、参加したいと手を挙げた社員を優先的に参加させる方法があります。この方法では、社員が自ら手を挙げて参加しているため、「自分の意思でここにいる」という自覚や、より多くのことを研修から学び取る姿勢が生まれます。
研修以外でも、様々な場面で手挙げ方式の活用は可能です。部下が日常的に自主性を発揮できる機会を設定し、「自主性を発揮するとは、どのようなことか」を体感してもらいましょう。
過剰な指示をしない
また、自主性を育てるには、部下が自分でルールや手順を確認して遂行する経験も重要です。
育成の際に陥りやすい状況の1つに、常に細かい指示を出してしまうというものがあります。しかし、それでは「言われたことにしたがって進める」という経験はできても、率先して物事を進める経験はできません。「いつも指示を出してくれるから、今回も指示が出るまで待っていよう」という“指示待ち”の態度を育ててしまう恐れもあります。
ルールや手順といった守るべき枠組みを伝えるのは大切なことです。そのうえで、最初に手本を見せながら教えたあとは、本人がどのくらい自分で遂行できるかを試せる時間を与えましょう。
業務を進める様子を見守る際も、横から逐一指摘・助言するのではなく、質問しやすい環境を整えて待つ時間を意図的に設けてください。そうすることで、部下は自分でできるか試す、自分から質問をするといった自主性を発揮しやすくなります。
ポジティブフィードバックを行う
以上のような自主性を高める取り組みにおいては、部下の成果や頑張りの承認も行いましょう。自主性を発揮するには、「自分には能力がある」という実感が必要だからです。これを自己効力感といいます。
自己効力感を育てる効果的な方法は、日々の業務で成功したこと、良い成果につながった行動などを積極的に褒めることです。
例えば、OJTの定期面談では目標達成度の確認とともに、成功ポイントを必ず振り返りましょう。
- どのような点で努力したのか
- どのような成果があったのか
- 継続すべき行動は何か
これらのポイントを本人と一緒に振り返り、ポジティブフィードバックを行います。管理職や育成担当者の立場から見て「この行動はよかった」など、今後も継続してもらいたい部分を伝えてください。
改善すべき課題が部下にあるとしても、まずは本人の努力を承認し、良かった点を見つけて褒めることが重要です。そのためにも、日頃から部下の業務の進め方や仕事に対する姿勢を観察しておきましょう。
自主性を育てたい管理職のための人材育成研修
部下の自主性を高めるには、管理職や育成担当者の方にも人材育成スキルが必要です。特に、育成対象者が自ら考える姿勢を促し、その努力を承認して適切なフィードバックを行うスキルが欠かせません。
様々な企業の人材育成に伴走してきたALL DIFFERENTでは、管理職の方を対象にコーチングやフィードバックスキルの習得・向上をサポートする研修をご提供しています。ワークショップおよびケーススタディで現場の状況に即して人材育成のポイントを理解できるプログラムとなっています。自主性のある社員を増やしたいとお考えの管理職の方、人材育成のご担当者の方は、ぜひご活用ください。