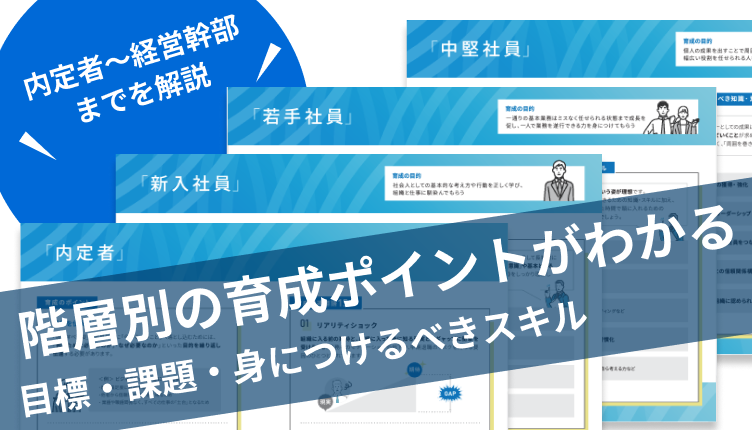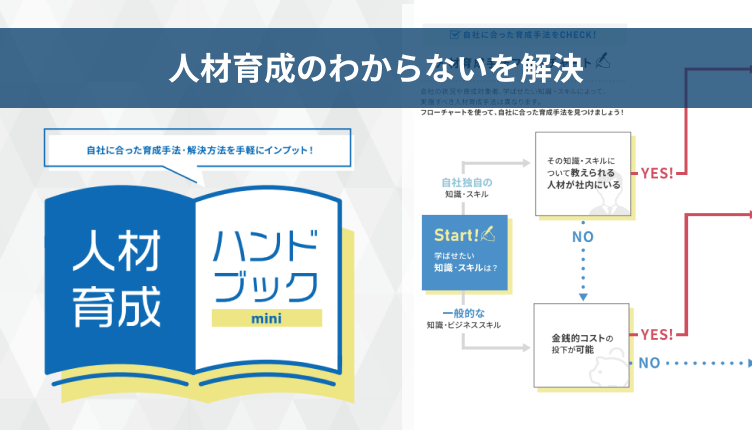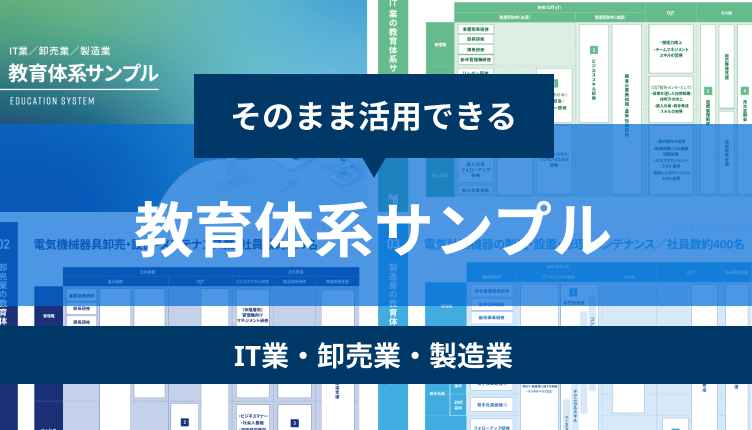業績連動賞与とは?計算方法・メリット・デメリットと導入のポイント
 公開日:2024.06.20
公開日:2024.06.20

業績連動賞与は、組織の業績を指標として支給額を決定する賞与制度。賞与による経営圧迫リスクを軽減できますが、従業員に理解しやすく経営計画に連動した指標を設定しなければ、効果が半減してしまう方法です。
本コラムでは、業績連動賞与の導入に当たって知っておくべき指標の種類や支給時期の例、メリット・デメリット、導入のポイントなどをご紹介します。
業績連動賞与とは
はじめに、業績連動賞与とは何か、その定義や一般的な計算方法を見ていきましょう。
業績連動賞与の定義と計算方法
業績連動賞与とは、企業や部門等の組織の業績に応じて賞与の支給額を決定する制度です。一般的には、組織の業績に加えて従業員個人の評価結果も反映します。
組織の業績が向上すれば支給額が増え、業績が低迷すれば賞与の支給自体がなくなりますので、成果主義型の賞与体系といえるでしょう。
業績連動賞与における支給額の計算は、賞与原資の総額を決めたうえで、それを支給対象者に振り分けるという流れで行います。原資総額は、例えば「営業利益の○%」などの形で算出します。
【業績連動賞与 計算式の例】
賞与原資の総額=業績指標による基準×分配する割合(売上の○%など)
→個人の基本額を決定
個人の支給額=個人の基本額×平均支給月数×評価係数
ただし、具体的な計算式は企業によって異なります。賞与として支給する固定の額を定め、それに上乗せする形で算出する場合もあれば、固定額を設定せずに「業績が一定基準を上回らない場合は賞与不支給」とする場合もあります。
経団連の「2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」*によれば、業績連動賞与を導入している企業は全体の約55%。過半数の企業で導入されている背景には、VUCAの時代といわれる近年の外部環境の激しい変化があります。
業績の見通しを立てにくい中で、常に一定額の賞与を支給すれば、経営にとって大きな負担になりかねません。そこで、賞与支給額を業績と連動させ、人件費を変動費化することで、経営の安定を図ろうとしているのです。
*参考:経団連「「2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を発表」
基本給連動型賞与・決算賞与との違い
賞与の支給額を算出する方法には、業績連動型のほかに、基本給連動型賞与と決算賞与があります。
それぞれの主な特徴をまとめたものが、下の表です。
【3種類の賞与制度】
| 賞与制度の種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 基本給連動型賞与 |
|
| 決算賞与 |
|
| 業績連動賞与 |
|
基本給連動型賞与は日本企業でなじみのある賞与体系で、「賞与は月給の○カ月分」という形で示されます。業績連動賞与とは異なり、会社の業績に関係なく支給される点に特徴があります。支給回数は年2回が一般的。年功序列型の給与体系では、ベテラン社員ほど多くの賞与が支給されます。
決算賞与は、事業年度の決算後に利益が出た場合に、それを従業員に還元する形で賞与が支給されます。企業の内部留保を減らし節税することが目的の賞与制度です。決算後の支給ですので、支給回数は年1回が基本です。
決算賞与は、利益が出なければ賞与不支給となる場合があるのは業績連動賞与と同じですが、算定期間に大きな違いがあります。決算賞与の算定期間は1年間、業績連動賞与の算定期間は企業が定めた期間です。
業績連動賞与の指標・条件
業績連動賞与の計算では、業績に関わる指標をもとに賞与支給の有無や原資総額を決定します。この指標の選び方によって、業績連動賞与は以下の5つに分類されます。
- 売上高基準
- 株主価値基準
- 利益基準
- キャッシュフロー基準
- 付加価値基準
売上高基準
1つめの「売上高基準」は、生産高や売上高を指標とするものです。企業全体の売上高等を基準とする場合もあれば、部署別あるいは店舗別とする場合もあります。
売上高基準では、従業員自身の業務状況や個人目標と連動しやすい指標を使います。そのため、従業員にとって理解しやすく、納得感がより高い基準といえるでしょう。
株主価値基準
2つめの「株主価値基準」は、ROA(純資産利益率)、ROE(自己資本利益率)、ROI(投資利益率)などを指標とする基準です。社内視点ではなく、社外の株主視点での評価が基準となる点に最大の特徴があります。
株主や投資家にアピールすることを経営計画に含む場合は、効果的な基準となるでしょう。一方で、社内の従業員にとっては直感的な理解がしづらく、納得感はあまり得られないかもしれません。
利益基準
3つめの「利益基準」は、営業利益や経常利益、当期純利益などの利益を指標とする基準です。先述した経団連の調査では、業績連動賞与を導入している企業の過半数が営業利益を指標にしていると回答しました。
利益基準は、売上高基準と並んで従業員にとってわかりやすい指標のひとつです。
キャッシュフロー基準
「キャッシュフロー基準」は、会社の資金の流れを指標とするものです。支出よりも収入が多い場合に賞与を支給する仕組みとなっています。
キャッシュフロー計算書がもとになりますので、これを読める従業員にとっては、透明性の高い仕組みといえるでしょう。反対に、キャッシュフロー計算書を読めない従業員にとっては、「よくわからない賞与制度」になる可能性があります。
付加価値基準
最後の「付加価値基準」は、粗利益(売上−売上原価・製造原価)を指標とするものです。
注意すべき点は、賞与以外の人件費の扱いです。製造業では製造原価に人件費を含めることができますが、例えば小売業では売上原価に人件費を含めることができません。そのため、人件費を無視した計算式にしてしまうと、経営の負担になる可能性があります。
こうした難しさから、付加価値基準で業績連動賞与の支給額を算出する企業はあまり見られません。
業績連動賞与の導入企業例と支給時期
より具体的なイメージをつかむには、実際に業績連動賞与を導入している企業の基準や支給時期を確認するとよいでしょう。
今回は関西電力株式会社、株式会社西友、山九株式会社の3社をご紹介します。
関西電力株式会社
関西電力株式会社(以下、関西電力)では、2020年度に業績連動賞与を導入しました。業績の指標は単独経常利益を採用しており、経常利益が1250億円を上回るほど賞与額も増えます。反対に、経常利益が基準を下回った場合は、賞与支給について労使で協議することとしました。
関西電力の業績連動賞与導入は、大手電力会社では、はじめての導入として話題になりました。電力小売りが自由化されたことによる競争激化と従業員のモチベーション向上が背景となっています。
株式会社西友
食料品、衣料品、住居用品などの小売りチェーンを展開する株式会社西友(以下、西友)も、業績連動賞与を導入しています。賞与の支給回数は年3回で、夏と冬は固定賞与、3月は業績連動賞与を支給するという仕組みです。
賞与の業績指標は所属別に設定されており、これと個人評価の結果をあわせて支給額を決定します。基準を上回った店舗であればパート・アルバイトの方にも賞与が支給されます。
山九株式会社
物流事業と機工事業を展開し、200件あまりの特許・実用新案・意匠を有する山九株式会社の業績連動賞与は5月に支給されます。業績連動賞与以外にも、6月と12月に賞与を支給しています。
賞与の支給対象者は在籍期間が2年以上の従業員。2023年度の実績は、年3回の支給で86万円〜210万円とのことです。
業績連動賞与のメリット・デメリット
業績連動賞与には、主に経営安定化というメリットがある一方で、支給のタイミングを誤ったり業績の低迷が続いたりした場合は、資金不足になるなどのデメリットもあります。適切な運用に向けて、メリットを活かし、デメリットへの対策を行いましょう。
業績連動賞与の3つのメリット
業績連動賞与の主なメリットは、経営の安定化、従業員の納得感、労使交渉の手間の軽減、従業員のモチベーション向上です。
経営の安定化を図れる
業績連動賞与は、自社に合う指標と基準をもとに業績に連動した支給額を設定できます。業績が悪ければ賞与の支払額は減りますので、経営における負担軽減につながります。
このメリットは、基本給連動型賞与と比較するとわかりやすいでしょう。基本給連動型賞与では、業績に関係なく基本給を基準として算出するため、業績が低迷している状態では経営を大きく圧迫します。
しかし、業績連動賞与では支給額に柔軟性があり、経営圧迫につながる額の賞与支給を回避できるのです。
従業員の納得感やモチベーション向上につながる
業績連動賞与の基準で従業員にとっても理解しやすい指標を用いている場合、従業員は「なぜその支給額なのか」を納得しやすくなるでしょう。計算式を従業員に開示しておけば、より納得感を高められます。
計算式には個人への評価結果も反映されるため、基本給連動型賞与のような「仕事をしていないのに年功序列で高い賞与をもらっている」という不公平感が出にくくなる点もメリットのひとつです。
労使交渉の手間が少ない
基本給連動型賞与の場合、基本給や賞与などの賃上げを毎年労使で交渉する必要があるでしょう。賃上げの労使交渉は、2月から3月に実施される春闘で行われます。
業績連動賞与の場合は、事前に計算で用いる指標や計算式を定めているため、基本給連動型賞与よりも交渉の負担が少なくなります。具体的な計算式について新たに労使の合意が必要な場合もありますが、景気や物価変動などに応じた具体的な支給額の交渉は基本的に不要です。
業績連動賞与の3つのデメリット
業績連動賞与のデメリットは、業績が悪い時期における賞与の有無と個人評価を反映する点に関わっています。いずれにおいても従業員の不満や事業への悪影響を軽減するための対策をとらなければなりません。
支給できないと従業員の意欲低下につながる
業績は、従業員の頑張りだけでなく外部環境の変化にも左右されます。そのため、業績連動賞与で従業員の個人評価が反映されるといっても、そもそも支給基準に達していなければ、十分な賞与を支払えません。
業績連動賞与には、従業員それぞれの努力がなければ業績アップが難しいと同時に、それぞれの努力があっても賞与支給額アップにつながらないケースがあるという問題があるのです。
賞与不支給となれば、従業員の年収に悪影響を与え、意欲低下を招く恐れすらあります。
このデメリットを軽減するには、業績に連動しない賞与制度の併用が考えられます。先にご紹介した西友や山九のような例です。自社の状況に合わせて従業員の安心と柔軟な賞与支給につながる制度を整えましょう。
資金不足になるリスクがある
業績連動賞与の支給時期は企業によって異なりますが、年2回の支給であれば算定期間が約半期ごとになるでしょう。業績連動賞与は業績に応じた支給額の決定ができるため経営圧迫のリスクを下げられます。しかし、支給のタイミングが悪いと、資金不足になる恐れもあります。
問題になるのは、はじめの算定期間で業績が好調なため賞与を支給したあとで、その直後の算定期間で業績が一気に落ちた場合や、大きな支出が必要になった場合などです。
資金不足を避けるには、直前の業績に加えて、その後の経営計画や現実的な原資総額の確認が欠かせません。中長期的な視点をもって指標と計算式を決定しましょう。
個人主義的傾向が高まる恐れがある
基本給連動型賞与と異なり、業績連動賞与では従業員個人に対する評価が反映されやすくなります。すると、賞与支給額を増やすために個人目標の達成や自分だけの業績向上を目指す個人主義的傾向が高まる恐れがあります。
言うまでもなく、事業の成功には個人の努力だけでなく部署やプロジェクト内でのチームプレーが欠かせません。メンバーそれぞれの強みを活かし、苦手を補うことで、組織全体の生産性が高まります。
業績連動賞与に個人評価が反映されることを強調しすぎると、チームプレーが損なわれ、結果として業績の低迷を招くかもしれません。
部門やチームの目標に対する貢献と個人目標の達成のどちらか一方を重視するのではなく、上手なバランスで全体の業績アップにつなげる制度設計と企業風土の醸成が必要です。
業績連動賞与の導入ポイント
以上を踏まえて、最後に業績連動賞与の導入のポイントを見ていきましょう。主なポイントは、目的の明確化、指標・計算式の決定、従業員への周知です。
導入目的を明確化する
業績連動賞与の導入に当たっては、「なぜ導入するのか」という目的を明確にしましょう。
導入するか否か検討する段階で現在の賞与制度に見られる課題を分析すると、目的を見いだしやすくなります。例えば、次のような観点で現状を分析してみましょう。
【現在の賞与制度の課題分析の例】
- 賞与支給の決定に要する時間が大きな負担になっていないか?
- 支給額の計算方法が現状に適しているか?
- 現在の賞与制度は、経営にどのような影響を与えているか?
- 現在の賞与制度は、従業員のモチベーションにどのような影響を与えているか?
業績連動賞与の導入でこれらの課題が軽減・解消されるのであれば、それが導入の目的となります。
業績指標・条件・計算式を決定する
業績連動賞与の導入を決定したら、次は計算に使う業績指標と条件、計算式を決定します。支給回数や支給時期などもあわせて決定しましょう。
どの指標を採用するかは企業によって異なりますので、先述した「業績連動賞与の指標・条件」を確認しながら検討を進めてください。
指標の選定は、「従業員にとっての納得感」と「中長期経営計画に関係する指標」という2つの観点から選んでもよいでしょう。
理解しやすい売上高基準や利益基準は従業員の納得感を高められますし、中長期経営計画で重視している指標を賞与計算に採用すれば、会社全体の経営方針と賞与を連動させられます。比較的変動が少ない項目を指標にすれば、従業員の収入への影響を減らすこともできるでしょう。
なお、業績は常に好調であるとは限りません。支給の有無を決める基準を下回った場合や、基準とほぼ同水準だった場合の賞与支給についても、あらかじめ検討しておくほうが安全です。
基準を下回った場合は一律に「不支給」とする場合もありますが、関西電力の例のように「労使で協議する」と定めておくと、賞与不支給に関わる重大なトラブルの回避につながります。
賞与支給の条件や評価方法を周知する
業績連動賞与の導入と支給額の決定方法、支給時期などを定めたら、従業員に周知しましょう。
業績連動賞与を導入する目的、基準とする指標と数値、計算式、個人評価方法などをしっかり説明することで、賞与制度の透明性を高め、従業員に納得してもらいやすくなります。
それまで基本給連動型賞与を採用してきた場合、「基本給の○カ月分」ではなくなることで、賞与の減額や不支給の可能性が出てきます。これについて、従業員が抱く抵抗感は大きいはずです。
抵抗感や不安を和らげるには、賞与制度の透明性を確保しなければなりません。必要であれば、「計算に使われる指標の変化を定期的にグラフで見られるようにする」といった工夫も行うとよいでしょう。